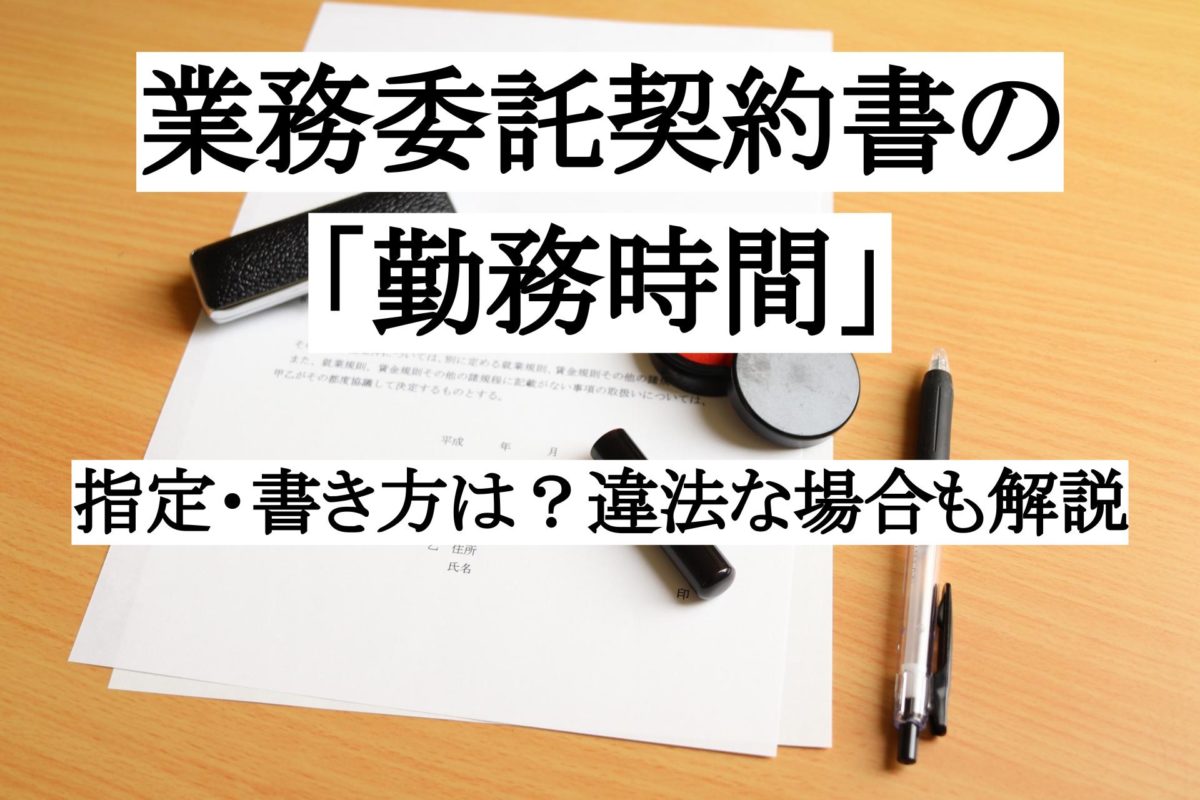業務委託契約において、受託者が物品・製品・成果物を納入する際に、委託者がこれらの受領を拒否する場合や、受領ができない場合があります。
前者を「受領拒否」といい、後者を「受領不能」といい、これらを合わせて「受領遅滞」といいます。
受領遅滞は、受託者にとっては非常に大きな問題となります。
このため、業務委託契約では、こうした受領遅滞(受領拒否・受領不能)があった場合の対応についても、規定しておきます。
このページでは、こうした受領遅滞・受領拒否について、解説していきます。
業務委託契約における受領遅滞(受領拒否・受領不能)とは?
【意味・定義】受領遅滞とは?
受領遅滞は、改正民法第413条では、次のとおり規定されています。
民法第413条(受領遅滞)
1 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
【意味・定義】受領遅滞とは?
受領遅滞とは、次の受領拒否と受領不能の総称をいう。
- 受領拒否とは、委託者が受託者からの納入・業務実施の受領を拒むことをいう。
- 受領不能とは、委託者が受託者からの納入・業務実施の受領ができないことをいう。
受領遅滞は、特に製造請負契約などでありがちですが、製品の納入の際、委託者が、あれこれと理由をつけて受領を拒否するのが、典型的な例です。
受領遅滞の要件は?
受領遅滞が成立するには、次の3つの要件が必要となります。
受領遅滞の要件
- 受領行為を要する債務であること。
- 債務の本旨に従った履行の提供があること。
- 履行遅滞が債権者の責任によるものであること。
受領遅滞の効果は?
受領遅滞が発生した場合、その具体的な効果は、以下のとおりです。
受領遅滞の効果
- 【債務者による自己の財産に対するのと同一の注意義務】「…債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる」こと(民法第413条第1項)。
- 【債権者の費用負担】「履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする」こと(民法第413条第2項)。
- 【債権者の責任】「当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす」こと(民法第413条の2第1項)。
ここでいう「自己の財産に対するのと同一の注意義務」とは、善管注意義務とは異なる注意義務であり、その定義は以下のとおりです。
【意味・定義】自己の財産に対するのと同一の注意義務とは?
自己の財産に対するのと同一の注意義務とは、行為者の注意能力に応じて要求される、行為者の通常の注意を払う義務をいう。
善管注意義務が「行為者の階層、地位、職業に応じて」要求されるのに対し、自己の財産に対するのと同一の注意義務は、あくまでその「行為者の注意能力に応じて」要求されるため、善管注意義務よりも注意義務は軽減されます。
つまり、受領遅滞が発生した場合は債務者=受託者の注意義務の程度が下がる、ということです。
このため、委託者の立場としては、業務委託契約では、受託者に対し、あくまで善管注意義務を求めるように規定することも検討するべきです。ただし、このような規定は、下請法や独占禁止法に抵触する可能性もあります。
なお、善管注意義務につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
受領遅滞の委託者の責任は?
改正民法第413条第の規定では、受領遅滞があった場合における債権者=委託者の具体的な「遅滞の責任」、特に「受領義務」は、明示されていません。
このため、具体的な責任がどのようなものであるのかは、学説や過去のでは、次のような考え方があります。
受領遅滞の責任の学説・判例
- 債務者による利息支払義務は免責される(大審院判決大正5年4月26日)
- 債権者の同時履行の抗弁権(民法第533条)は無くなる。
- 債務者は、債権者に対し、損害賠償の請求ができる。
- 債務者は、履行遅滞を理由に、契約解除ができる。
なお、学説によっては、3.と4.については、認めない立場もあります(判例同旨。最高裁判決昭和40年12月3日)。
もっとも、履行遅滞以外の理由、特に(「債権者」=委託者の側の)債務不履行があった場合は、これを理由に損害賠償請求や契約解除はできます。
例えば、製造請負契約において、委託者による受領遅滞があった場合、受託者としては、委託者による支払いがないこと=債務不履行を理由に、損害賠償請求や契約解除ができます。
ポイント
- 受領遅滞とは、次の受領拒否と受領不能の総称をいう。
- 受領拒否とは、委託者が受託者からの納入・業務実施の受領を拒むことをいう。
- 受領不能とは、委託者が受託者からの納入・業務実施の受領ができないことをいう。
- 受領遅滞の要件は、1.受領行為を要する債務であること、2.債務の本旨に従った履行の提供があること、3.履行遅滞が債権者の責任によるものであること―の3点。
- 受領遅滞の効果は、1.債務者による自己の財産に対するのと同一の注意義務、2.債権者の費用負担、3.債権者の責任―の3点。
- 受領遅滞があった場合の債権者=委託者の具体的な「遅滞の責任」は、学説・判例があるものの、法的には明記されていない。
業務委託契約では受領遅滞について規定する
受託者の側にとって特に重要な規定
このように、受領遅滞があった場合の委託者の「遅滞の責任」については、一部は改正民法により明文化されました。
ただ、すでに触れたとおり、(あくまで受領遅滞を理由とした)損害賠償責任や契約解除について否定する判例もあります。
このため、受託者にとっては、業務委託契約では、契約にもとづく権利として、「遅滞の責任」特に損害賠償責任や契約解除について明文化する必要があります。
特に、受託者の立場としては、委託者による履行遅滞があった場合の権利を確保しておくという点で、「履行遅滞」の条項は、非常に重要な条項です。
履行遅滞の条項に規定するべき内容
そこで、受託者としては、以下のような内容について、業務委託契約に履行遅滞の条項に規定します。
受託者が履行遅滞の条項で規定するべき内容
- 受領遅滞があった場合、委託者の同時履行の抗弁権が無くなり、受領がなくても受託者に報酬・料金・委託料の支払義務が発生するようにする。
- 受領遅滞そのものにもとづく、損害賠償・遅延損害金の請求ができるようにする。
- 受領遅滞があった場合における、違約金・損害賠償額の予定を設定する。
- 受領遅滞そのものにもとづく、契約解除ができるようにする。
- 受領遅滞により契約を解除した場合、物品・製品等を第三者に売却できるようにする。
ただ、これらの内容をすべて盛り込むのは、委託者にとっては、非常に厳しい内容と受け止められる可能性が高いです。
このため、当事者の関係性や、契約交渉における地位の優劣などを考慮のうえ、内容を調整してください。
ポイント
- 法的な定義がない「遅滞の責任」を明確化するため、業務委託契約で受領遅滞について規定する。
- 特に受託者の立場では、業務委託契約で、履行遅滞があった場合に備えた内容を規定しておくことが重要。
- 受領遅滞に備えた条項は数多くあるが、すべてを規定すると、契約交渉の際に揉める可能性も。
業務委託契約での受領拒否は下請法違反
委託者による受領拒否は下請法第4条第1項第1号違反
下請法が適用される業務委託契約の場合、受領拒否は、次のとおり、下請法第4条第1項第1号違反となります。
下請法第4条(親事業者の遵守事項)
1 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
(1)下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと。
(以下省略)
下請法が適用される業務委託契約のパターンにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
また、下請法そのものにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
【意味・定義】下請法における受領とは?
下請法における「給付の受領」の定義は、次のとおりです。
ア 「給付の受領」とは,物品の製造又は修理委託においては,給付の内容について検査をするかどうかを問わず,親事業者が下請事業者の給付の目的物を受け取り,自己の占有下に置くことである。
引用元: 下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準第4 1(1)ア
また、特に製造請負契約において、物品・製品等の引渡しの前に、受託者の工場等で委託者による検査がある場合は、その検査の開始の時点で「給付の受領」があったものとみなされます。
● 受領日の考え方
親事業者の検査員が下請事業者の工場へ出張し検査を行うような場合には,検査員が出張して検査を開始すれば受領となる。
引用元: 下請取引適正化推進講習会テキストp.44
なお、システム等開発業務委託契約における「給付の定義」は、次のとおりです。
イ 情報成果物の作成委託における「給付の受領」とは,情報成果物を記録した媒体がある場合には,給付の目的物として作成された情報成果物を記録した媒体を自己の占有下に置くことであり,また,情報成果物を記録した媒体がない場合には,当該情報成果物を自己の支配下に置くことであり,例えば,当該情報成果物が親事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されることである。
引用元: 下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準第4 1(1)イ
【意味・定義】下請法における受領拒否とは?
下請法では、「受領を拒む」の定義は、次のとおりです。
ウ 「受領を拒む」とは,下請事業者の給付の全部又は一部を納期に受け取らないことであり,納期を延期すること又は発注を取り消すことにより発注時に定められた納期に下請事業者の給付の全部又は一部を受け取らない場合も原則として受領を拒むことに含まれる。
引用元: 下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準第4 1(1)ウ
また、次の行為も受領拒否に該当します。
● 「受領を拒む」
「受領を拒む」とは,下請事業者の給付の全部又は一部を納期に受け取らないことであり,以下の行為も原則として含まれる。
(ア)発注を取り消すこと(契約の解除)により,下請事業者の給付の全部又は一部を発注時に定められた納期に受け取らないこと
(イ)納期を延期することにより,下請事業者の給付の全部又は一部を発注時に定められた納期に受け取らないこと
引用元: 下請取引適正化推進講習会テキストp.40
「下請事業者の責めに帰すべき理由」とは?
なお、例外として、下請法で禁止されていない適法な「受領拒否」には、次のとおり、「下請事業者の責めに帰すべき理由」が必要です。
● 下請事業者の責めに帰すべき理由
「下請事業者の責に帰すべき理由」があるとして,下請事業者の給付の受領を拒むことができるのは,以下の(ア),(イ)の場合に限られる。
(ア)下請事業者の給付の内容が3条書面に明記された委託内容と異なる場合又は下請事業者の給付に瑕疵等がある場合
※ただし,以下のような場合は,委託内容と異なること又は瑕疵等があることを理由として受領を拒むことは認められない。
① 3条書面に委託内容が明確に記載されていなかったり,検査基準が明確でなかったりしたために,下請事業者の給付の内容が委託内容と異なることが明らかでない場合
② 発注後に,検査基準を恣意的に厳しくすることにより,委託内容と異なる又は瑕疵等があるとして,従来の検査基準で合格とされたものを不合格とする場合
③ 取引の過程において,委託内容について下請事業者が提案し,確認を求めたところ,親事業者が了承したので,下請事業者がその内容に基づき製造等を行ったにもかかわらず,給付内容が委託内容と異なるとする場合
(イ)下請事業者の給付が,3条書面に明記された納期までに行われなかったため,そのものが不要になった場合
※ただし,以下のような場合は,納期遅れを理由として受領を拒むことは認められない。
① 3条書面に納期が明記されておらず納期遅れであることが明らかでない場合
② 親事業者が原材料を支給する場合において,支給が発注時に取り決めた引渡し日より遅れた場合
③ 無理な納期を一方的に決定している場合
引用元: 下請取引適正化推進講習会テキストp.40
ポイント
- 下請法が適用される業務委託契約では、受領拒否は下請法違反。
- 「給付の受領」とは、下請事業者が納入したものを検査の有無にかかわらず受け取るという行為のこと。
- 指定した納期に下請事業者が納入する給付の目的物の受取を拒んだときは受領拒否となる。
- 「下請事業者の責に帰すべき理由」は、(ア)下請事業者の給付の内容が3条書面に明記された委託内容と異なる場合又は下請事業者の給付に瑕疵等がある場合、(イ)下請事業者の給付が,3条書面に明記された納期までに行われなかったため,そのものが不要になった場合―の2点だけ。
- ただし、「下請事業者の責に帰すべき理由」には、例外が多い。
業務委託契約での受領拒否は独占禁止法違反
委託者による受領拒否は不公正な取引方法(優越的地位の濫用)
また、仮に下請法が適用されない業務委託契約であっても、受領拒否は、独占禁止法違反となる可能性もあります。
独占禁止法につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
独占禁止法では、受領拒否は、不公正な取引方法のうちの、優越的地位の濫用に該当する行為類型のひとつです。
この点について、公正取引委員会では、次のとおり規定しています。
(1) 受領拒否
ア 取引上の地位が相手方に優越している事業者が,取引の相手方から商品を購入する契約をした後において,正当な理由がないのに,当該商品の全部又は一部の受領を拒む場合(注16)であって,当該取引の相手方が,今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には,正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり,優越的地位の濫用として問題となる(注17)。
引用元:優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方p.15
なお、優越的地位の濫用につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
【意味・定義】受領を拒むとは?
独占禁止法における「受領を拒む」とは、次のとおりです。
「受領を拒む」とは,商品を納期に受け取らないことである。納期を一方的に延期すること又は発注を一方的に取り消すことにより納期に商品の全部又は一部を受け取らない場合も,これに含まれる。
引用元:優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方p.15
委託者として注意するべき点は、いわゆる一般的な受領の拒否だけではなく、「納期を一方的に延期すること又は発注を一方的に取り消すことにより納期に商品の全部又は一部を受け取らない場合」も「受領を拒む」ことになる、という点です。
優越的地位の濫用にならない受領拒否とは?
他方で、次の3つの場合については、優越的地位の濫用に該当しない受領拒否になります。
優越的地位の濫用とならない受領拒否
- 当該取引の相手方から購入した商品に瑕疵がある場合,注文した商品と異なる商品が納入された場合,納期に間に合わなかったために販売目的が達成できなかった場合等,当該取引の相手方側の責めに帰すべき事由がある場合,損失を負担する場合
- 商品の購入に当たって当該取引の相手方との合意により受領しない場合の条件を定め,その条件に従って受領しない場合
- あらかじめ当該取引の相手方の同意を得て,かつ,商品の受領を拒むことによって当該取引の相手方に通常生ずべき損失を負担する場合
参照:優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方p.15
なお、2点目については、同ガイドラインにより、「当該商品について,正常な商慣習の範囲内で受領を拒む条件を定める場合に限る」とされています。
また、3点目の「同意を得て」については、同ガイドラインにより、「了承という意思表示を得ることであって,取引の相手方が納得して同意しているという趣旨である」とされています。
さらに、3点目の「通常生ずべき損失」は、次のとおりです。
【意味・定義】通常生ずべき損失とは?
「通常生ずべき損失」とは、受領拒否により発生する相当因果関係の範囲内の損失をいう。例えば、次の3つが挙げられる。
- 商品の市況の下落、時間の経過による商品の使用期限の短縮に伴う価値の減少等に相当する費用
- 物流に要する費用
- 商品の廃棄処分費用
参照:優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方p.16
ポイント
- 下請法が適用されない業務委託契約でも、受領拒否は独占禁止法違反となる可能性がある。
- 単に商品を納期に受け取らないだけでなく、納期の一方的延期や発注の一方的取消しによる受領拒否も、受領拒否に該当する。
- 例外として、優越的地位の濫用に該当しない受領拒否もある。
受領遅滞(受領拒否・受領不能)に関するよくある質問
- 受領遅滞とは何ですか?
- 受領遅滞とは、次の受領拒否と受領不能の総称のことです。
- 受領拒否とは、委託者が受託者からの納入・業務実施の受領を拒むことをいう。
- 受領不能とは、委託者が受託者からの納入・業務実施の受領ができないことをいう。
- 受領遅滞について、特約では何を規定するべきですか?
- 特に業務委託契約における受託者の場合、受領遅滞に関しては、特約で次の内容を規定するべきです。
- 受領遅滞があった場合、委託者の同時履行の抗弁権が無くなり、受領がなくても受託者に報酬・料金・委託料の支払義務が発生するようにする。
- 受領遅滞そのものにもとづく、損害賠償・遅延損害金の請求ができるようにする。
- 受領遅滞があった場合における、違約金・損害賠償額の予定を設定する。
- 受領遅滞そのものにもとづく、契約解除ができるようにする。
- 受領遅滞により契約を解除した場合、物品・製品等を第三者に売却できるようにする。