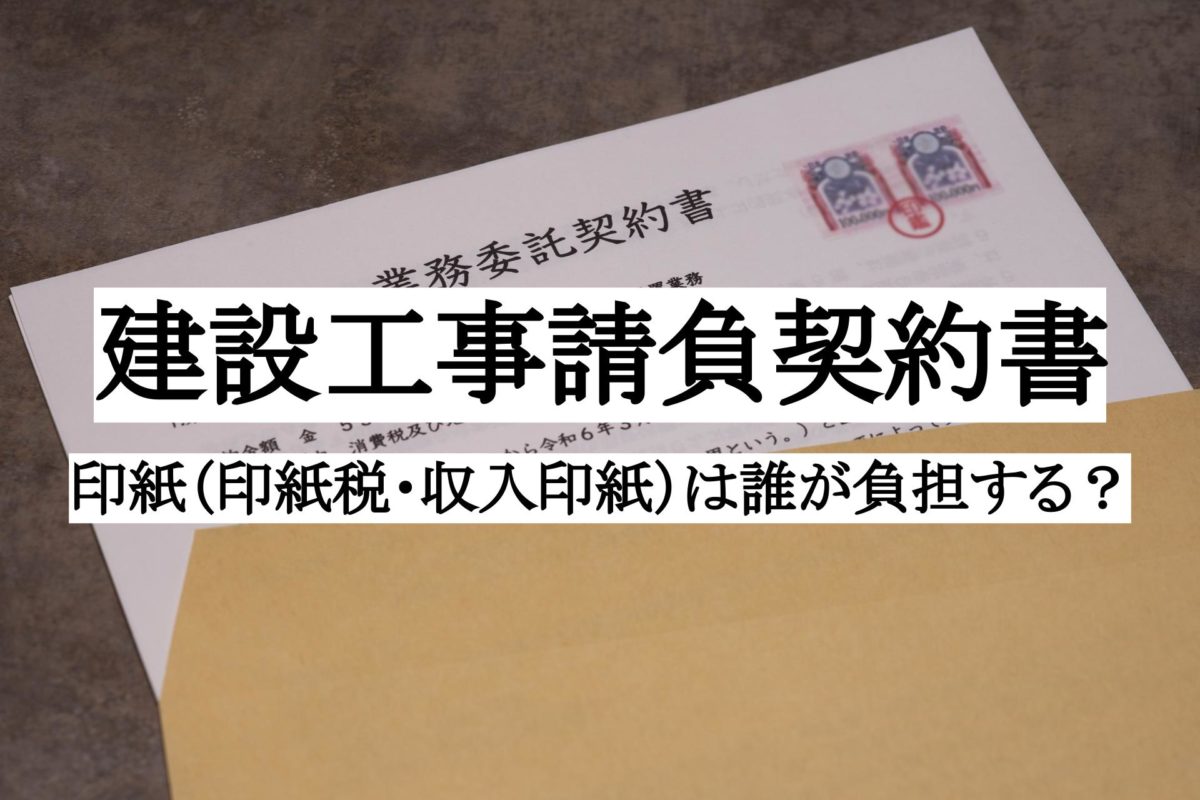- 警備業務委託契約書の印紙税はいくらでしょうか?また、そもそも印紙税を貼る必要があるのでしょうか?
- 警備業務委託契約書は、契約形態が請負契約なのか準委任契約なのかにより、印紙税が変わってきます。
請負契約の場合は、報酬の記載があるものは2号文書(印紙税は報酬の金額により算出)、報酬の記載がないものは契約期間や更新の規定によっては7号文書(印紙税は4,000円)となります。
準委任契約の場合は、不課税文書(印紙税は0円)となります。
このページでは、主に警備業者向けに、弊所によく寄せられるご質問である、警備業務委託契約書に貼る収入印紙と印紙税の金額について、簡単にわかりやすく解説します。
警備業務委託契約書は、契約形態によって、請負契約の場合は2号文書(印紙税の金額は警備料金による)または7号文書(印紙税は4,000円)、準委任契約の場合は不課税文書(印紙税は0円)のいずれかに該当します。
ただ、警備業界の方々の中には、「そもそも警備に関する契約って何の契約なの?」と思われる方も多いと思います。
それもそのはずで、警備に関する契約は契約形態は、法律で定義づけられておらず、判例でも明確になっていません。
だからこそ、請負契約なのか準委任契約なのか、他の契約なのかが判然とせず、どの文書に該当するのか不明であることが多いのです。
このページでは、こうした警備に関する契約書の印紙税や収入印紙について、開業20年・400社以上の取引実績がある管理人が、わかりやすく解説していきます。
このページをご覧いただくことで、以下の内容を理解できます。
このページでわかること
- 警備に関する契約書の印紙税の金額。
- 警備に関する契約書が不課税文書となる条件。
- 警備に関する契約の契約形態の違い。
- 契約締結前交付書面・契約締結時交付書面が課税文書になるかどうか。
なお、警備業務委託契約書・警備契約書そのものの解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
警備業務委託契約書は2号文書(報酬による)・7号文書(4,000円)・不課税文書(0円)のいずれか
契約書が「課税物件」に該当すると収入印紙を貼る必要がある
警備業務委託契約書に収入印紙を貼る必要があるかどうかは、契約内容次第です。また、印紙税の金額も、契約内容次第です。
契約書が印紙税法上の課税文書に該当するかどうかは、原則として、その契約書が印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書に該当するかどうかによって判断されます(ただし、例外あり。印紙税法基本通達第2条)。
印紙税法第2条(課税物件)
別表第1の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
引用元:印紙税法 | e-Gov法令検索
このため、警備業務委託契約書が課税物件表に掲げられている文書に該当する場合、収入印紙を貼る必要があります。
なお、「課税物件」に該当しない警備業務委託契約書には、収入印紙を貼る必要はありません。
警備業務委託契約書が課税文書かどうかは請負契約か準委任契約かで決定する
一般的な警備業務委託契約は、請負契約か準委任契約のいずれかに該当します。
請負契約に該当する場合は2号文書または7号文書、準委任契約に該当する場合は不課税文書となります。
また、一般的な警備業務委託契約書では、無体財産権(≒知的財産権)の譲渡がありませんので、1号文書に該当することはありません。
印紙税の金額は、契約形態が請負契約の場合、スポットの警備業務委託契約書などの2号文書の場合は報酬に応じて計算され、継続的な警備業務委託契約書などの7号文書の場合は4,000円となります。
契約形態が準委任契約の場合は不課税文書ですので、印紙税の金額は、当然0円となります。
以下、それぞれ詳しく見ていきましょう。
2号文書に該当する警備業務委託契約書とは?
2号文書とは?
警備業務委託契約書が2号文書に該当する条件は、以下の3つのすべてとなります。
警備業務委託契約書が2号文書となる3条件
- 契約形態が請負契約であること
- 一回的契約(いわゆるスポット契約、単発契約)であること(継続的な契約はものは後述の7号文書となる可能性があります)
- 報酬・警備料金の記載があること(報酬の記載がないものは後述の7号文書となる可能性があります)
2号文書とは、「請負に関する契約書」であって、「職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むもの」が該当します。
【意味・定義】2号文書(印紙税法)とは?
印紙税法における2号文書とは、請負に関する契約書であって、「職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むもの」をいう。
「請負に関する契約書」とあるとおり、警備業務委託契約書の契約形態が請負契約の場合は、2号文書となります。
例外として、報酬・警備料金の記載がなく、かつ、契約期間が3ヶ月を超えるか、または3ヶ月未満で更新に関する定めがあるものは、後述の7号文書に該当する可能性があります。
なお、請負契約の解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
2号文書の印紙税の金額は?
2号文書の印紙税の金額は、報酬・警備料金に応じて、次のとおりです。
| 2号文書の印紙税の金額(不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書を除く) | |
|---|---|
| 記載された契約金額 | 印紙税額(1通又は1冊につき) |
| 1万円未満(※) | 非課税 ※ 第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。 |
| 100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 1千円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
ポイント
- 請負契約であり、スポット契約・単発契約であり、報酬・警備料金の記載がある場合は、警備業務委託契約書は2号文書となる。
- 2号文書の印紙税の金額は、報酬・警備料金の金額に応じて計算される。
7号文書に該当する警備業務委託契約書とは?
7号文書とは?
警備業務委託契約書が7号文書に該当する条件は、以下の5つのすべてとなります。
警備業務委託契約書が7号文書となる5条件
- 委託者が「営業者」であること。
- 契約形態が請負契約であること。
- 継続的取引の基本となる契約書、いわゆる取引基本契約書であること。
- 「契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないもの」でないこと。
- 報酬=警備料金の記載がないこと(報酬の記載があるものは前述の2号文書となる可能性があります)。
7号文書とは、「継続的取引の基本となる契約書」、いわゆる取引基本契約書であって、売買契約や請負契約等の印紙税法施行規則第26条に該当するもののことです。
【意味・定義】7号文書(印紙税法)とは?
7号文書とは、継続的取引の基本となる契約書であって、「特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもの」のうち、売買契約や請負契約等の印紙税法施行規則第26条で定めるものをいう。
「請負に関する二以上の取引を継続して行うため作成される契約書」とあるとおり、警備業務委託契約書の契約形態が請負契約の場合において、継続的取引の基本となる取引条件が規定されているものは、7号文書となります。
7号文書に該当しない警備業務委託基本契約書は?
契約期間が3か月以内かつ更新なしの場合は2号文書
なお、「契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないもの」は7号文書からは除外されています。
このため、契約期間が3か月以内で更新条項が無い警備業務委託基本契約書(請負契約型)は、基本契約書であっても、7号文書には該当しません。
この場合は、2号文書として扱われます。
報酬・警備料金の金額の記載がある場合は2号文書
具体的に確定した報酬・警備料金の金額が記載された警備業務委託基本契約書(請負契約型)は、7号文書ではなく2号文書となります。
一般的な警備業務委託基本契約書では、金額の計算方法等は規定することはあっても、具体的な確定した報酬・警備料金が記載されることはありません。
このため、警備業務委託基本契約書だけでは、7号文書として扱われます。
しかし、警備業務委託基本契約書に、初回の個別契約にかかる注文書・注文請書や個別契約書を基本契約書と一緒に綴じ込むことで、具体的に確定した金額が記載されることとなります。
これによって、その契約書は2号文書として扱われ、報酬・警備料金の金額によっては、4,000円よりも節税できることもあります。
委託者が営業者でない場合は2号文書
警備業務の委託者が「営業者」(印紙税法施行令第26条第1号)に該当しない場合、警備業務委託基本契約書(請負契約型)は、7号文書ではなく2号文書となります。
いわゆる取引基本契約書が7号文書に該当する条件のひとつに、契約当事者の双方が営業者であることがあります。
契約当事者の一方でもこの営業者に該当しない場合は、取引基本契約書は、7号文書ではなく2号文書となります。
このため、例えば委託者が公益法人や医療法人等である場合は、警備業務委託基本契約書(請負契約型)は、7号文書ではなく2号文書となります。
この他、7号文書の営業者の定義や例外につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
7号文書の印紙税の金額は?
7号文書の印紙税の金額は、次のとおり4,000円とされています。
| 7号文書の印紙税の金額 | ||
|---|---|---|
| 号 | 文書の種類 | 印紙税額(1通または1冊につき) |
| 7 | 継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。) | 4千円 |
7号文書に該当するかどうかの判断は?
7号文書に該当するかどうかにつきましては、以下のフローチャートでかんたんに判断できます。
ポイント
- 請負契約であり、取引基本契約であり、3ヶ月を超える契約期間であり、金額の記載がない場合は、警備業務委託契約書は7号文書となる。
- 契約期間が3か月以内かつ更新なしの場合は2号文書扱い。
- 報酬・警備料金の金額の記載がある場合は2号文書扱い。
- 7号文書の印紙税の金額は、金4,000円。
不課税文書に該当する警備業務委託契約書とは?
準委任契約に関する契約書は原則として不課税文書
警備業務委託契約の契約形態が準委任契約である場合、その契約書は、不課税文書となります。
すでに述べたとおり、印紙税の課税対象となる文書は、印紙税法第2条と印紙税法別表第1により、具体的に指定されています。
しかしながら、印紙税法別表第1には、「準委任契約書」の記載がありません。
このため、準委任契約型の警備業務委託契約書の印紙税は0円で、収入印紙を貼る必要もありません。
準委任契約型の警備業務委託契約書は7号文書にも該当しない
7号文書に該当するかどうかの基準を規定した、印紙税法施行令第26条各号のいずれにも、警備に関する契約が規定されていません。
このため、準委任契約型の警備業務委託契約書は7号文書にも該当しませんので、印紙税が課税されず、収入印紙も貼る必要がありません。
ポイント
- 印紙税法上の「課税物件」としては、「委任契約書」や「準委任契約書」のような記載はない。
- (準)委任契約型の警備業務委託契約書には印紙税は課税されず、収入印紙を貼る必要もない。
補足1:警備に関する契約形態は請負契約?準委任契約?無名契約?
現行法では警備に関する契約の契約形態は規定がない
警備契約、警備基本契約、警備業務委託契約、警備業委託基本契約、警備保障契約書、ホームセキュリティ契約書など、警備業務に関する契約が、民法上のどの契約に該当するのかは、民法や警備業法では規定がありません。
この点については、以下の3つの考え方があります。
警備に関する契約の契約形態の考え方
- 請負契約であるとの考え方
- 準委任契約であるとの考え方
- 請負契約や準委任契約などの民法上の典型契約に該当しない非典型契約・無名契約であるとの考え方(名古屋地裁昭和50年4月22日判決)
いずれにしても、特に法律で規定がない以上、契約自由の原則により、契約形態を自由に決めることができます。
【意味・定義】契約自由の原則とは?
契約自由の原則とは、契約当事者は、その合意により、契約について自由に決定することができる民法上の原則をいう。
一般的な警備業務委託契約書は請負契約か準委任契約
すでに述べたとおり、一般的な警備業務委託契約書の契約形態は、請負契約か準委任契約となります。
通常、委託者にとっては「仕事の完成」=結果が保証されている請負契約の方が有利であり、受託者である警備業者にとっては必ずしも結果の保証が必要でない準委任契約の方が有利となります。
なお、請負契約と(準)委任契約については、次の14の違いがあります。
| 請負契約と(準)委任契約の違い | ||
|---|---|---|
| 請負契約 | (準)委任契約 | |
| 業務内容 | 仕事の完成 | 法律行為・法律行為以外の事務などの一定の作業・行為の実施 |
| 報酬請求の根拠 | 仕事の完成 | 履行割合型=法律行為・法律行為以外の事務の実施、成果完成型=成果の完成 |
| 受託者の業務の責任 | 仕事の結果に対する責任 (完成義務・契約不適合責任) | 仕事の過程に対する責任 (善管注意義務) |
| 報告義務 | なし | あり |
| 業務の実施による成果物 | 原則として発生する(発生しない場合もある) | 原則として発生しない(発生する場合もある) |
| 業務の実施に要する費用負担 | 受託者の負担 | 委託者の負担 |
| 受託者による再委託 | できる | できない |
| 再委託先の責任 | 受託者が負う | 原則として受託者が直接負う (一部例外として再委託先が直接負う) |
| 委託者の契約解除権 | 仕事が完成するまでは、いつでも損害を賠償して契約解除ができる | いつでも契約解除ができる。ただし、次のいずれかの場合は、損害賠償責任が発生する
|
| 受託者の契約解除権 | 委託者が破産手続開始の決定を受けたときは、契約解除ができる | いつでも契約解除ができる。ただし、委託者の不利な時期に契約解除をしたときは損害賠償責任が発生する |
| 印紙(印紙税・収入印紙) | 必要(1号文書、2号文書、7号文書に該当する可能性あり) | 原則として不要(ただし、1号文書、7号文書に該当する可能性あり) |
| 下請法違反のリスク | 高い | 高い |
| 労働者派遣法違反=偽装請負のリスク | 低い(ただし常駐型は高い) | 高い(常駐型は特に高い) |
| 労働法違反のリスク | 低い | 高い |
この他、請負契約と(準)委任契約の違いの解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
警備業務委託契約書に契約形態が規定されていない場合の印紙税は?
国税庁・管轄税務署・担当官によって判断が異なる
では、警備業務委託契約書に契約形態が明確に規定されていない場合、どの課税文書に該当するのか、あるいは不課税文書に該当するのかでしょうか?
この場合は、国税庁、管轄の税務署、担当官によって、判断が異なります。
このため、実際に照会をかけるか、税務調査の際に判断をされないと、判然としません。
ただし、契約条項として契約形態の規定がなくても、契約書のタイトルが「警備請負契約書」となっている場合は、請負契約=2号文書または7号文書と判断される可能性が高くなります。
警備請負契約書に契約形態の規定がない場合は直ちに契約書を見直すべき
なお、警備請負契約書に契約形態の規定がない場合、警備上の事故が発生したときに問題となる可能性があります。
すでに述べたとおり、警備に関する契約は請負契約か準委任契約であることが多いですが、そのどちらかによって、責任の程度が大きく異なります。
請負契約の場合は、「仕事の完成」を目的としているため、「仕事」の定義によっては、警備業者にとっては非常に大きな責任となる可能性があります。
【意味・定義】仕事(請負契約)とは?
請負契約における仕事とは、請負人が労務をすることによって何らかの結果を生じさせることをいう。
これに対し、準委任契約の場合は、善管注意義務が課されているため、業務の実施そのものには責任が発生しますが、その結果については、必ずしも責任が発生するとは限りません。
【意味・定義】善管注意義務とは?
善管注意義務とは、行為者の階層、地位、職業に応じて、社会通念上、客観的・一般的に要求される注意を払う義務をいう。
この他、契約形態に関する契約条項の解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 現行法では、警備に関する契約の契約形態は、明確な規定がない。
- 一般的な警備業務委託契約書は請負契約か準委任契約のどちらか。
- 警備業務委託契約書に契約形態が規定されていない場合の印紙税は、国税庁・管轄税務署・担当官によって判断が異なる。
- 警備請負契約書に契約形態の規定がない場合は、直ちに契約書を見直すべき。
補足2:どの警備の契約であっても契約形態の考え方は同じ
警備業務は、警備業法により、主に次のようなものがあります。
警備業務一覧
- 施設警備
- 空港保安警備(以上、一号警備)
- 雑踏警備
- 交通誘導警備(以上、二号警備)
- 貴重品運搬警備
- 核燃料物質等危険物運搬警備(以上、三号警備)
- 身辺警護警備(以上、四号警備)
- 機械警備
これらのいずれの警備であっても、現行法では特に契約形態が規定されれていません。
このため、すでに述べたとおり、契約自由の原則により、契約形態を自由に決めることができます。
ただし、三号警備に関しては、運送請負契約に類似した性質があります。
このため、警備業務委託契約書において特に契約形態を規定していない場合は、請負契約と解釈される可能性があります。
補足3:契約締結前交付書面・契約締結時交付書面の印紙税は?
警備業法第19条の契約締結前交付書面・契約締結時交付書面とは?
なお、警備業者は、警備業法第19条により、委託者に対し、いわゆる「契約締結前交付書面」と「契約締結時交付書面」を交付しなければなりません。
この契約締結前交付書面と契約締結時交付書面が課税文書に該当するかどうかは、これらが印紙税法上の「契約書」に該当するかどうかによります。
契約締結前交付書面は不課税文書
この点につき、国税庁の見解によると、契約書の意義は以下のとおりです。
…契約書とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含みます。以下同じ。)の成立もしくは更改または契約の内容の変更もしくは補充の事実(以下「契約の成立等」といいます。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書または契約の当事者の全部もしくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解または商慣習に基づき契約の成立等を証することになっているものも含まれます。
したがって、通常、契約の申込みの事実を証明する目的で作成される申込書、注文書、依頼書などと表示された文書であっても、実質的にみて、その文書によって契約の成立等が証明されるものは、契約書に該当することになります。引用元: No.7117 契約書の意義|国税庁
契約締結前交付書面は、一般的な見積書と同様に、「契約の成立等を証する」書面ではありませんので、不課税文書であると考えられます。
契約締結時交付書面は課税文書となる可能性が高い
他方で、契約締結時交付書面は、「警備業務を行う契約を締結したとき」に遅滞なく交付する書面です。
契約締結時交付書面は、警備業法施行規則第33条第1号イの「警備業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名」を記載する必要はありません。
しかしながら、一般的な契約締結時交付書面では、これらの項目は記載されています。
仮に記載がないとしても、「契約の当事者の全部もしくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解または商慣習に基づき契約の成立等を証することになっているもの」に該当する可能性が高いです。
このため、準委任契約である旨が明記されていなければ、契約締結時交付書面は課税文書に該当する可能性が高いです。
契約締結時交付書面を警備業務委託契約書に綴じ込むことで節税できる
課税文書はあくまで1部または1冊のみ
なお、契約締結時交付書面とは別に警備業務委託契約書を作成している場合、契約締結時交付書面を警備業務委託契約書に綴じ込むことで、1冊の文書とすることができます。
課税文書は、あくまで1部または1冊あたりに課税されます。
このため、契約締結時交付書面と警備業務委託契約書を1冊の文書とすることで、印紙税の2重払いを回避できます。
警備業務委託契約書があっても別途交付書面の作成が必要な場合も
なお、理論上は、警備業法第19条の内容を満たした警備業務委託契約書を2部作成し、委託者に交付していれば、契約締結時交付書面を交付したこととなります。
しかしながら、各都道府県公安委員会の警備業法の運用によっては、警備業務委託契約書とは別に契約締結前交付書面・契約締結時交付書面の作成・交付を求めるケースもあります。
こうした場合は、実務上は、契約締結前交付書面と契約締結時交付書面を警備業務委託契約書に綴じ込むことで対応することができます。
ポイント
- 契約締結前交付書面は不課税文書。
- 契約締結時交付書面は、準委任契約である旨が明記されていなければ、課税文書となる可能性が高い。
- 契約締結時交付書面を警備業務委託契約書に綴じ込むことで印紙税の2重払いを回避でき、節税できる。
補足4:収入印紙への消印(≠割印)の押し方
なお、収入印紙に消印を押す場合、以下の図のように押します。
.jpg)
この他、収入印紙への消印(≠割印)の押し方の詳細な解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
印紙税の節税は電子契約サービスがおすすめ
印紙税の節税には、電子契約サービスの利用がおすすめです。
というのも、電子契約サービスは、他の方法に比べて、デメリットがほとんど無いからです。
印紙税を節税する方法は、さまざまあります。
具体的には、以下のものが考えられます。
印紙税を節税する方法
- コピーを作成する:原本を1部のみ作成し、一方の当事者のみが保有し、他方の当事者はコピーを保有する。
- 契約形態を変更する:節税のために準委任契約のような非課税の契約にする。
- 7号文書を2号文書・1号文書に変更する:取引基本契約に初回の注文書・注文請書や個別契約を綴じ込むことで7号文書から2号文書・1号文書に変える。
しかし、これらの方法には、以下のデメリットがあります。
印紙税の節税のデメリット
- コピーを作成する:契約書のコピーは、原本に比べて証拠能力が低い。
- 契約形態を変更する:節税のために契約形態を変えるのは本末転倒であり、節税の効果以上のデメリットが発生するリスクがある。
- 7号文書を2号文書・1号文書に変更する:7号文書よりも印紙税の金額が減ることはあるものの、結局2号文書・1号文書として課税される。
これに対し、電子契約サービスは、有料ではあるものの、その料金を上回る節税効果があり、上記のようなデメリットがありません。
電子契約サービスのメリット
- 電子契約サービスを利用した場合、双方に証拠として電子署名がなされた契約書のデータが残るため、コピーの契約書よりも証拠能力が高い。
- 電子契約サービスは印紙税が発生しないため、印紙税を考慮した契約形態にする必要がない。
- 電子契約サービスは印紙税が発生しないため、7号文書に2号文書や1号文書を同轍する必要はなく、そもそも契約書を製本する必要すらない。
このように、印紙税の節税には、電子契約サービスの利用が、最もおすすめです。
![]()
警備業務委託契約書の印紙税・収入印紙に関するよくある質問
- 警備業務委託契約書の印紙税はいくらでしょうか?
- 警備業務委託契約書は、契約形態が請負契約の場合は2号文書か7号文書に該当し、2号文書では印紙税の金額は報酬の金額に応じて計算され、7号文書では印紙税の金額は4,000円となります。
- 警備業務委託契約書には印紙税を貼る必要があるのでしょうか?
- 警備業務委託契約書の契約形態が請負契約の場合は、収入印紙を貼る必要があります。
なお、契約形態が準委任契約の場合は警備業務委託契約書は不課税文書となるため、収入印紙を貼る必要はありません。
- 警備業務委託契約には、どのような契約形態があるのでしょうか?
- 警備業務委託契約の契約形態は、主に請負契約、準委任契約、無名契約の3パターンがあります。
- 警備業務によって、契約形態や印紙税の考え方は変わってきますか?
- 警備業務によって、契約形態や印紙税の考え方は特に変わりません。
- 契約締結前交付書面は課税文書となりますか?
- 契約締結時交付書面は、一般的な見積書と同様に、「契約の成立等を証する」書面ではありませんので、不課税文書であると考えられます。
- 契約締結時交付書面は課税文書となりますか?
- 契約締結時交付書面は、「契約の当事者の全部もしくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解または商慣習に基づき契約の成立等を証することになっているもの」に該当し、準委任契約である旨が明記されていなければ、契約締結時交付書面は課税文書に該当する可能性が高いです。
警備業務委託契約書・契約締結前交付書面・契約締結時交付書面の作成依頼はすべておまかせください
弊所では、警備業務委託契約書等の警備に関する契約書、契約締結前交付書面、契約締結時交付書面をはじめ、さまざまな契約書の作成依頼を承っております。
お見積りは完全無料となっていますので、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
- 1 警備業務委託契約書は2号文書(報酬による)・7号文書(4,000円)・不課税文書(0円)のいずれか
- 2 2号文書に該当する警備業務委託契約書とは?
- 3 7号文書に該当する警備業務委託契約書とは?
- 4 不課税文書に該当する警備業務委託契約書とは?
- 5 補足1:警備に関する契約形態は請負契約?準委任契約?無名契約?
- 6 補足2:どの警備の契約であっても契約形態の考え方は同じ
- 7 補足3:契約締結前交付書面・契約締結時交付書面の印紙税は?
- 8 補足4:収入印紙への消印(≠割印)の押し方
- 9 印紙税の節税は電子契約サービスがおすすめ
- 10 警備業務委託契約書の印紙税・収入印紙に関するよくある質問
- 11 警備業務委託契約書・契約締結前交付書面・契約締結時交付書面の作成依頼はすべておまかせください