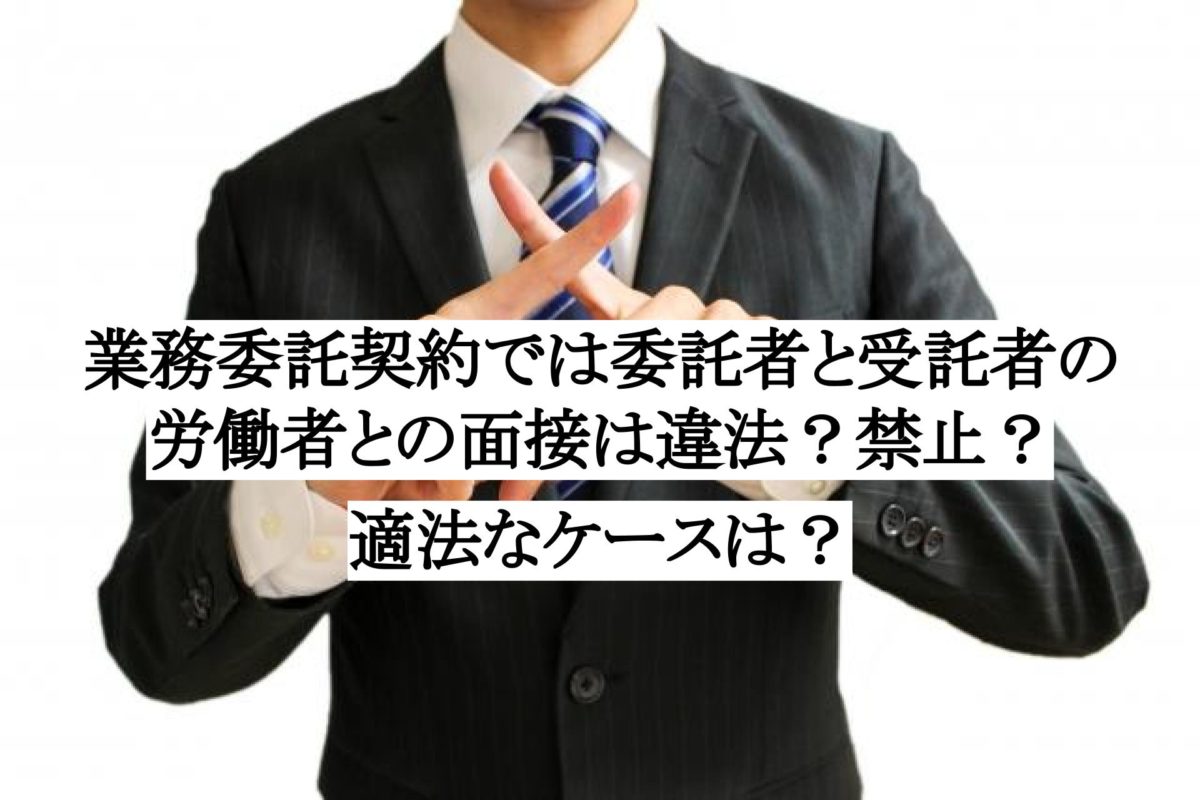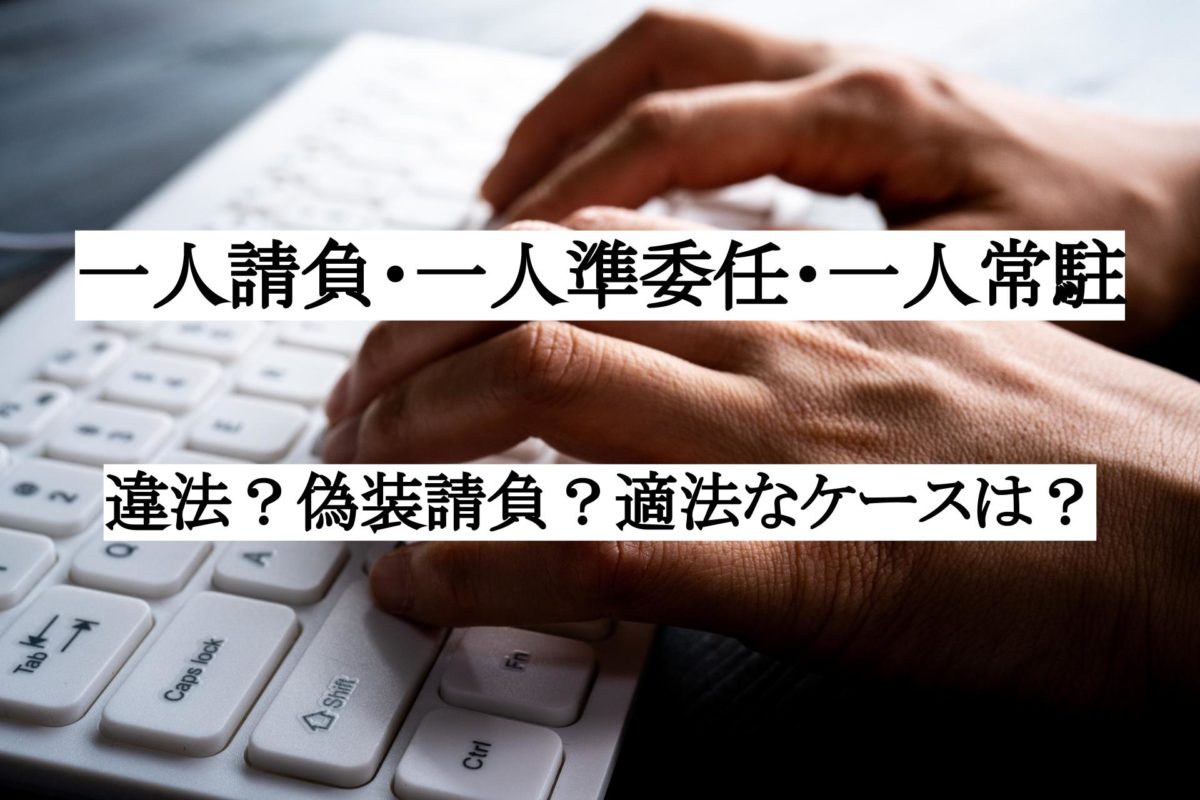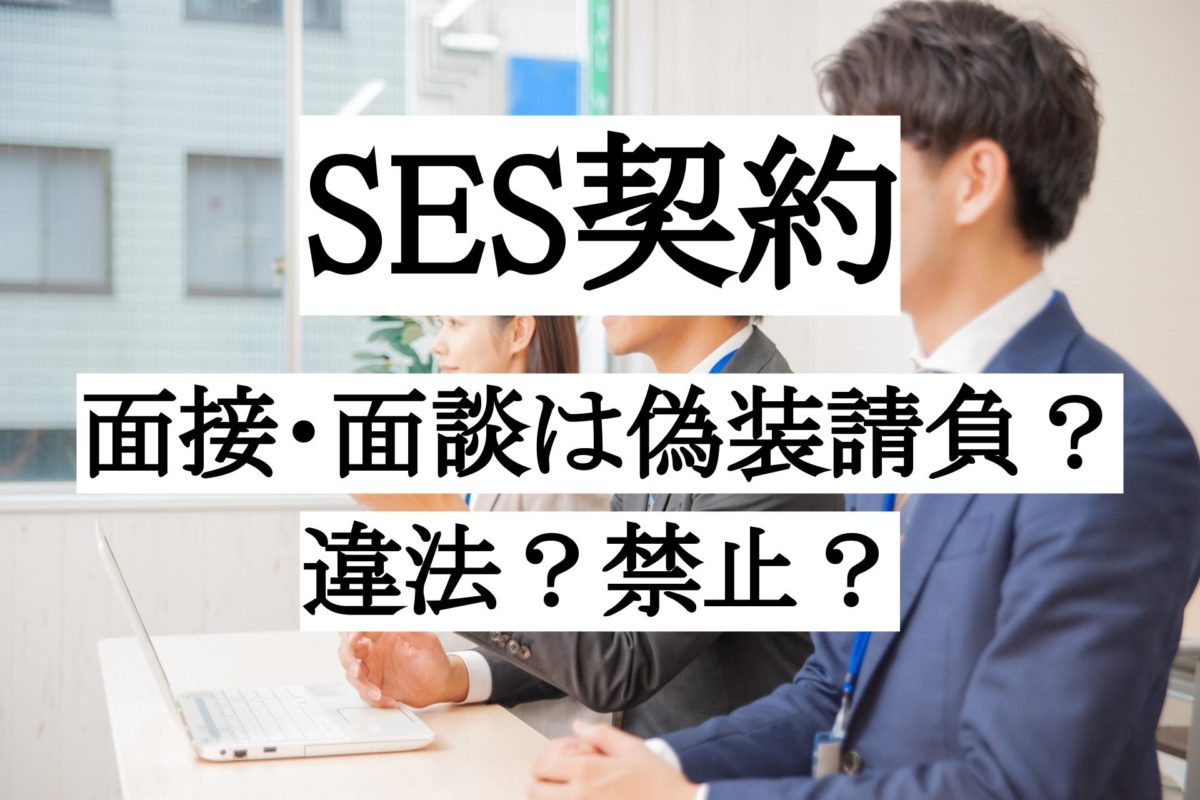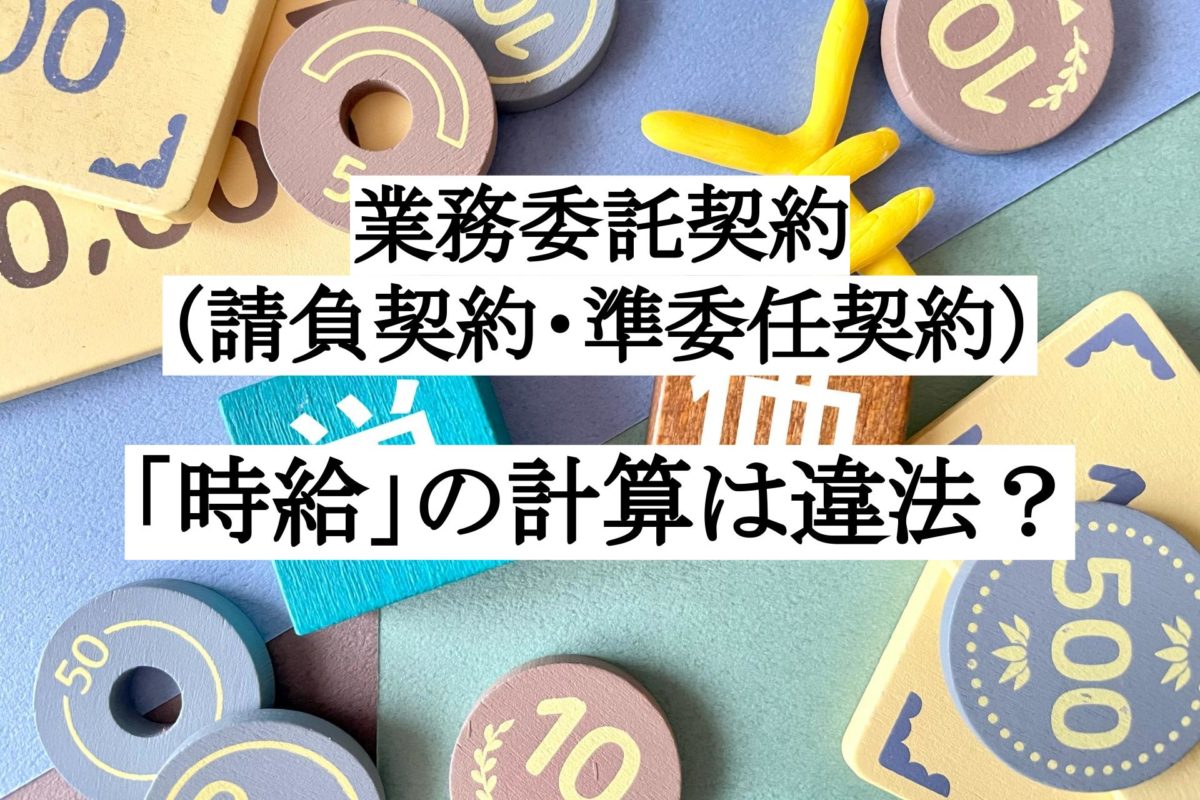- 一人で客先常駐をする契約は違法となるのでしょうか?
- 一人で取引先・客先に常駐する契約は、一人であることや客先常駐であること自体をもって直ちに違法となるわけではありません。ただし、一人であることや客先常駐であることによって、委託者から受託者の作業者に対し、直接指示・指揮命令がなされる状態となる場合は、偽装請負となり、労働者派遣法違反=違法となります。
このページでは、受託者の労働者が一人で客先常駐する場合に、違法=偽装請負・労働者派遣法違反に該当するかどうかと、その条件や基準について解説しています。
SES契約や建設工事請負契約など、客先や現場に常駐する契約では、受託者の作業者が1人で客先常駐をする場合があります。
このような一人での客先常駐は、「偽装請負であり労働者派遣法違反になる」と誤解されがちです。
しかし、実は、一人であることや客先常駐であるこtは、そのこと自体は偽装請負になるわけではなく、労働者派遣法違反にはなりません。
このページでは、客先常駐の業務委託契約の委託者・受託者の双方向けに、一人での客先常駐の業務委託契約が偽装請負・労働者派遣法違反になるかどうかの基準について、厚生労働省の公式の資料にもとづき、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。
このページでわかること
- 偽装請負・労働者派遣法違反に該当しない適法な一人での常駐常駐のしかた。
- 偽装請負・労働者派遣法違反に該当する一人での客先常駐の条件。
- 偽装請負・労働者派遣法違反に該当しない適法な一人での常駐常駐の条件。
- 一人での常駐常駐の業務委託契約書の作成のポイント。
一人での客先常駐の業務委託契約は偽装請負・労働者派遣法違反にはならない
結論:一人での客先常駐そのものは違法ではない
結論から言えば、一人での客先常駐の業務委託契約は、そのこと自体によって、直ちに違法となるわけではありません。
ただし、一人での客先常駐であることによって、受託者の作業者に対して、委託者が直接指示・指揮命令をした場合は違法となります。
具体的には、いわゆる「偽装請負」に該当し、労働者派遣法違反となります。
【意味・定義】偽装請負(労働者派遣法・労働者派遣契約)とは?
労働者派遣法・労働者派遣契約における偽装請負とは、実態は労働者派遣契約なのに、労働者派遣法等の法律の規制を免れる目的で、請負その他労働者派遣契約以外の名目で契約が締結され、労働者が派遣されている状態をいう。
逆に言えば、(非常に厳しいですが)条件さえ満たせは、一人での客先常駐であっても、適法な業務委託契約とすることは可能です。
作業員を一人とする契約は原則として違法にはならない
業務委託契約等において業務を実施する際に、受託者の作業員を一人となることは、契約自由の原則により、一般的には、それ自体は違法ではありません。
【意味・定義】契約自由の原則とは?
契約自由の原則とは、契約当事者は、その合意により、契約について自由に決定することができる民法上の原則をいう。
民法第521条(契約の締結及び内容の自由)
1 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
上記の民法第521条第2項にあるとおり、「法令の制限内」ではありますが、受託者の作業員が一人になることは、適法になります。
ただし、業務委託契約において、委託者が受託者の作業員を一人に限定したり、受託者の特定の作業員を指名した場合は、違法になります(後述)。
客先常駐の契約は原則として違法にならない
また、客先常駐についても、上記の契約自由の原則により、一般的には、それ自体は違法にはなりません。
ただし、客先常駐は、一人に限らず、複数人であったとしても、委託者が受託者の従業員に対し直接指示・指揮命令をした場合は、違法=偽装請負・労働者派遣法違反となる可能性があります。
特に、受託者の作業員が一人で客先常駐をする場合は、どうしても委託者からの指示・指揮命令がありがちですので、違法となる可能性が高くなる傾向があります。
ただし、一人での客先常駐が必ず違法になる、というわけではありません。
厚生労働省の資料によっても、一人での客先常駐であっても、違法にはならないケースが例示されています。
一人での客先常駐が違法・適法となる条件・基準とは?
では、一人での客先常駐が違法となる条件・基準や、適法となる条件・基準は、どのようなものでしょうか?
それぞれ、具体的な条件・基準は、次のとおりです。
違法=偽装請負・労働者派遣法違反となる一人での客先常駐の条件・基準
- 受託者の管理責任者が選任されていないこと。
- 常駐外で受託者の管理責任者が常駐外で選任されていても、管理業務ができていないこと。
- 受託者の作業者が管理責任者を兼任していること。
- 委託者が受託者の労働者の人数を「一人」に指定すること。
※上記は、いずれかひとつでも該当すると偽装請負・違法となります。
適法な一人での客先常駐の条件・基準
- 受託者の作業者以外に受託者の管理責任者が選任されていること。
- 受託者の管理責任者が常駐でなくても常に管理業務ができる状態であること。
- 受託者の作業者に対し、委託者が直接指示・指揮命令をしていないこと。
- 上記の内容を反映した業務委託契約書が作成されていること。
※上記はすべてを満たしている必要があります。
以下、それぞれについて、厚生労働省の資料にもとづき、詳しく解説していきます。
違法=偽装請負の判定基準=「37号告示」とは?
労働者派遣事業と「労働者派遣事業でない事業」の区分に関する基準
まず、偽装請負=労働者派遣法違反の判定基準を紹介します。
偽装請負=労働者派遣法違反は、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第 37 号)によって判断されます。
この判断基準を、「37号告示」といいます。
その第1条にも、以下のように規定されています。
37号告示第1条
1 この基準は、(途中省略)労働者派遣事業(途中省略)に該当するか否かの判断を的確に行う必要があることに鑑み、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的とする。
2 (以下省略)
【意味・定義】37号告示とは?
37号告示とは、労働者派遣事業と請負等の労働者派遣契約にもとづく事業との区分を明らかにすることを目的とした厚生労働省のガイドラインである「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」をいう。
このため、企業間取引において、37号告示は、厚生労働省に違法な労働者派遣事業=偽装請負と判断されないように対処する際の、最も重要な基準となります。
一人での客先常駐が偽装請負・労働者派遣法違反となるか、または適法になるかどうかについても、この37号告示によって判断することとなります。
一人での客先常駐については疑義応答集により判断する
また、37号告示については、厚生労働省から、次のとおり詳細な疑義応答集が公表されています。
37号告示に関する厚生労働省の疑義応答集
- 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37 号告示)に関する疑義応答集(以下、「疑義応答集第1集」とします)
- 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)(以下、「疑義応答集第2集」とします)
- 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37 号告示)に関する疑義応答集(第3集)(以下、「疑義応答集第3集」とします)
一人での客先常駐については、この疑義応答集の中で詳細な言及があります。
このため、主にこの疑義応答集の記載内容によって、一人での客先常駐が適法か、または違法かを判断することとなります。
ポイント
- 37号告示=労働者派遣事業と「労働者派遣事業でない事業」の区分に関する基準。
- 一人での客先常駐については、37号告示の疑義応答集に具体的な記載がある。
違法となる一人での客先常駐となる条件とは?
委託者が受託者の労働者に対し直接指示・指揮命令をする状態かどうかがポイント
偽装請負・労働者派遣法違反となる違法な一人での客先常駐の条件・基準は、以下のとおりです。
違法=偽装請負・労働者派遣法違反となる一人での客先常駐の条件・基準
- 受託者の管理責任者が選任されていないこと。
- 受託者の管理責任者が常駐外で選任されていても、管理業務ができていないこと。
- 受託者の作業者が管理責任者を兼任していること。
- 委託者が受託者の労働者の人数を「一人」に指定すること。
これらのいずれかに該当する場合は、偽装請負・労働者派遣法違反となります。
ポイントは、これらのいずれもが、結果的に、「委託者が受託者の労働者に対し直接指示・指揮命令をする状態」となってしまっていることにあります。
以下、それぞれ詳しく解説します。
【条件1】受託者の管理責任者が選任されていないこと
受託者の労働者は受託者が自ら管理しなければならない
一人での客先常駐の業務委託契約が偽装請負・労働者派遣法違反となる1つめの条件は、受託者の管理責任者が選任されていないことです。
37号告示第2条第1号では、以下のとおり、労働者の様々な事項に関する管理について、受託者「自ら行う」ことを求めています。
37号告示第二条
請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であつても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。
一 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。
イ 次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1)労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
(2)労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。
ロ 次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1)労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
(2)労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
ハ 次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1)労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
(2)労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。
管理責任者の不選任≒委託者による管理
受託者の労働者の管理は、実際には、企業である受託者によって選任された管理責任者がおこなうこととなります。
ところが、管理責任者を選任していなければ、労働者を管理をしていることにはなりません。
そうなると、一人かどうかに関係なく、委託者の事業所に常駐している受託者の労働者の管理は、委託者がしているとみなされやすくなります。
よって、受託者が管理責任者を専任していなければ、たとえ複数人であっても、偽装請負・労働者派遣法違反に該当します。
【条件2】受託者の管理責任者が常駐外で選任されていても、管理業務ができていないこと
受託者の管理責任者は常駐していなくてもいい
一人での客先常駐の業務委託契約が偽装請負・労働者派遣法違反となる2つめの条件は、受託者の管理責任者が常駐外で選任されていても、管理業務ができていないことです。
実は、受託者の管理責任者は、委託者の事業所に常駐している必要はありません。
これは、疑義応答集第2集において、明確に回答されています。
このため、一人での客先常駐の業務委託契約は必ずしも違法ではありませんし、「客先常駐は2人以上でなければ違法」という考え方は誤りです。
管理責任者が不在でも管理は徹底されている必要がある
ただし、「管理責任者の不在時であっても、請負事業主が自己の雇用する労働者の労働力を自ら利用するものであること」が必要とされています(疑義応答集第2集)。
このため、せっかく常駐外の管理責任者を選任していたとしても、その管理責任者が常駐している受託者の労働者の管理をしていなければ、委託者が受託者の労働者を管理していることとなり、偽装請負・労働者派遣法違反に該当します。
よって、単に常駐外の管理責任者を選任するだけでなく、以下の点が重要となります(同上)。
常駐外の管理責任者による管理のポイント
- 発注者と請負事業主の管理責任者との確実な連絡体制をあらかじめ確立しておくこと
- 請負労働者の出退勤管理を含む労働時間管理等労働者の管理や業務遂行に関する指示等を請負事業主自らが確実に行えるようにしておくこと
なお、以上の点は具体例に過ぎませんので、これだけしていれば問題がないわけではありません。
【条件3】受託者の作業者が管理責任者を兼任していること
一人での客先常駐の業務委託契約が偽装請負・労働者派遣法違反となる3つめの条件は、受託者の作業者が管理責任者を兼任していることです。
管理責任者は、受託者の労働者の管理について専任されている必要なく、作業者と兼任しても、管理責任者としての責任を果たせるのであれば問題はありません(疑義応答集第2集Q4)。
しかしながら、それはあくまで2名以上が常駐している場合です。
「作業者が1人しかいない場合で当該作業者が管理責任者を兼任している場合は、実態的には発注者から管理責任者への注文が、発注者から請負労働者への指揮命令となる」ため、偽装請負・労働者派遣法違反となります。
【条件4】委託者が受託者の労働者の人数を「一人」に指定すること。
一人での客先常駐の業務委託契約が偽装請負・労働者派遣法違反となる4つめの条件は、委託者が受託者の労働者の人数を「一人」に指定していることです。
すでに述べた37号告示第2条第1号第2条第1号ハ(2)には、「労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと」と規定されています。
このため、実際に業務に従事する受託者の労働者の人数について、受託者ではなく委託者が指定することは、この第2条第1号ハ(2)に抵触します。
ここでいう「労働者」は受託者の労働者であり、「自ら」は受託者のことを意味します。
よって、委託者が受託者の労働者の人数を「一人」に指定していることは、偽装請負・労働者派遣法違反となります。
この他、委託者による受託者の労働者の人数の指定に関する違法性につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
なお、「一人」に指定することとは別に、作業者を「指名すること」も、人数にかかわらず、同様の理由で違法となります。
この他、作業者・人の指定・指名の違法性につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 受託者の管理責任者が選任されていないと偽装請負・労働者派遣法違反。
- 常駐外で受託者の管理責任者が常駐外で選任されていても、管理業務ができていないと偽装請負・労働者派遣法違反。
- 受託者の作業者が管理責任者を兼任していると偽装請負・労働者派遣法違反。
- 委託者が受託者の労働者の人数を指定することは偽装請負・労働者派遣法違反。
適法な一人での客先常駐となる条件とは?
委託者が受託者の労働者に対し直接指示・指揮命令をしていない状態かどうかがポイント
以上のように、一人での客先常駐の業務委託契約は、偽装請負・労働者派遣法違反とみなされやすいのですが、必ずしも、違法=偽装請負・労働者派遣法違反となるわけではありません。
そこで、次に、違法=偽装請負・労働者派遣法違反とならない、適法な一人での客先常駐の業務委託契約の条件を解説します。
偽装請負・労働者派遣法違反とならない適法な一人での客先常駐の条件は、以下のとおりです。
適法な一人での客先常駐の条件
- 受託者の作業者以外に受託者の管理責任者が選任されていること。
- 受託者の管理責任者が常駐でなくても常に管理業務ができる状態であること。
- 受託者の作業者に対し、委託者が直接指示・指揮命令をしていないこと。
- 受託者が自らの労働者の人数を「一人」に指定すること。
- 上記の内容を反映した業務委託契約書が作成されていること。
これらのすべてを満たした場合は、偽装請負・労働者派遣法違反とならず、適法な業務委託契約になります。
ポイントは、これらのいずれもが、「委託者が受託者の労働者に対し直接指示・指揮命令をしていない状態」であることです。
逆に言えば、「受託者の管理責任者が受託者の労働者に対し直接指示・指揮命令をしている状態」であることです。
以下、それぞれ詳しく解説します。
【条件1】受託者の作業者以外に受託者の管理責任者が選任されていること
一人での客先常駐の業務委託契約が適法となる1つめの条件は、受託者の作業者以外に受託者の管理責任者が選任されていることです。
すでに述べたとおり、37号告示第2条第1号では、労働者の様々な事項に関する管理について、受託者「自ら行う」ことを求めています。
よって、まずは受託者の労働者の管理をおこなう管理責任者が選任されていなければなりません。
【条件2】受託者の管理責任者が常駐でなくても常に管理業務ができる状態であること
一人での客先常駐の業務委託契約が適法となる2つめの条件は、受託者の管理責任者が常駐でなくても常に管理業務ができる状態であることです。
こちらもすでに述べたとおり、受託者の管理責任者は、委託者の事業所に常駐している必要はありません(疑義応答集第2集Q8)。
この条件が、一人での客先常駐において、最も重要なポイントと言えるでしょう。
ただし、常駐外の管理責任者は、単に選任されているだけではなく、「業務遂行に関する指示、労働者の管理等を自ら的確に行っている」ことが求められます。
こちらについても、すでに述べたとおり、以下の点が重要となります(同上)。
常駐外の管理責任者による管理のポイント
- 発注者と請負事業主の管理責任者との確実な連絡体制をあらかじめ確立しておくこと
- 請負労働者の出退勤管理を含む労働時間管理等労働者の管理や業務遂行に関する指示等を請負事業主自らが確実に行えるようにしておくこと
なお、以上の点は具体例に過ぎませんので、これだけしていれば問題がないわけではありません。
【条件3】受託者の作業者に対し、委託者が直接指示・指揮命令をしていないこと
一人での客先常駐の業務委託契約が適法となる3つめの条件は、受託者の作業者に対し、委託者が直接指示・指揮命令をしていないことです。
上記のように、受託者の管理責任者が選任されており、かつ、常駐外であっても管理責任を果たしていることが、一人での客先常駐の業務委託契約が偽装請負・労働者派遣法違反とならない最低限の条件です。
ただ、これらの条件を満たしていたとしても、同じように委託者から受託者の労働者に対する直接の指示・指揮命令があると、結局は、偽装請負・労働者派遣法違反に該当します。
このため、受託者の管理責任者による受託者の労働者の管理とは別に、委託者からは、受託者の労働者に対する直接の指示・指揮命令がないようにしなければなりません。
【条件4】受託者が自らの労働者の人数を「一人」に指定すること。
一人での客先常駐の業務委託契約が適法となる4つめの条件は、受託者が受託者自身の労働者の人数を「一人」に指定していることです。
すでに述べたとおり、委託者による受託者の労働者の人数の指定は、偽装請負・労働者派遣法違反となります。
逆に言えば、37号告示第2条第1号第2条第1号ハ(2)にあるとおり、受託者自身が「労働者の配置等の決定及び変更を自ら行う」場合は、特に問題はありません。
このため、一人での客先常駐について、「一人」とする決定は、委託者ではなく、受託者自身がおこなう必要があります。
【条件5】上記の内容を反映した業務委託契約書が作成されていること
一人での客先常駐の業務委託契約が適法となる5つめの条件は、委託者から受託者の作業者に対し直接指示・指揮命令がなされていないことを反映した業務委託契約書が作成されていることです。
37号告示では、適法な一人での客先常駐の業務委託契約とすることについて、特に書面や契約書の作成は求められていません。
しかしながら、厚生労働省では、37号告示の具体的判断基準として、以下の内容を示しています。
(2)次の①及び②のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理
を自ら行うものであること。① 労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く)を自ら行うこと。
(具体的判断基準)
当該要件の判断は、受託業務の実施日時(始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等)について、事前に事業主が注文主と打ち合わせているか、業務中は注文主から直接指示を受けることのないよう書面が作成されているか、それに基づいて事業主側の責任者を通じて具体的に指示が行われているか、事業主自らが業務時間の実績把握を行っているか否かを総合的に勘案して行う。
引用元:労働者派遣・請負を適正に 行うためのガイドp.4
このほか、具体例として上げられている、医療事務受託業務や製造業務の場合についても、書面の作成は求められています。
いずれにせよ、上記の判断基準は、特に業種に言及されていない一般的な基準であるため、医療事務受託業務や製造業務に該当しない場合であっても、業務委託契約書の作成は必須と言えます。
業務委託契約書を作成する理由
偽装請負・労働者派遣法違反にならない適法な業務委託契約では、指示・指揮命令があってはならないことから、委託者から受託者の労働者に対し、直接の指示・命令を受けることがないよう規定した契約書が必要となるから。
なお、当然ながら、業務委託契約書を作成しただけでは不十分であり、「それに基づいて事業主側の責任者を通じて具体的に指示が行われている」ことも重要となります(同上)。
ポイント
- 適法な一人での客先常駐の業務委託契約では、受託者の作業者以外に受託者の管理責任者が選任されている必要がある。
- 受託者の管理責任者は、常駐していなくても、常に管理業務ができる状態でなけばならない。
- 委託者は、受託者の作業者に対し、直接指示・指揮命令をしてはいけない。
- 適法な一人での客先常駐の業務委託契約とするためには、上記の内容を反映した業務委託契約書が作成しなければならない。
適法な一人での客先常駐の業務委託契約書とするポイントは?
一人での客先常駐の業務委託契約書は特殊な契約書
以上のように、偽装請負・労働者派遣法違反とならない一人での客先常駐の業務委託契約では、様々な条件があります。
適法な一人での客先常駐の業務委託契約とするためには、これらの条件を満たしつつ、他の37号告示の基準にも抵触しないようにする必要があります。
このため、一人での客先常駐の業務委託契約書は、他の一般的な業務委託契約書と比べて、特殊な契約内容となります。
具体的には、以下の点に配慮する必要があります。
偽装請負・労働者派遣法違反とならない一人での客先常駐の業務委託契約書のポイント
- 37号告示に準拠した契約内容とする
- 指示・指揮命令に関して詳細な連絡体制・方法・ツールを規定する
- 委託者側の禁止事項を明確にする
以下、それぞれ詳しく解説していきます。
【ポイント1】37号告示に準拠した契約内容とする
37号告示の判断基準を満たすことが大前提
偽装請負・労働者派遣法違反とならない一人での客先常駐の業務委託契約書の1つめのポイントは、37号告示に準拠した契約内容とすることです。
すでに述べたとおり、37号告示は、偽装請負・労働者派遣法違反と適法な業務委託契約の判断基準となります。
このため、37号告示に準拠した契約内容とすることは、適法な業務委託契約書の作成の大前提となります。
指示・指揮命令の部分以外も満たした内容とする。
37号告示の判断基準は、すべて満たしている必要があります。
このため、後述する指示・指揮命令の部分以外の部分も満たしている必要があります。
具体的には、以下のチェックポイントの7.以下の部分です。
偽装請負(労働者派遣法違反)とならないチェックリスト
- 1.「業務の遂行方法に関する指示その他の管理」を受託者が自らおこなっている。
- 2.「業務の遂行に関する評価等に係る指示」を受託者が自らおこなっている。
- 3.「労働時間の指示」を受託者が自らおこなっている。
- 4.「残業・休日出勤の指示」を受託者が自らおこなっている。
- 5.「服務規律の指示」を受託者が自らおこなっている。
- 6.「労働者の配置の決定・変更」を受託者が自らおこなっている。
- 7.受託者が運転資金などの自己資金を自ら調達し、使用している。
- 8.受託者が事業主としての民法・商法等の法律に基づく責任の負担している。
- 9.業務内容が単に肉体的な労働力を提供するものでない。
- 10.受託者が自らの責任・負担での機械・設備・器材・材料・資材の調達している。
- 11.受託者自身の企画・専門的技術・専門的経験によって業務を処理している。
※ただし、10.と11.はいずれかを満たせばよい。
実際に一人での客先常駐の業務委託契約書を作成する際には、こうした指示・指揮命令関係以外の部分にも注意する必要があります。
なお、上記のチェックリストの詳細な解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
【ポイント2】指示・指揮命令に関して詳細な連絡体制・方法・ツールを規定する
偽装請負・労働者派遣法違反とならない一人での客先常駐の業務委託契約書の2つめのポイントは、指示・指揮命令に関して詳細な連絡体制・方法・ツールを規定することです。
一般的な業務委託契約では、こうした指示・指揮命令について考慮する必要はありません。
他方で、一人での客先常駐に限らず、客先常駐の契約では、連絡体制・方法・ツール等を含め、指示・指揮命令に関する詳細な内容について決定します。
そののうえで、すでに述べた厚生労働省による37号告示の具体的判断基準でもあるとおり、業務委託契約書を作成します。
【ポイント3】委託者側の禁止事項を明確にする
偽装請負・労働者派遣法違反とならない一人での客先常駐の業務委託契約書の3つめのポイントは、委託者側の禁止事項を明確にすることです。
上記のポイント2にあるとおり、指示・指揮命令等の連絡体制、方法、ツールなどを、いわゆる「ホワイトリスト方式」で規定します。
ただ、これだけでは不十分であり、併せて、委託者側の禁止事項について、「ブラックリスト方式」で規定します。
これは、特に指示・指揮命令に関連する行為について、禁止事項として規定することとなります。
【補足】下請法の3条書面に準拠した契約書とする
なお、一人での客先常駐の業務委託契約、特にSES契約(システムエンジニアリングサービス契約)では、下請法の規制対象となることが多いです。
このため、下請法を遵守した契約内容とする必要があります。
特に、委託者の立場としては、受託者に対し、いわゆる「三条書面」を交付する義務があります。
よって、一人での客先常駐の業務委託契約書を三条書面として交付する場合は、その記載事項も、下請法第3条を遵守したものとしなければなりません。
偽装請負(労働者派遣法違反)のリスクは?
偽装請負・労働者派遣法違反のリスクは委託者・受託者の双方にある
実際に、業務委託契約が偽装請負と判断された場合は、様々なリスクが発生します。
わかりやすい例としては、受託者の側は、無許可での労働者派遣事業をおこなっていたことになります。
勘違いされがちですが、委託者の側は、偽装請負で何の問題がないわけではなく、派遣先としての義務に違反することになります。
つまり、偽装請負・労働者派遣法違反のリスクは、受託者だけでなく、委託者にもあることとなります。
このほか、具体的なリスク・問題点は、次のとおりです。
委託者の偽装請負のリスク・問題点一覧
偽装請負の委託者のリスク・問題点
- 「派遣先」とみなされる
- 労働者派遣法違反となる
- 各種罰則が科される
受託者の偽装請負のリスク・問題点一覧
偽装請負の受託者のリスク・問題点
- 派遣元=無許可の派遣業者とみなされる
- 労働者派遣法違反となる
- 各種罰則が科される
委託者・受託者共通のリスク・問題点一覧
委託者・受託者共通のリスク・問題点
- 行政指導・行政処分を受ける
- 労働契約申込みみなし制度
- 罰則は法人だけでなく個人にも科される
- 適法な業務委託契約にするコストがかかる
ポイント
- 偽装請負は、受託者はもとより、委託者も労働者派遣法違反となる。
一人での客先常駐の業務委託契約に関するよくある質問
- 一人での客先常駐は偽装請負・労働者派遣法違反となりますか?
- 一人での客先常駐は、それ自体は偽装請負・労働者派遣法違反にはならず、一人での客先常駐であることによって、結果的に委託者から受託者の労働者に対し、直接指示・指揮命令がされてしますことによって、偽装請負・労働者派遣法違反となります。
- 偽装請負・労働者派遣法違反とならない一人での客先常駐の条件について教えてください。
- 偽装請負・労働者派遣法違反とならない一人での客先常駐は、以下の条件のすべてを満たしている必要があります。
- 受託者の作業者以外に受託者の管理責任者が選任されていること。
- 受託者の管理責任者が常駐でなくても常に管理業務ができる状態であること。
- 受託者の作業者に対し、委託者が直接指示・指揮命令をしていないこと。
- 上記の内容を反映した業務委託契約書が作成されていること。
一人での客先常駐の業務委託契約書(SES契約書)の作成はおまかせください
弊所では、一人での客先常駐の業務委託契約書、システムエンジニアリングサービス契約書(SES契約書)、建設工事請負契約の作成依頼を承っております。
偽装請負となった場合、一人での客先常駐をしている受託者の側だけでなく、委託者の側も労働者派遣法違反となってしまいます。
弊所では、37号告示や関連する疑義応答集を始め、厚生労働省から出されている各種資料を丁寧に読み解き、違法とならないように配慮して、一人での客先常駐の業務委託契約書・システムエンジニアリングサービス契約書(SES契約書)を作成いたします。
お見積りは完全無料となっていますので、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。