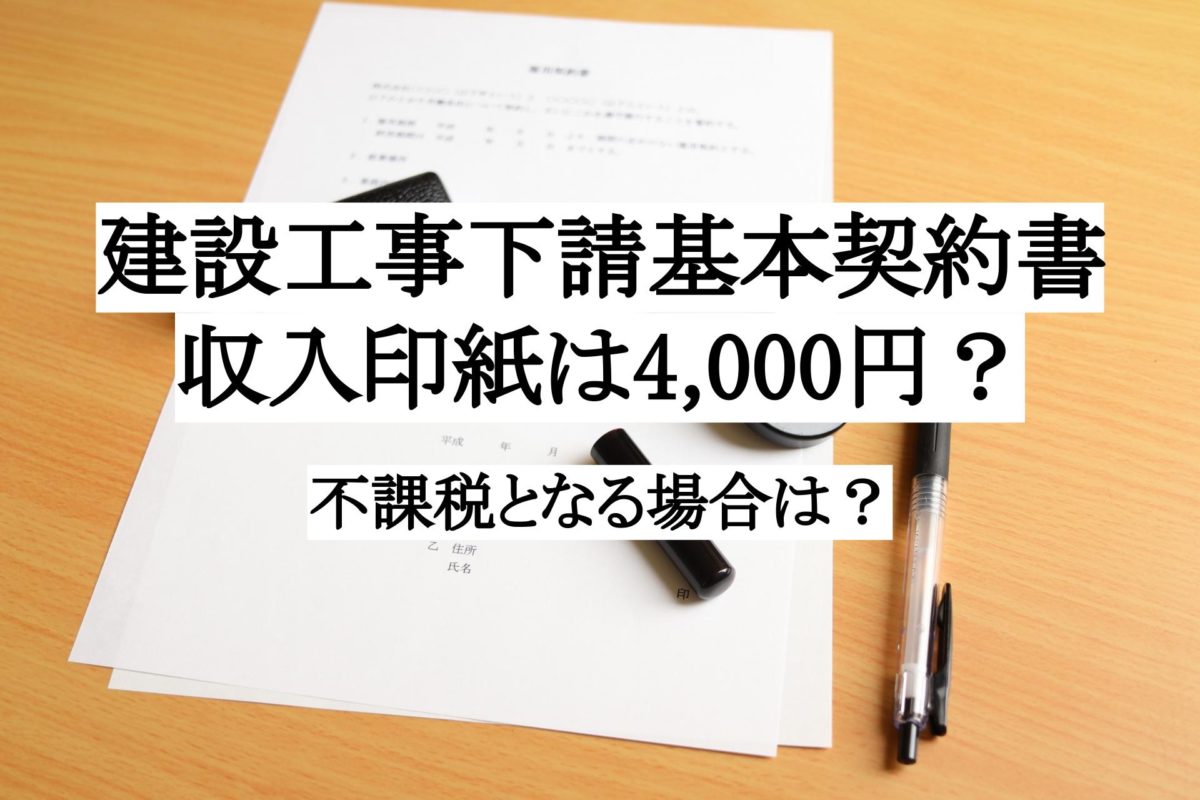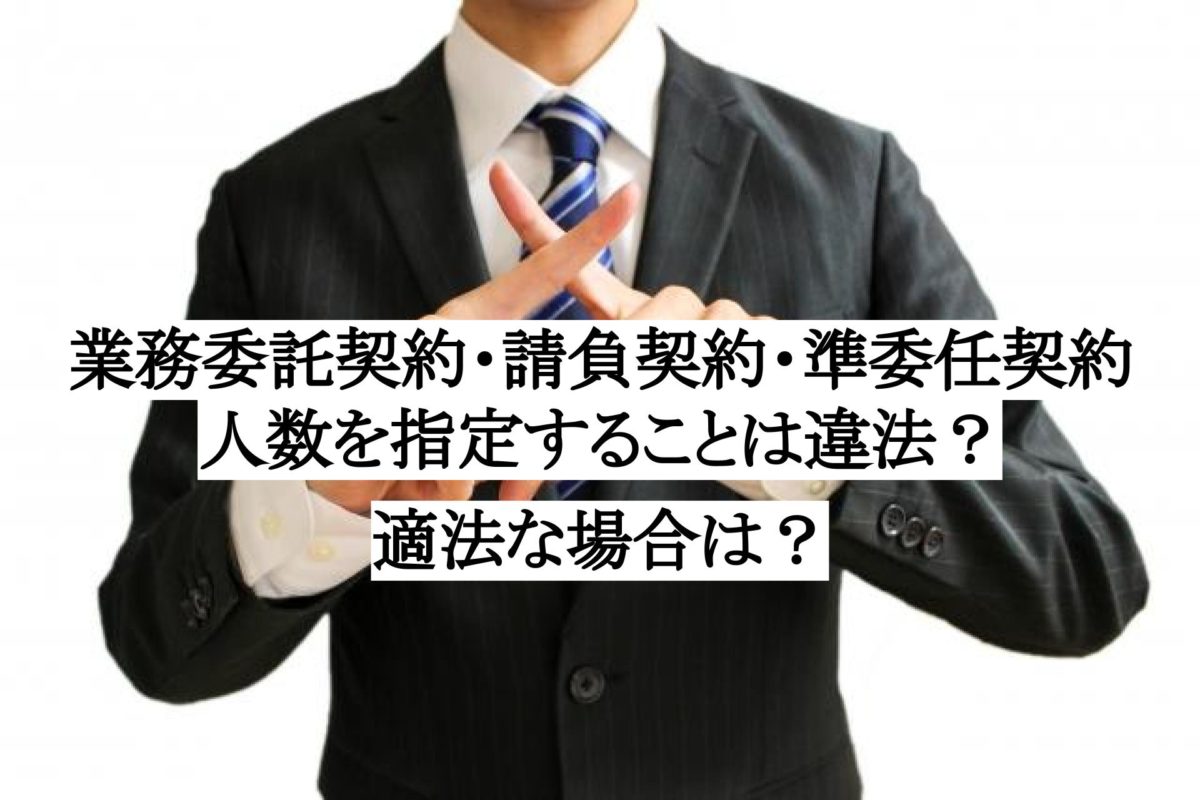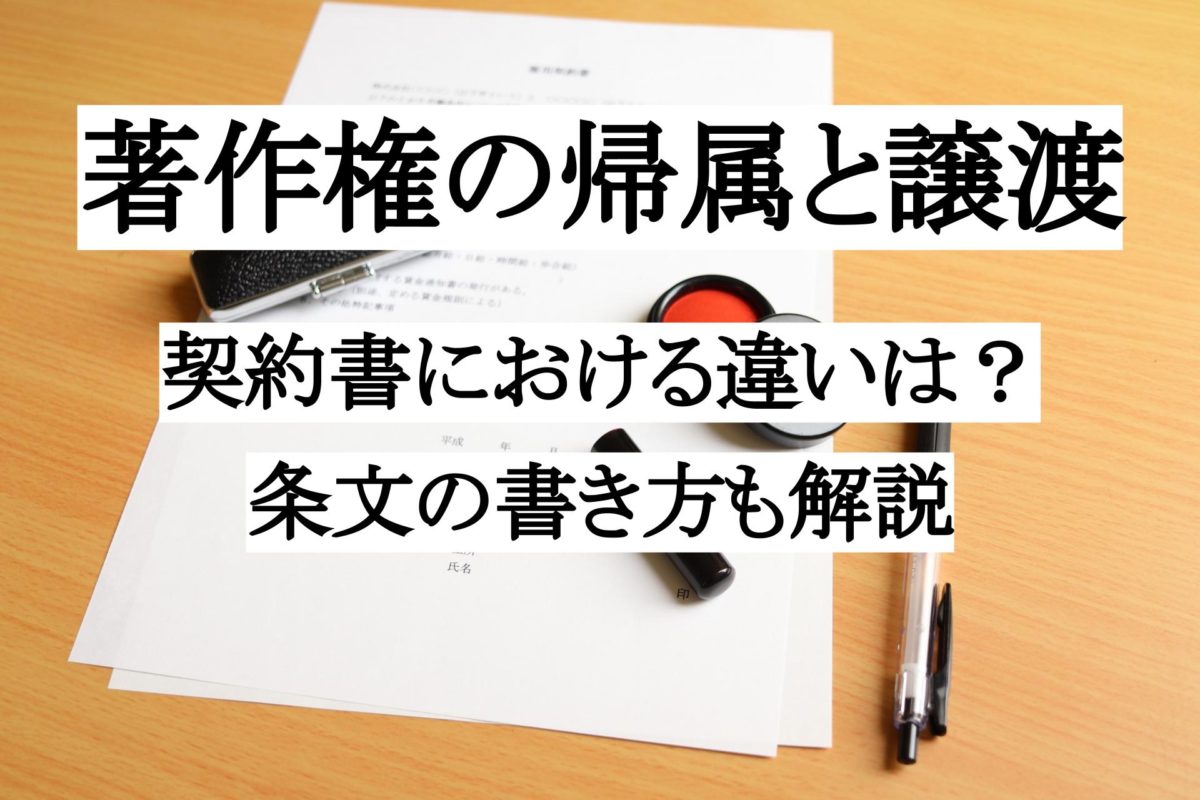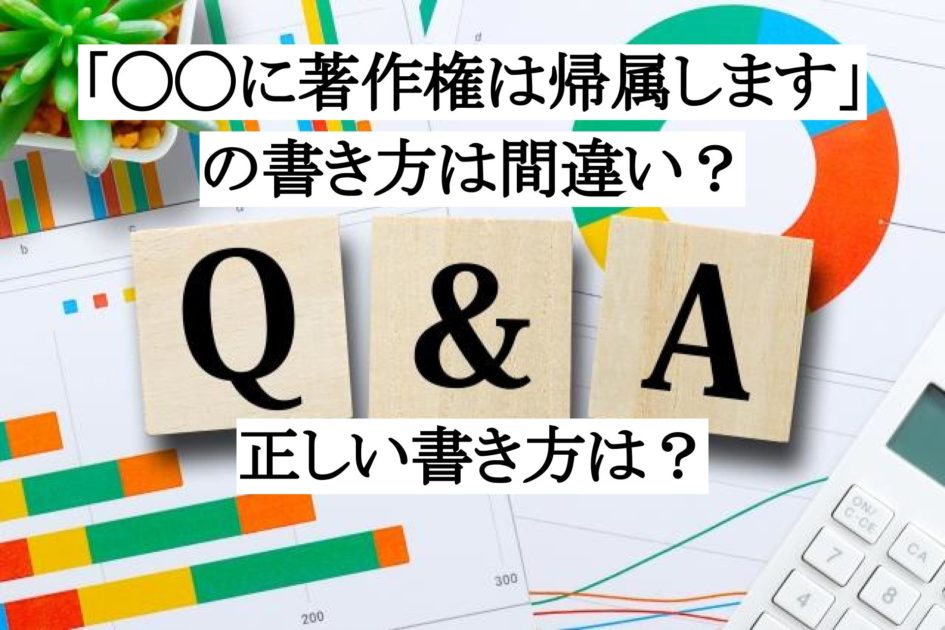
- 著作権が発生する契約書で「◯◯に著作権は帰属します」という書き方は、どのような意味になるのでしょうか?
- 契約書における「◯◯に著作権は帰属します」という書き方は、著作権者が誰であるかを明示するための規定であり、一般的には、著作権の譲渡や移転を意味する規定として記載されることが多いです。ただし、この書き方では、法的には著作権の譲渡を意味する規定と解釈されない可能性があります。
このページでは、著作権が発生する業務委託契約等の当事者向けに、著作権の譲渡・移転に関する規定の書き方について解説しています。
著作権が発生する契約では、「◯◯に著作権は帰属します」と規定されることがあります。
このような規定は、著作権の帰属を確認するための条項であることもありますが、ほとんどの場合は、著作権の譲渡・移転を意図した条項として規定されます。
しかしながら、そもそも著作権は原始的に著作者に帰属するものであるため、このような記載をした場合は契約条項として無効となるリスクがあります。
このページでは、こうした「◯◯に著作権は帰属します」という条項の書き方について、開業20年・400社以上の取引実績がある管理人が、わかりやすく解説していきます。
このページでわかること
- 「◯◯に著作権は帰属します」という条項の意味・意図
- 「◯◯に著作権は帰属します」という条項の間違い
- 著作権の譲渡・移転の条項の正確な書き方
「◯◯に著作権は帰属します」は著作権の譲渡・移転を意図した規定
著作権が発生する契約書では、発生した著作権の取り扱いについて、以下のように規定されている場合があります。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】著作権の帰属条項
第○条(著作権の帰属)
受託者による本件業務の実施により著作権が発生した場合、委託者に著作権は帰属します。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
一般的に、このような書き方は、受託者に発生した著作権を委託者に移転・譲渡をする目的・意図で規定されるものです。
しかしながら、表現としては「帰属」と記載しているため、移転・譲渡の目的・意図がある場合は、この書き方は正確ではありません。
このような不正確な表現は、契約条項として無効となる可能性もあります。
「◯◯に著作権は帰属します」は間違い
著作権は原始的に著作者に帰属する
著作権法における著作権の帰属は、原則として、著作者が著作物の著作権者になることを意味します。
【意味・定義】帰属(著作権法)とは?
著作権法における著作権の帰属とは、原則として著作物の著作者が原始的にその著作物の著作権者がとなることをいう。
なお、著作権法第29条では、(著作権の帰属)という見出しとなっています。
しかしながら、これは、あくまで例外として、著作者以外の者(映画製作者、放送事業者、有線放送事業者)に著作権を帰属させるための規定に過ぎません。
著作者以外の者に「著作権が帰属する」は「無効」?
このように、原則としては、著作権は著作者に原始的に帰属します。
つまり、著作権が著作者に原始的に帰属するからこそ、わざわざ著作権法第29条で例外を規定しているわけです。
このため、新しく発生する著作権については、「著作者以外の者に原始的に著作権が帰属する契約条項は無効である」という考え方もあります。
つまり、例えば以下の例文の場合は、「本来は受託者に著作権が帰属する著作権法の原則を無視した表現であるため無効となる」という考え方です。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】著作権の帰属条項
第○条(著作権の帰属)
受託者による本件業務の実施により著作権が発生した場合、委託者に著作権は帰属します。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
なお、職務著作の場合は、労働者等の「業務に従事する者」ではなく、その使用者である「法人等」が、「著作者」となります(著作権法第15条)。
「◯◯に著作権は帰属します」の正確な書き方は?
正確な書き方は「譲渡」
以上のように、契約条項として著作権の「帰属」を表現した場合、無効となるリスクもあります(裁判等において必ずしもそのように解釈されるとは限りませんが)。
そこで、著作権の移転・譲渡をする目的・意図で規定する場合は、「帰属」ではなく「譲渡」という表現をするべきです。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】著作権の譲渡条項
第○条(著作権の譲渡)
受託者による本件業務の実施により著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。以下、本条において同じ。)が発生した場合、報酬の支払いがあった時点で、受託者から委託者に著作権は譲渡されます。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
著作権の譲渡とは
著作権法における著作権の譲渡は、すでに存在する著作権について著作権者から別の者に移転させる、という意味になります。
【意味・定義】譲渡(著作権法)とは?
著作権法における著作権の譲渡とは、著作権を著作権者から別の者に移転させることをいう。
著作権の「譲渡」という用語・概念は、著作権法第61条に等おいて使用されています。
著作権法第61条(著作権の譲渡)
1 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
引用元:著作権法 | e-Gov法令検索
この他、著作権の帰属と譲渡の違いにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
譲渡される著作権には必ず「著作権法第27条および第28条の権利」を含める
「著作権法第27条及び第28条の権利」とは?
なお、カッコ書きの「著作権法第27条および第28条の権利を含む。」という記載は、著作権法第61条第2項の規定に対応したものです。
著作権法第61条(著作権の譲渡)
1 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
引用元:著作権法 | e-Gov法令検索
著作権法第27条の権利は、翻案権・翻訳権です。
著作権法第27条(翻訳権、翻案権等)
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
引用元:著作権法 | e-Gov法令検索
【意味・定義】翻訳権・翻案権とは?
翻訳権・翻案権とは、二次的著作物(著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物)を創作できる権利をいう。
著作権法第28条の権利は、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利です。
著作権法第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
引用元:著作権法 | e-Gov法令検索
これらの「著作権法第27条および第28条の権利」は、著作権法第61条第2項にあるとおり、特約として譲渡の目的として特掲されていなければ、譲渡者に留保したものと推定されます。
このため、著作権が発生する業務委託契約では、必ず業務委託契約書を作成し、「著作権法第27条および第28条の権利」を含めて、著作権が譲渡されるようにします。
業務委託契約書を作成する理由
著作権法では、著作権の譲渡について、特約として「著作権法第27条および第28条の権利」の譲渡について特掲しないと、譲渡者にこれらの権利が留保される可能性が高いことから、特約として「著作権法第27条および第28条の権利を含む。」著作権が譲渡された旨を規定した契約書が必要となるから。
「推定する」とは?
なお、著作権法第61条第2項は、「第27条又は第28条に規定する権利」が「譲渡した者に留保されたもの推定する」という、いわゆる「推定規定」です。
【意味・定義】推定するとは?
推定するとは、ある事実があった場合に、反証がない限り、法律上、そのような効果を認めることをいう。このため、その事実とはことなる反証があった場合は、その反証が認められる。
推定規定は、いわゆる「みなし規定」とは異なり、反証がある場合は、この推定を覆えすことができます。
このため、「著作権法第27条および第28条の権利」の譲渡について特約の特掲が無かったとしても、反証があれば、著作権法第61条第2項の規定を覆すことができます。
ただ、その反証が困難であることもあるため、契約実務では、すでに述べた特約を必ず明記するようにします。
単に著作権の帰属を明示する場合もある
なお、「◯◯に著作権は帰属します」という表現は、場合によっては、単に著作権の帰属について明示しただけに過ぎないこともあります。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】著作権の帰属条項
第○条(著作権の帰属)
受託者による本件業務の実施により著作権が発生した場合、受託者に著作権は帰属します。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
上記の例の場合、一般的な著作物の著作権であれば、著作権法にもとづき当然に受託者に帰属します。
このため、このような規定は、法的には特に意味がなく、せいぜい、念のために規定される「為念規定」としての意味があるに過ぎません。