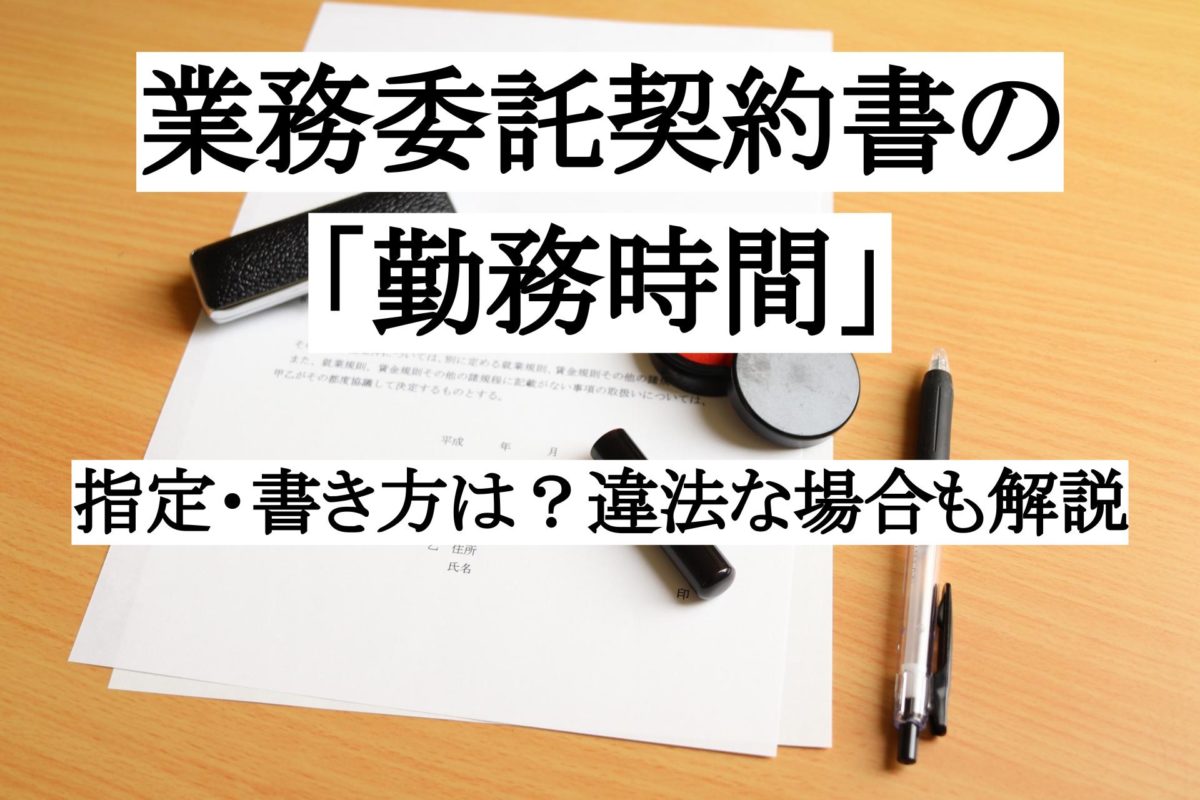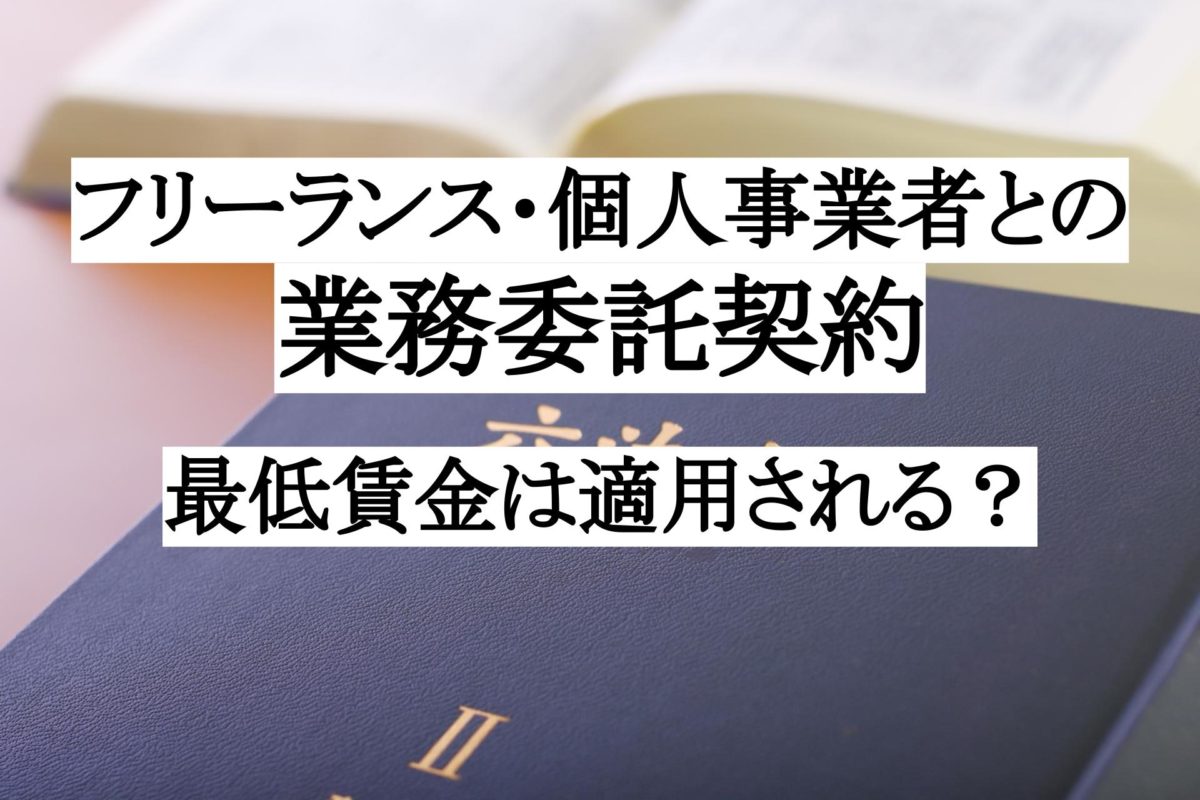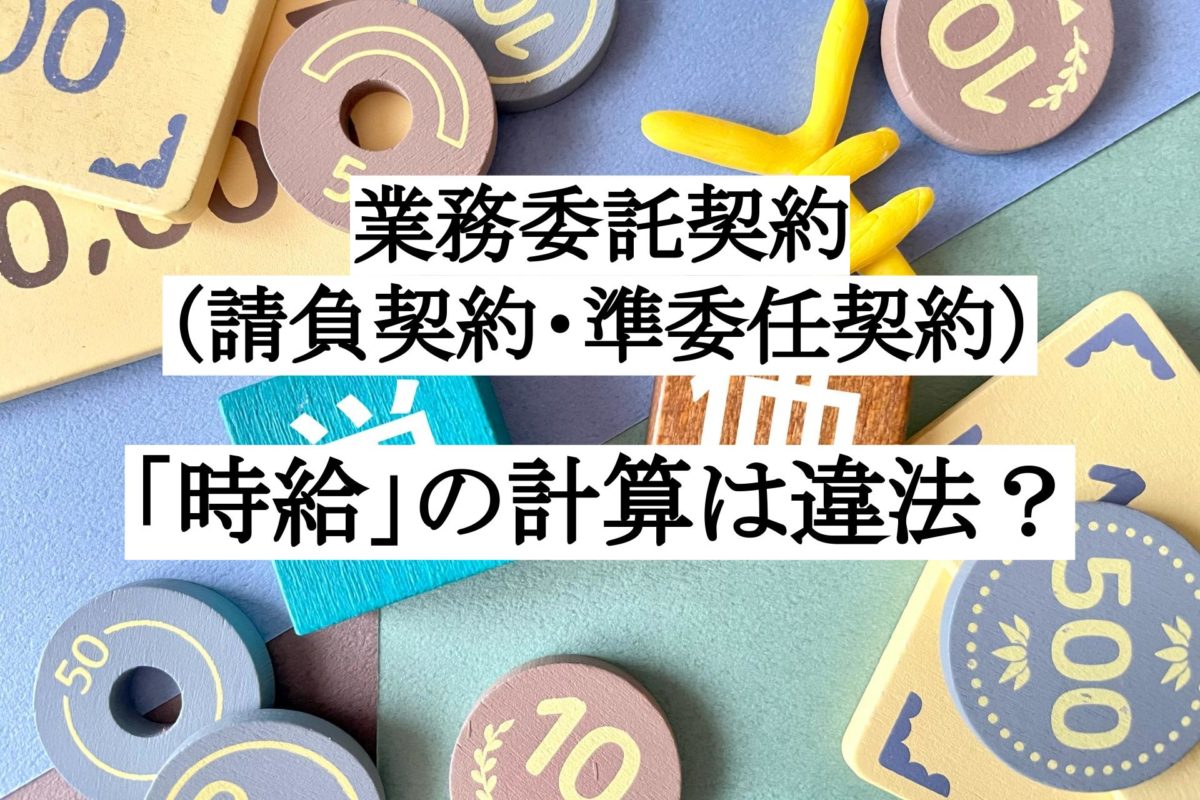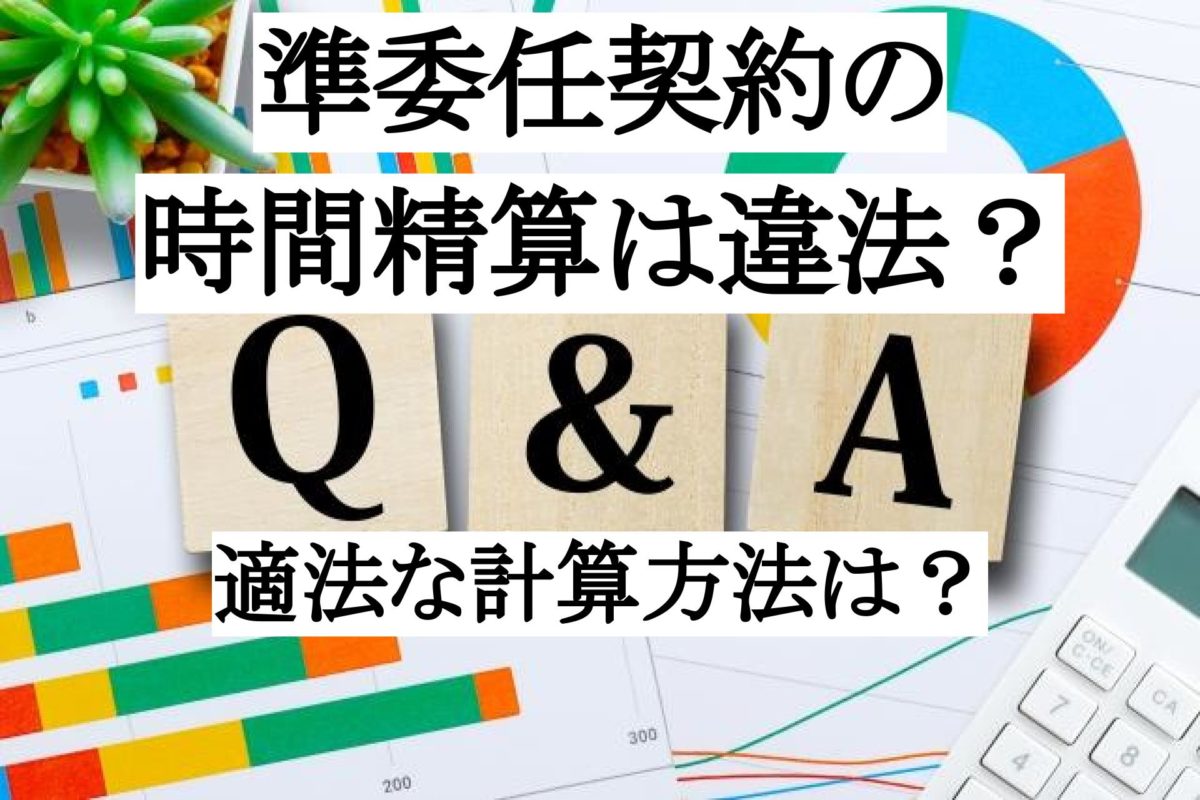
- 準委任契約型の業務委託契約では、委託者が受託者に対し時間精算で委託料を支払うと違法になるのでしょうか?
- 準委任契約型の業務委託契約において、委託者が受託者に対し時間精算で報酬を支払うことは、原則として違法ではなく、適法です。
ただし、受託者が個人事業者・フリーランスである場合は、違法(偽装請負)と適法の両方の可能性があります。
このページでは、準委任契約型の業務委託契約の委託者・受託者の双方向けに、時間精算での報酬の違法性・適法性について解説しています。
準委任契約において、委託者が受託者に対し支払う報酬を時間あたりの計算(時間精算)としたとしても、原則として適法であり、特に問題にはなりません。
ただし、受託者が個人事業者・フリーランスである場合は、金額の計算のしかたや金額の多寡によっては、時間精算の報酬は、「指揮命令」とみなされ、受託者が労働者扱いとなり、各種労働法違反(偽装請負)となる可能性があります。
つまり、準委任契約において、受託者が個人事業者・フリーランスの場合は、時間精算の報酬は、適法な場合と違法(偽装請負)の場合があります。
このページでは、こうした準委任契約型の業務委託契約における時間精算の報酬に関する違法性と適法性について、開業20年・400社以上の取引実績がある管理人が、わかりやすく解説していきます。
このページでわかること
- 準委任契約型の業務委託契約における時間精算の報酬が違法性・適法性。
- 受託者が個人事業者・フリーランスとなる場合において、時間精算の報酬が違法・適法となる条件。
準委任契約における時間精算の報酬は適法?違法?
時間精算の報酬は原則として適法
企業間契約である準委任契約において、時間あたりの報酬=時間精算の報酬は、契約自由の原則により、原則として違法ではありません。
【意味・定義】契約自由の原則とは?
契約自由の原則とは、契約当事者は、その合意により、契約について自由に決定することができる民法上の原則をいう。
民法第521条(契約の締結及び内容の自由)
1 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
上記の民法第521条第2項にあるとおり、「法令の制限内」ではありますが、準委任契約において時間精算の報酬としたとしても、原則として違法=法律違反にはありません。
このような時間精算の報酬は、いわゆる「タイムチャージ」や「出来高払い」と言われ、ビジネスの現場ではよく使われている計算方法です。
個人事業者・フリーランス相手では各種労働法違反の偽装請負となる
ただし、受託者が個人事業者・フリーランスの場合において、時間精算の報酬を設定したときは、準委任契約ではなく、労働契約・雇用契約とみなされる可能性があります。
個人事業者・フリーランスとの契約が労働契約・雇用契約とみなされた場合、委託者は使用者、受託者は労働者とみなされます。
これにより、委託者は、労働基準法、労働契約法、最低賃金法等の各種労働法に違反する可能性があります。
また、各種社会保険料についても、遡って支払義務が発生する可能性もあります。
準委任契約とは?
準委任契約=作業・助言・企画・知識・技芸の提供・教授などの契約
なお、準委任契約は、民法では、以下のように規定されています。
民法第656条(準委任)
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
【意味・定義】準委任契約とは?
準委任契約とは、委任者が、受任者に対し、法律行為でない事務をすることを委託し、受任者がこれ受託する契約をいう。
ここでいう「事務」というのは、一般的な用語としての事務(例:事務を執る、事務所、事務職など)ではなく、もっと広い概念です。
民法上は定義がありませんが、作業、助言、企画、知識・技芸の教授など、「法律行為でない行為」が該当します。
ちなみに、「準用」とは、ある法律の規定を、必要な修正・変更をしたうえで、類似した別の規定に当てはめることをいいます。
【意味・定義】準用とは?
準用とは、ある法律の規定を、必要な修正・変更をしたうえで、類似した別の規定に当てはめることをいう。
契約実務においては、法律の条文だけでなく、契約条項としても、「準用する」場合があります。
準委任契約の代表例・具体例
準委任契約の代表例や具体例には、以下のものがあります。
準委任契約の代表例・具体例一覧
- 医師や医療機関との医療行為準委任契約(企業間取引としては産業医嘱託契約など)
- アジャイル開発のシステム等開発委託契約
- システムエンジニアリングサービス契約(SES契約)
- 経営コンサルティング契約
このように、企業間取引における準委任契約は、継続的な契約が多いです。成果物の納入の有無は、契約内容によります。
なお、これらは、あくまでも代表的な例であり、実際のビジネスの現場では、様々な準委任契約が締結されています。
この他、準委任契約につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
個人事業者・フリーランスが受託者の場合は時間精算の報酬は適法?違法?
必ずしも「時間精算=指揮命令=違法」とは限らない
受託者が個人事業者・フリーランスの場合における準委任契約において、時間精算の報酬を設定したときは、報酬の計算のしかたや報酬の金額によって違法となる可能性と適法となる可能性の両方があります。
時間精算の違法性・適法性(個人事業者・フリーランスが受託者の場合)
- 1.「使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることに対する対価」としての時間精算の報酬=違法
- 2.「報酬について給与所得としての源泉徴収を行っている」場合における時間精算の報酬=違法
- 3.委託者の「同様の業務に従事している正規従業員に比して著しく高額である場合」おける時間精算の報酬=適法
1.と2.の場合は、いわゆる「指揮命令」に該当し、準委任契約が労働契約・雇用契約(偽装請負)とみなされ、委託者が労働基準法・労働契約法等の労働法に違反する可能性があります。
また、この場合は、受託者である個人事業者・フリーランスが労働者とみなされます。
他方で、3.の場合は、時間精算の報酬であっても、適法な準委任契約と判断される可能性が高いです。
つまり、個人事業者・フリーランスが受託者となる準委任契約において、時間精算の報酬は、必ずしも違法となるわけではありません。
労働者性の判断基準=「労働基準法研究会報告」とは?
上記の違法性・適法性の判断基準は、「労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)(昭和60年12月19日)」によるものです。
この「労働基準法研究会報告」の第2 1(2)に、以下の記載があります。
(2)報酬の労務対償性に関する判断基準
労働基準法第11条は、「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と規定している。すなわち、使用者が労働者に対して支払うものであって、労働の対償であれば、名称の如何を問わず「賃金」である。この場合の「労働の対償」とは、結局において「労働者が使用者の指揮監督の下で行う労働に対して支払うもの」と言うべきものであるから、報酬が「賃金」であるか否かによって逆に「使用従属性」を判断することはできない。
しかしながら、報酬が時間給を基礎として計算される等労働の結果による較差が少ない、欠勤した場合には応分の報酬が控除され、いわゆる残業をした場合には通常の報酬とは別の手当が支給される等報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることに対する対価と判断される場合には、「使用従属性」を補強することとなる。
同様に、の第2 1(3)に、以下の記載があります。
(3)その他
以上のほか、裁判例においては、①採用、委託等の際の選考過程が正規従業員の採用の場合とほとんど同様であること、②報酬について給与所得としての源泉徴収を行っていること、③労働保険の適用対象としていること、④服務規律を適用していること、⑤退職金制度、福利厚生を適用していること等「使用者」がその者を自らの労働者と認識していると推認される点を、「労働者性」を肯定する判断の補強事由とするものがある。
これにより、時間精算が「報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることに対する対価と判断される場合」や「報酬について給与所得としての源泉徴収を行っている」場合は違法(労働基準法・労働契約法等の各種労働法違反)となります。
他方で、「労働基準法研究会報告」の第2 2(1)ロに、以下の記載があります。
ロ 報酬の額
報酬の額が当該企業において同様の業務に従事している正規従業員に比して著しく高額である場合には、上記イと関連するが、一般的には、当該報酬は、労務提供に対する賃金ではなく、自らの計算と危険負担に基づいて事業経営を行う「事業者」に対する代金の支払と認められ、その結果、「労働者性」を弱める要素となるものと考えられる。
これにより、時間精算が委託者の「同様の業務に従事している正規従業員に比して著しく高額である場合」は適法となります。
この他、「労働基準法研究会報告」につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
時間精算の準委任契約が違法となる条件(受託者=個人事業者・フリーランス)
あくまで「時間あたりの労務の提供に対する対価」=違法
以上の点をまとめると、個人事業者・フリーランスが受託者である準委任契約の場合、時間精算の報酬が違法となる条件は、次のとおりです。
時間精算が違法(労働法違反・偽装請負)となる条件
- 「労働の結果による較差が少ない」こと。
- 「欠勤した場合には応分の報酬が控除され」ること。
- 「いわゆる残業をした場合には通常の報酬とは別の手当が支給される」こと。
これらの条件を満たすことによって、「報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることに対する対価と判断される場合」、受託者である個人事業者・フリーランスが労働者扱いとなり、違法(労働基準法、労働契約法、最低賃金法等の各種労働法の違反)となる可能性があります。
「給与所得」としての源泉徴収=違法
また、時間精算に限りませんが、個人事業者・フリーランスが受託者である場合において、「給与所得」として源泉徴収をしている場合は、「『労働者性』を肯定する判断の補強事由とする」判例があります。
源泉徴収により違法(労働法違反・偽装請負)となる条件
- 「報酬について給与所得としての源泉徴収を行っていること」
ただ、これは誤解されがちですが、すべての源泉徴収が違法となるのではなく、「給与所得」として源泉徴収をした場合です。
委託者が、「報酬若しくは料金、契約金又は賞金」(所得税法第204条)として源泉徴収をする場合は、特に問題ありません。
むしろ源泉徴収をしなければ、所得税法違反となります。
このため、報酬について、本来は必要のない(給与所得としての)源泉徴収をしている場合は、違法となる可能性があります。
すべての時間精算が違法になるわけではない
ただし、これらの条件を満たしたとしても、あくまで「使用従属性」を補強する要素や「労働者性」を肯定する判断の補強事由となるのであって、直ちに違法となるのではありません。
つまり、個人事業者・フリーランスが受託者になる準委任契約であるからといって、すべての時間精算の報酬が直ちに指揮命令に該当するわけではありません。
また、これらの条件は、数多くある労働者性の判断基準のひとつに過ぎません。
この点からも、(そのこと自体は望ましくはないですが)時間精算により、直ちに「準委任契約→労働契約・雇用契約」「個人事業者・フリーランス→労働者」(偽装請負)と判断されるわけではありません。
この他、個人事業者・フリーランスの労働者性のチェックリストにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
時間精算が適法となる条件(受託者=個人事業者・フリーランス)
逆に、個人事業者・フリーランスが受託者である準委任契約の場合、時間精算の報酬が適法となる条件は、次のとおりです。
時間精算が適法となる条件
- 報酬の額が委託者において同様の業務に従事している正規従業員(正社員)に比して著しく高額であること。
このように、個人事業者・フリーランスが受託者である準委任契約の場合であっても、報酬が同様の業務に従事する正社員よりも著しく高額なときは、時間精算の報酬であっても、適法となります。
この際、単に額面上の正社員の賃金と比較するのではなく、社会保険料等も考慮するべきです。
このため、個人事業者・フリーランスであっても、例えば以下のような契約・職業は、時間精算の報酬であっても、その金額が著しく高額であれば違法とはなりません。
時間精算が適法となる個人事業者・フリーランスの具体例
- SES契約(システムエンジニアリングサービス)におけるハイスキルのエンジニア
- コンサルティング契約における経営コンサルタント
- 顧問契約における士業
時間精算が違法となる条件(受託者=法人)
受託者が法人の場合は時間精算そのものは違法ではない
一方で、受託者が法人である場合は、受託者は、当然ながら個人事業者・フリーランスでありません。
このため、こうした準委任契約が労働契約・雇用契約とみなされるリスクはありません。
この点から、冒頭で触れた「契約自由の原則」により、時間精算による報酬の設定は、労働基準法、労働契約法、最低賃金法などの各種労働法の観点では問題とはなりません。
受託者の労働者の人数の指定は違法
このように、受託者が法人である場合において、時間精算そのものは、労働法上の問題にはなりません。
しかしながら、時間精算とするために、委託者の側から受託者の労働者の人数を指定すると、違法(労働者派遣法違反=偽装請負)とみなされるリスクがあります。
ただし、委託者による受託者の労働者の人数の指定が直ちに違法となるわけではありません。
具体的には、以下の条件を満たした一定の契約内容・業務内容の場合は、労働者の人数の指定や、労働者の人数と稼働時間による報酬・料金の計算が適法になり得ます。
適法な人数の指定・人数にもとづく報酬・料金の計算となり得る条件
- 請負・委任・準委任の業務が「仕事を完成させ目的物を引き渡す」形態ではないこと。
- 「請負事業主が自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用」していること。
- 請負事業主が「契約の相手方から独立して業務を処理していること」。
この他、委託者による受託者の労働者の人数の指定に関する違法性・適法性につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
準委任契約における時間精算の報酬に関するよくある質問
- 準委任契約で時間精算の報酬は違法ですか?
- 準委任契約で時間精算の報酬としたとしても、原則として違法にはなりません。
- 準委任契約において、例外として違法となる時間精算の報酬は、どのような場合でしょうか?
- 個人事業者・フリーランスが受託者になる準委任契約では、以下の場合は、適法な準委任契約ではなく、労働契約・雇用契約(偽装請負)とみなされ、労働基準法、労働契約法などの各種労働法に違反する可能性があります。
- 1.「使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることに対する対価」としての時間精算の報酬
- 2.「報酬について給与所得としての源泉徴収を行っている」場合における時間精算の報酬
- 3.委託者の「同様の業務に従事している正規従業員に比して著しく高額」でない場合おける時間精算の報酬