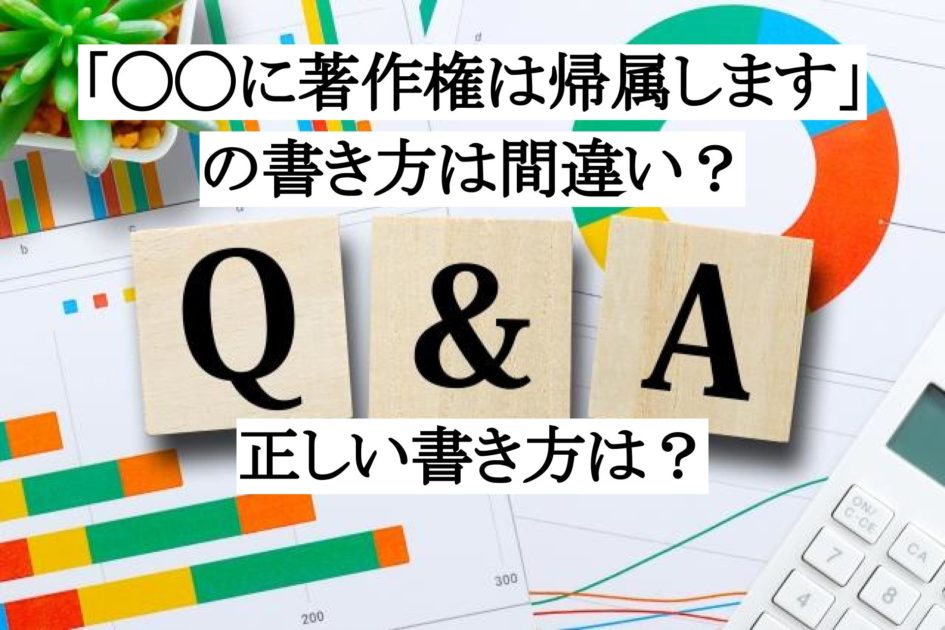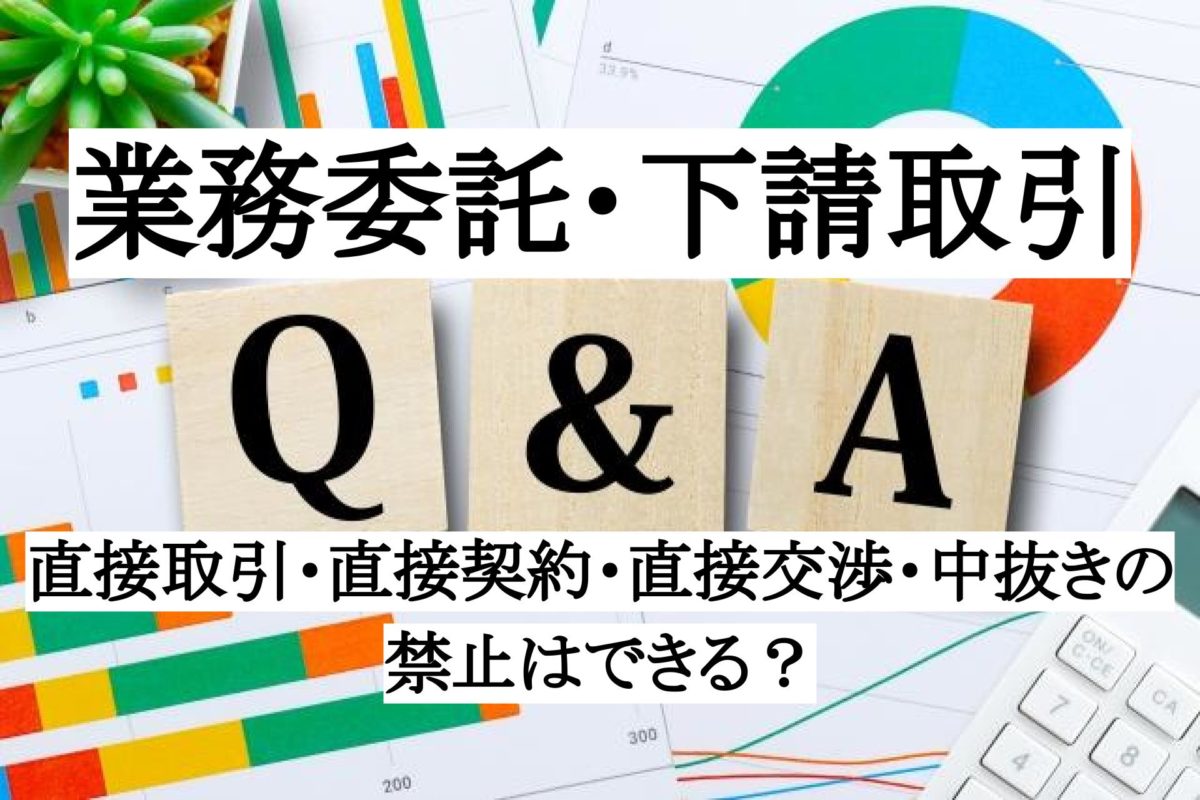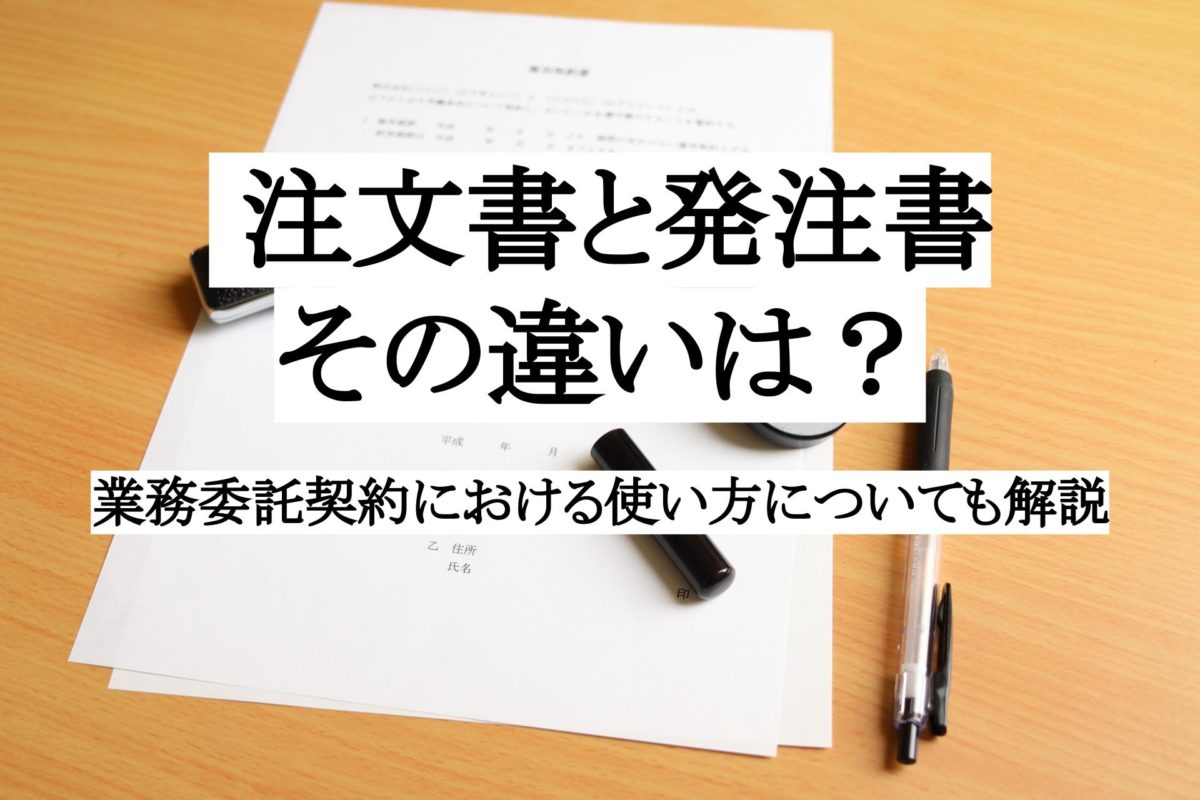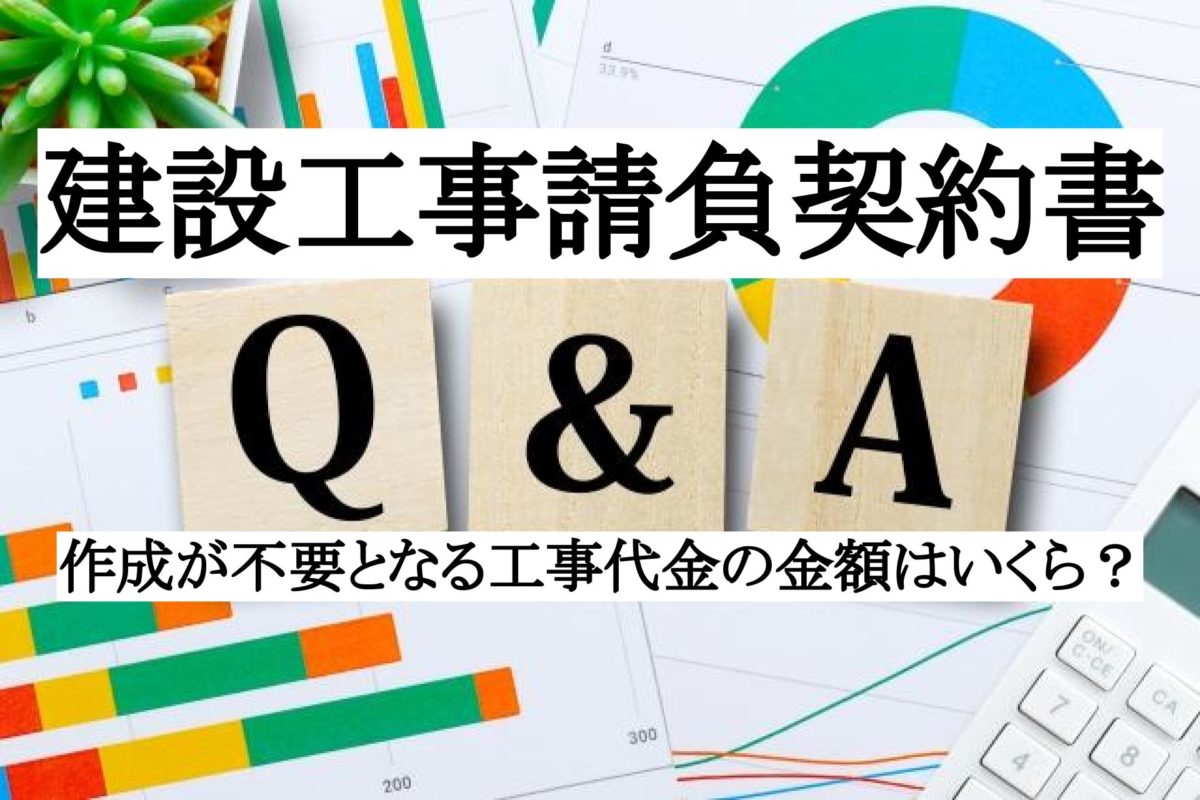
- 建設業法では建設工事請負契約書の作成が義務づけられていますが、工事代金がいくらであれば、契約書の作成が不要になるのでしょうか?
- 建設業法が適用される場合、工事代金の金額に関係なくあらゆる建設工事請負契約書の作成が義務づけられています。このため、たとえ工事代金が0円であったとしても、建設工事請負契約書の作成は必要となります。
このページでは、建設工事請負契約の当事者、特に建設業の事業者向けに、建設工事請負契約書の作成義務について解説しています。
建設工事請負契約では、建設業法第19条により、建設工事請負契約書の作成が義務づけられています。
この点について、「工事代金の金額が少なければ契約書の作成は不要である」という考え方がありますが、これは誤解です。
建設工事請負契約では、工事代金の金額に関係なく契約書を作成する義務があります。
このページでは、こうした建設工事請負契約書の作成義務と工事代金の関係について、開業20年・400社以上の取引実績がある管理人が、わかりやすく解説していきます。
このページでわかること
- 施工代金の金額に関係なく建設工事請負契約書の作成が不要にならない理由。
- 下請法にもとづき建設業務委託契約書の作成が必要となる条件。
- フリーランス保護法にもとづき建設業務委託契約書の作成が必要となる条件。
建設工事請負契約書は工事代金が少なくても作成が不要にはならない
建設工事請負契約書は金額に関係なく作成が必要
結論から言えば、建設業法が適用される建設工事請負契約では、工事代金の金額に関係なく、契約書の作成は必須となり、不要にはなりません。
建設工事請負契約書の作成義務を規定している条項は、建設業法第19条です。
この建設業法第19条や、関連する条項において、請負代金や工事代金が少額の場合に建設工事請負契約書の作成を不要とする規定はありません。
このため、どんなに少額の請負代金・工事代金であったとしても、建設工事請負契約の当事者は、建設工事請負契約書を作成しなければなりません。
なお、建設工事請負契約書につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
工事代金が関係するのはあくまで建設業の許可
よく誤解されがちですが、「施工代金が500万円未満の建設工事では業務委託契約書・建設工事請負契約書を作成しなくてもいい」と考えられることがあります。
この「施工代金が500万円」というのは、あくまで建設業の許可が必要な工事のひとつの基準に過ぎません。
このため、どんなに請負金額・施工代金が少ない建設工事であっても、建設工事請負契約書を作成する義務があります。
なお、建設業法第19条第1項の主語が「建設工事の請負契約の当事者」となっていることから、建設業の許可の有無に関係なく、建設工事請負契約書の作成は必須となります。
例外:請負契約でなければ契約書の作成が不要となる
建設業法はあくまで「請負契約」に適用される法律
なお、建設工事を対象とした契約であっても、請負契約でない場合、つまり工事の完成を目的としていない契約の場合は建設業法は適用されません。
【意味・定義】請負契約とは?
請負契約とは、請負人(受託者)が仕事の完成を約束し、注文者(委託者)が、その仕事の対価として、報酬を支払うことを約束する契約をいう。
具体的には、工事の完成を目的とせず、建設工事の一部の作業を委託する場合、つまり準委任契約の場合は建設業法は適用されません。
【意味・定義】準委任契約とは?
準委任契約とは、委任者が、受任者に対し、法律行為でない事務をすることを委託し、受任者がこれ受託する契約をいう。
このため、建設業者の間の再委託の取引や、いわゆる一人親方に対する建設業務委託契約などにおいて、契約形態が準委任契約である場合は、建設業法第19条は適用されないため、建設業法にもとづく建設工事請負契約書の作成は不要となります。
ただし、この場合は、下請法やフリーランス保護法にもとづき、いわゆる「三条書面」の作成義務が発生する可能性もあります(後述)。
「建設工事の完成を目的として締結する契約」は請負契約扱い
ただし、建設業法第24条により、「委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約」は、建設工事請負契約とみなされます。
建設業法第24条(請負契約とみなす場合)
委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
引用元:建設業法 | e-Gov法令検索
このように、「建設工事の完成を目的」とした場合は、たとえ契約書のタイトルが「建設業務委託契約」や「建設工事業務委託契約」だったとしても、建設業法が適用されます。
補足1:建設業法が適用されない場合は下請法が適用される可能性もある
下請法が適用される場合は三条書面の作成義務が発生する
以上のとおり、建設業法が適用されない場合は、少なくとも建設業法にもとづく契約書の作成は不要となります。
しかし、この場合は、下請法にもとづく、いわゆる「三条書面」の作成が必要になる可能性が出てきます。
【意味・定義】三条書面(下請法)とは?
三条書面(下請法)とは、下請代金支払遅延等防止法(下請法)第3条に規定された、親事業者が下請事業者対し交付しなければならない書面をいう。
準委任契約である建設業務委託契約は下請法の規制対象
下請法や建設業法に詳しい方であれば、「建設工事には下請法が適用されない」と思われるはずです。
ただ、下請法において、建設工事について除外されている「役務提供委託」の規定には、以下のとおり記載されています。
下請法第2条(定義)
(途中省略)
4 この法律で「役務提供委託」とは、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること(建設業(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第2項に規定する建設業をいう。以下この項において同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(同条第2項に規定する建設工事をいう。)の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く。)をいう。
(以下省略)
このように、あくまで下請法の適用除外とされているのは、「請け負う建設工事」とされています。
このため、請負契約以外の準委任契約等の建設工事に関する契約の場合は、下請法が適用除外にならずに適用対象となります。
下請法の対象となる建設業務委託契約とは?
下請法の規制対象となる建設業務委託契約は、一般的には、次の条件を満たしたものとなります。
下請法の規制対象となる建設業務委託契約
- 契約形態が準委任契約等の請負契約以外のものであること。
- 建設業を営む者(建設業の許可を受けた建設業者に限らず、建設業の許可を受けていない者も含む)から他の建設業者への再委託であること。
- 委託者の資本金が5千万1円以上であり、受託者の資本金が5千万円以下(または個人事業者)であること、または委託者の資本金が1千万1円以上5千万円以下であり、受託者の資本金が1千万円以下(または個人事業者)であること。
この他、下請法の適用対象かどうかにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
三条書面を交付しないと最大で50万円の罰金が個人単位にも科される
なお、親事業者が下請業者に対し三条書面を交付しない場合は、50万円以下の罰金が科されます。
下請法第10条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、50万円以下の罰金に処する。
(1)(省略)
(2)第5条の規定による書類若しくは電磁的記録を作成せず、若しくは保存せず、又は虚偽の書類若しくは電磁的記録を作成したとき。
ポイントは、親事業者である法人だけに罰金が科されるのではなく、「その違反行為をした親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者」にも罰金が科される、ということです。
つまり、会社で50万円を払えばいい、というものではないのです。しかも、50万円とはいえ、いわゆる「前科」がつきます。
なお、親事業者である法人にも、罰金は科されます。
下請法第12条(罰則)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
補足2:一人親方との契約はフリーランス保護法による書面交付等の義務がある
フリーランス保護法が適用される場合は契約条件の書面交付等の義務が発生する
下請法が適用されない場合であっても、2024年秋頃に施行予定のフリーランス保護法が適用されるときは、契約条件の明示義務が発生します。
【意味・定義】フリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)とは?
フリーランス保護法とは、正式には特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律といい、委託者である事業者に対し、受託者の給付の内容その他の事項(契約内容)の明示を義務づけるなど、受託者を保護することを目的とした法律をいう。
フリーランス保護法第3条(書面の交付等)
1 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。
2 業務委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。
フリーランス保護法は、下請法とは異なり契約形態が請負契約であっても適用されます。
フリーランス保護法の対象となる建設業務委託契約とは?
フリーランス保護法の規制対象となる建設工事請負契約・建設業務委託契約は、次の条件を満たしたものとなります。
フリーランス保護法の規制対象となる建設工事に関する契約
- 受託者が特定受託事業者(従業員がいない個人事業者、または従業員がおらず、かつ役員が代表者一人の法人(いわゆる一人親方))であること。
- 委託者が業務委託事業者(特定受託事業者に業務委託をする事業者)であること。
このため、委託者が事業者(個人事業者やフリーランスであっても)であれば、一人親方に対して建設工事請負契約や建設業務委託契約を発注する場合は、書面等の交付により、契約条件を明示しなければなりません。
フリーランス保護法第3条違反は勧告・命令・罰則の対象
フリーランス保護法第3条に違反した場合、下請法第3条とは異なり、直ちに罰則は課されませんが、勧告・命令の対象となります。
フリーランス保護法第8条(勧告)
1 公正取引委員会は、業務委託事業者が第3条の規定に違反したと認めるときは、当該業務委託事業者に対し、速やかに同条第1項の規定による明示又は同条第2項の規定による書面の交付をすべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(以下省略)
フリーランス保護法第9条(命令)
1 公正取引委員会は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2 公正取引委員会は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公表することができる。
なお、命令があった場合は、罰則こそありませんが、フリーランス保護法第9条第2項にもとづく公表の対象となります。
この命令に違反した場合は、金50万円の罰金が科されます。
フリーランス保護法第24条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
(1)第9条第1項又は第19条第1項の規定による命令に違反したとき。
(2)第11条第1項若しくは第2項又は第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
フリーランス保護法第25条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
ポイントは、業務委託事業者である法人に限らず、「代理人、使用人その他の従業者」に対しても罰金が科される、ということです。
つまり、会社で50万円を払えばいい、というものではないのです。しかも、50万円とはいえ、いわゆる「前科」がつきます。
補足3:消費者との契約は特定商取引法による書面交付等の義務がある
訪問販売・電話勧誘販売とは?
一般消費者が相手方となる建設工事では、勧誘のしかたによっては、特定商取引法が適用されます。
具体的には、訪問販売、電話勧誘販売など、一部の勧誘方法による、建設業者と消費者との建設工事請負契約(例:リフォーム契約)が該当します。
【意味・定義】訪問販売とは?
訪問販売とは、特定商取引法第2条第1項に規定する販売方法であって、事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売または役務の提供をおこなう契約をする取引をいい、キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。
【意味・定義】電話勧誘販売とは?
電話勧誘販売とは、特定商取引法第2項第3項に規定する販売方法であって、事業者が消費者を電話で勧誘し、申込みを受ける取引をいい、電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みをおこなう場合も含む。
特定商取引法が適用される場合は法定書面の交付義務がある
建設工事の勧誘方法が訪問販売や電話勧誘販売である場合、建設業者は、消費者に対し、契約の申込みを受けたときまたは契約を締結したときは、法定書面を交付しなければなりません。
この法定書面には、以下の内容を記載しなければなりません。
特定商取引法で交付を義務づけられた法定書面の内容
- 商品・権利・役務の種類
- 販売価格・役務の対価
- 代金・対価の支払時期
- 代金・対価の支払方法
- 商品の引渡時期・権利の移転時期・役務の提供時期
- 契約の申込みの撤回・契約の解除に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む。)
- 事業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 契約の申込みまたは締結を担当した者の氏名
- 契約の申込みまたは締結の年月日
- 商品名および商品の商標または製造業者名
- 商品の型式
- 商品の数量
- 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
- そのほか特約があるときには、その内容
また、これらの書面には、次の記載も必要となります。
特定商取引法で交付を義務づけられた法定書面の記載方法
- 注意事項として、赤枠内に赤字でこの書面をよく読むべきことを記載すること。
- クーリングオフに関する事項を赤枠内に赤字で記載すること。
- 文字の大きさを日本工業規格で8ポイント以上とすること。
法定書面の不交付・不十分な法定書面の交付は特定商取引法違反となる
訪問販売や電話勧誘販売など、特定商取引法が適用される場合において、建設業者が消費者に対し法定書面を交付しないときは、特定商取引法違反となり、業務停止命令等の行政処分の対象や、罰則の対象となります。
また、法定書面を交付した場合であっても、その内容が不十分であったり、虚偽の内容であったりした場合も、同様です。
以上のとおり、特定商取引法の規制対象となる場合における契約書なしの建設工事は、違法行為となります。
法定書面の不交付・不十分な法定書面の交付は無期限のクーリングオフの対象となる
なお、訪問販売や電話勧誘販売は、適法な法定書面を交付した場合もクーリングオフ制度の対象となります。
この場合、消費者が法定書面を受け取った日から起算して8日後までは、消費者は、書面または電磁的方法により契約の申込みの撤回や契約解除ができます。
この点について、建設業者が法定書面を交付しなかった場合や、不十分な法定書面・虚偽の内容の法定書面を交付した場合は、そもそも適法な法定書面を交付したことにはなりません。
よって、適法な法定書面の交付がなされてから8日後を経過するまでの間は、無期限でクーリングオフの対象となります。
建設工事における特定商取引法の法定書面は契約書とする
このように、特に建設業者にとっては、特定商取引法が適用される建設工事請負契約は、一定のリスクがあります。
また、たとえ適法な法定書面を作成し、消費者に対し交付したとしても、「交付した証拠」が残っていないと、後日、トラブルとなる可能性もあります。
こうしたトラブルを予防するため、建設工事における特定商取引法の法定書面は、契約書の形式にして、建設業者の側にも、契約書の原本が残るようにします。
こうすることで、特定商取引法の法定書面を交付した証拠を残しつつ、建設業法第19条も遵守することができます。
建設工事請負契約書の作成義務と施工代金の金額に関するよくある質問
- 建設業法では建設工事請負契約書の作成が義務づけられていますが、工事代金がいくらであれば、契約書の作成が不要になりますか?
- 建設業法が適用される場合、工事代金の金額に関係なく、建設工事請負契約書の作成が義務づけられています。
- 建設工事に関する契約で、契約書の作成が不要となるものはありますか?
- 契約形態が請負契約でない場合、建設業法は適用されませんので、建設業法にもとづく契約書の作成義務は発生しません。ただし、下請法やフリーランス保護法により、契約書の作成が必要となり場合もあります。
まとめ:契約書が必要な建設工事・契約書が不要な建設工事とは?
以上をまとめると、契約書が必要な建設工事に関する契約は、以下のとおりです(カッコ内は根拠法令)。
契約書が必要な建設工事に関する契約
- 契約形態が請負契約の建設工事に関する契約(建設業法)
- 一般消費者が委託者となる場合において、訪問販売・電話勧誘販売による建設工事に関する契約(特定商取引法)
- 契約形態が請負契約でない(=準委任契約である)建設工事に関する契約であって、委託者と受託者の資本金に大きな差がある場合におけるもの(下請法)
- 受託者がフリーランス・個人事業者(一人親方を含む)や一人法人の場合における建設工事に関する契約(フリーランス保護法。ただし、2024年秋頃までに施行予定)
逆に、現行法において契約書が不要な建設工事に関する契約は、以下のすべての条件を満たした場合となります。
契約書が不要な建設工事に関する契約
- 事業者間の建設工事に関する契約(建設業務委託契約)であること。
- 契約形態が請負契約でない(=準委任契約である)建設工事に関する契約(建設業務委託契約)であること。
- 委託者と受託者の資本金に大きな差がない場合(下請法の適用対象外である場合)における建設工事に関する契約(建設業務委託契約)であること。
なお、これらの条件をすべて満たしたとしても、2024年秋頃に施行されるフリーランス保護法により、受託者がフリーランス・個人事業者(一人親方を含む)や一人法人の場合は、契約書が必要となります。
建設工事請負契約書の作成は弊所におまかせください
このように、建設工事請負契約書は、請負代金・施工代金の金額に関係なく、作成義務があります。
また、特に特定商取引法が適用される建設工事請負契約書は、作成しないことによるペナルティが非常に強いです。
弊所では、こうした法規制の対象となる建設工事請負契約書・建設業務委託契約書の作成依頼を承っております。
適法な建設工事請負契約・建設業務委託契約とし、建設業法、下請法、特定商取引法に違反しないよう配慮した契約書を作成いたしております。
お見積りは完全無料となっていますので、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。