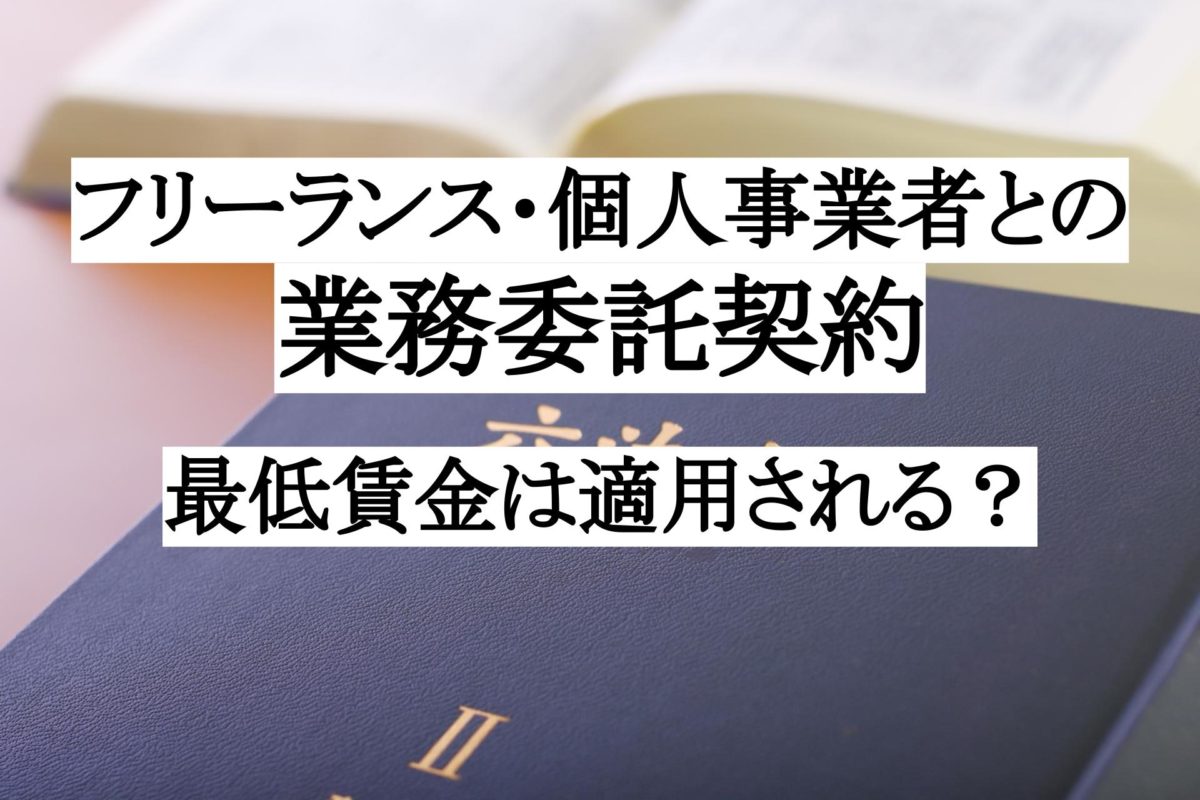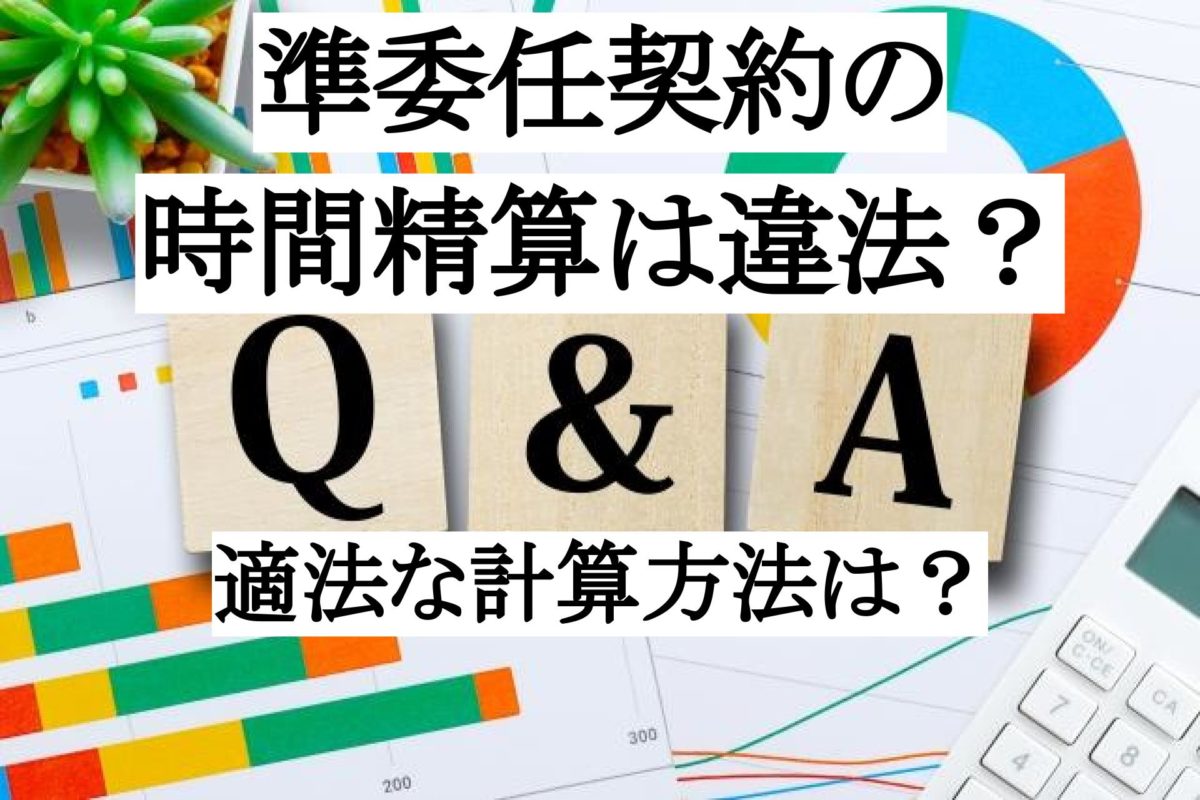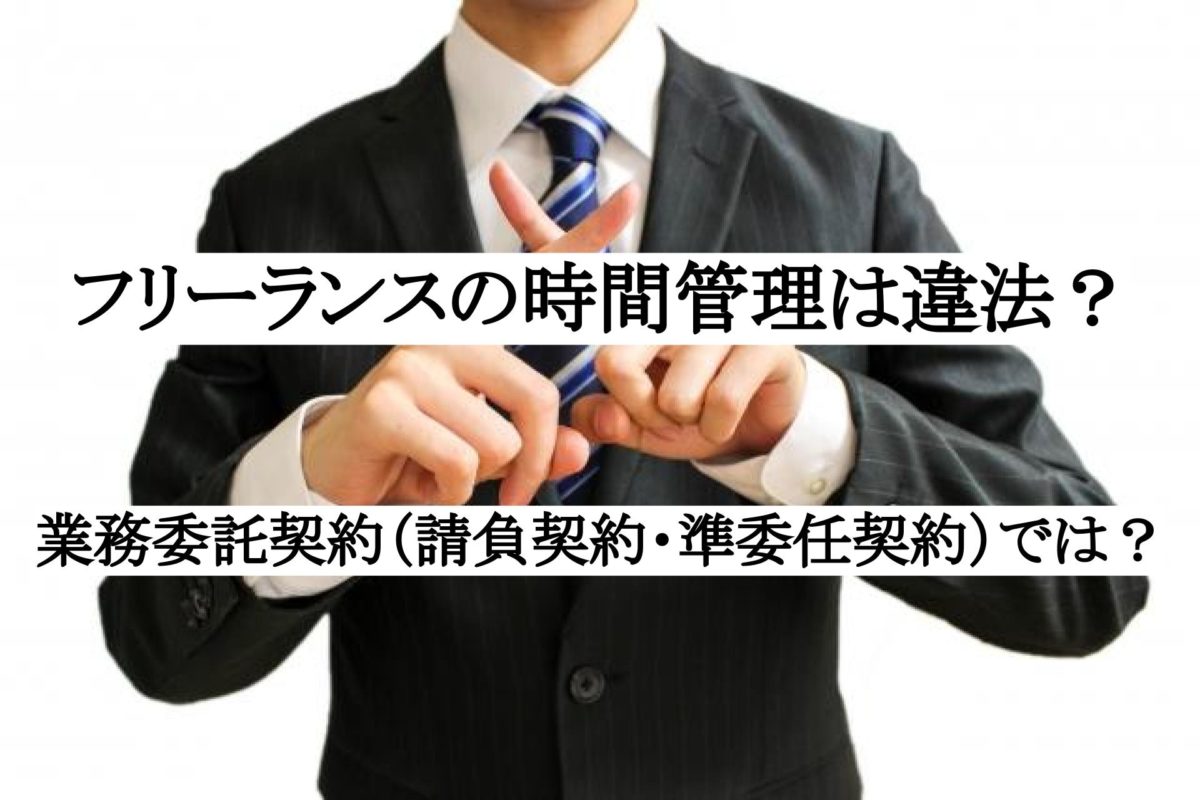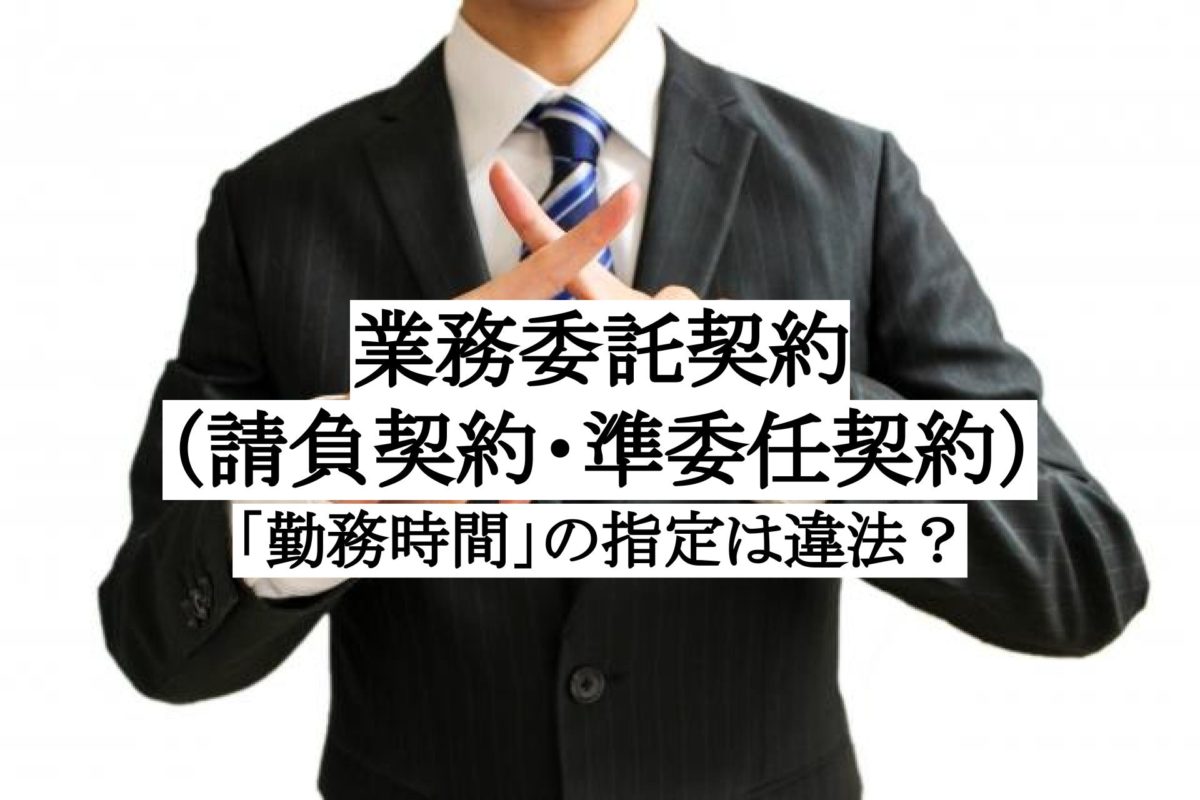『労働基準法研究会報告』は、旧労働省(現:厚生労働省)の労働基準法研究会によっておこなわれた、労働基準法第9条の「労働者」の定義と、その判定基準を研究した結果について報告した報告書です。
『労働基準法研究会報告』は、業務委託契約書を作成する際に、業務委託契約と雇用契約・労働契約との違いの基準となります。
このため、特に個人事業者・フリーランスが受託者となる業務委託契約の場合、この『労働基準法研究会報告』に準拠した業務委託契約書を作成することが重要となります。
『労働基準法研究会報告』(労働基準法の「労働者」の判断基準について)(昭和60年12月19日)とは?
『労働基準法研究会報告』は労働者の判断基準を提示した報告
『労働基準法研究会報告』(労働基準法の「労働者」の判断基準について)(昭和60年12月19日)は、厚生労働省の前身である、旧労働省に設置された、「労働基準法研究会」という研究会が出した報告のひとつです。
内容は、カッコ書きにあるとおり、「労働基準法」の「労働者」の判定基準を示したものです。
【意味・定義】昭和60年労働基準法研究会報告とは?
昭和60年労働基準法研究会報告とは、旧労働省(現:厚生労働省)の労働基準法研究会によっておこなわれた、労働基準法第9条の「労働者」の定義と、その判定基準をいう。
なお、同様の報告として、『労働者性検討専門部会報告』があります。
これは、旧労働省の労働基準法研究報告会労働契約等法制部会が、建設業の個人事業者(いわゆる「一人親方」)や芸能関係者の労働者性の判断基準についてまとめた報告です。
労働組合法の「労働者」の判断基準も別にある
実は、労働組合法の「労働者」の判断基準を示したものも、別に存在します。
参照:労使関係法研究会報告書(労働組合法上の労働者性の判断基準について)平成23年7月 労使関係法研究会
同じ「労働者」という表現でも、労働基準法の「労働者」と労働組合法の「労働者」は、必ずしも一致しませんので、ご注意ください。
このページでは、特に業務委託契約との関係で問題になる、「労働基準法」の「労働者」の判断基準である、『労働基準法研究会報告』のほうを取り上げて解説します。
労働基準法の「労働者」の判断基準は「使用従属性」と「労働者性の判断を補強する要素」の2つ
【意味・定義】労働基準法における「労働者」と「使用従属性」とは?
まず、労働基準法における労働者の定義を確認しましょう。
労働基準法第9条(定義)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
【意味・定義】労働者(労働基準法)とは?
労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう(労働基準法第9条)。
『労働基準法研究会報告』では、この「使用される」という点と、「賃金を支払われる」という点の2つの基準を総称して、「使用従属性」と呼んでいます。
【意味・定義】使用従属性とは?
- 使用される=指揮監督下の労働であること
- 賃金を支払われること
「使用従属性」だけでは労働者と判断するのは難しい
このように、労働基準法での労働者の定義では、「使用される」という点と、「賃金を支払われる」という点の2つが、要件となっています。
このように、労働基準法上の要件は、たった2点で、しかも内容が曖昧です。
このため、実際の企業活動の現場では、労働基準法の労働者に該当するかどうかを判断するのは困難です。
このような事情から、学説や判例の判断基準を参考に、当時の労働省が監督行政の判断基準とするために、より労働者の判断基準を明確にしたものが、『労働基準法研究会報告』です。
「労働者性の判断を補強する要素」とは
「労働者性の判断を補強する要素」とは、「使用従属性に関する判断基準」だけで労働者性の判断が難しい場合に、さらに追加で勘案する要素のことです。
すでに述べたとおり、「使用される」「賃金を支払われる」という2点=「使用従属性」だけでは、労働者かどうか、言い換えれば、他の契約形態(請負契約・(準)委任契約などの業務委託契約)の個人事業者・フリーランスとは区別が難しい場合があります。
このため、使用従属性だけで労働者性の判断が難しい場合は、「労働者性の判断を補強する要素」をも総合的に勘案して、労働者かどうかを判断します。
つまり、まずは「使用従属性に関する判断基準」で判断して、それでも労働者かそうでないか判断がつかない場合は、「労働者性の判断を補強する要素」を勘案して、労働者かどうかを総合的に判断します。
ポイント
- 「使用従属性に関する判断基準」→「労働者性の判断を補強する要素」の順に判断される。
- 「使用従属性に関する判断基準」だけで労働者である、または労働者でないと判断された場合は、「労働者性」については判断されない。
- 「使用従属性に関する判断基準」だけでは判断がつかない場合は、「労働者性の判断を補強する要素」が勘案され、労働者かどうかが総合的に判断される。
「使用従属性の判断基準」と「労働者性の判断を補強する要素」の概略
では、実際に個別の判断基準の前に、「使用従属性の判断基準」と「労働者性の判断を補強する要素」の概略を見てみましょう。
「使用従属性に関する判断基準」と「労働者性の判断を補強する要素」
1 「使用従属性」に関する判断基準
(1)「指揮監督下の労働」に関する判断基準
イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
ロ 業務遂行上の指揮監督の有無
(イ)業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
(ロ)その他
ハ 拘束性の有無
ニ 代替性の有無 -指揮監督関係の判断を補強する要素-
(2)報酬の労務対償性に関する判断基準
2 「労働者性」の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
イ 機械、器具の負担関係
ロ 報酬の額
ハ その他
(2)専属性の程度
イ 他社の業務への従事の制約の強さ、困難さ
ロ 報酬の生活保障的な要素の強さ
(3)その他
1「使用従属性」に関する判断基準
(1)「指揮監督下の労働」に関する判断基準
イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
諾否の自由の有無
- 「使用者」の具体的な仕事の依頼、業務従事の指示等に対して諾否の自由有り→対等な当事者間の関係=指揮監督関係を否定する重要な要素
- 「使用者」の具体的な仕事の依頼、業務従事の指示等に対して拒否する自由無し→指揮監督関係を推認させる重要な要素
包括的契約・専属下請の例外
- 一定の包括的な仕事の依頼を受諾した以上、当該包括的な仕事の一部である個々具体的な仕事の依頼については拒否する自由が当然制限される場合
- 専属下請のように事実上、仕事の依頼を拒否することができないという場合
このような場合には、直ちに指揮監督関係を肯定することはできず、その事実関係だけでなく、契約内容等も勘案する必要がある。
ロ 業務遂行上の指揮監督の有無
(イ)業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
指揮命令の有無
- 業務の内容及び遂行方法について「使用者」の具体的な指揮命令を受けていることは、指揮監督関係の基本的かつ重要な要素
- 通常注文者が行う程度の指示等に止まる場合には、指揮監督を受けているとは言えない
(ロ)その他
予定外の業務の有無
「使用者」の命令、依頼等により通常予定されている業務以外の業務に従事することがある場合には、「使用者」の一般的な指揮監督を受けているとの判断を補強する重要な要素となろう。
ハ 拘束性の有無
拘束性の有無
- 勤務場所及び勤務時間が指定され、管理されていることは、一般的には、指揮監督関係の基本的な要素
- 業務の性質上(例えば、演奏)、安全を確保する必要上(例えば、建設)等から必然的に勤務場所及び勤務時間が指定される場合は、(指揮命令する必要によるものではなく)業務の性質等によるもの
ニ 代替性の有無 -指揮監督関係の判断を補強する要素-
代替性の有無
- 本人に代わって他の者が労務を提供することが認められているか否か
- 本人が自らの判断によって補助者を使うことが認められているか否か
等労務提供に代替性が認められているか否かは、指揮監督関係そのものに関する基本的な判断基準ではないが、労務提供の代替性が認められている場合には、指揮監督関係を否定する要素のひとつとなる。
(2)報酬の労務対償性に関する判断基準
報酬の計算
- 報酬が時間給を基礎として計算される等労働の結果による較差が少ない
- 欠勤した場合には応分の報酬が控除され
- いわゆる残業をした場合には通常の報酬とは別の手当が支給される
等報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることに対する対価と判断される場合には、「使用従属性」を補強することとなる。
2「労働者性」の判断を補強する要素
すでに述べたとおり、「労働者性の判断を補強する要素」で労働者性が判断されるのは、あくまで「使用従属性の判断基準」だけでは、労働者かどうかの判断がつかない場合です。
(1)事業者性の有無
生産手段等の有無
- 労働者は、機械、器具、原材料等の生産手段を有しないのが通例
- いわゆる傭車運転手のように、相当高価なトラック等を所有して労務を提供するような事例については、前記 1 の基準のみをもって「労働者性」を判断することが適当でなく、その者の「事業者性」の有無を併せて、総合判断することが適当
イ 機械、器具の負担関係
機械・器具の所有
- 本人が所有する機械、器具が安価な場合には問題はない
- 本人が所有する機械、器具が著しく高価な場合には自らの計算と危険負担に基づいて事業経営を行う「事業者」としての性格が強く、「労働者性」を弱める要素となる
ロ 報酬の額
高額な報酬
報酬の額が当該企業において同様の業務に従事している正規従業員に比して著しく高額である場合…、「労働者性」を弱める要素となる
ハ その他
損害賠償責任・商号の使用
- 業務遂行上の損害に対する責任を負う
- 独自の商号使用が認められている
等の点を「事業者」としての性格を補強する要素としている判例がある。
(2)専属性の程度
専属性の有無
- 特定の企業に対する専属性の有無は、直接に「使用従属性」の有無を左右するものではない
- 特に専属性がないことをもって労働者性を弱めることとはならない
- 「労働者性」の有無に関する判断を補強する要素のひとつ
専属性の有無は「使用従属性」の判断基準にはならないものの、「労働者性」の有無に関する判断を補強する要素のひとつとなります。
つまり、専属性の有無は、「使用従属性」の判断の段階では直接考慮されない要素ですが、使用従属性では労働者性の判断がつかなかった場合には、「労働者性の判断を補強する要素」となります。
イ 他社の業務への従事の制約の強さ、困難さ
他社の業務への従事
- 他社の業務に従事することが制度上制約される場合
- 他社の業務に従事する時間的余裕がなく事実上困難である場合
―には、専属性の程度が高く、いわゆる経済的に当該企業に従属していると考えられ、「労働者性」を補強する要素のひとつとなる。
ロ 報酬の生活保障的な要素の強さ
固定報酬
- 報酬に固定給部分がある
- 業務の配分等により事実上固定給となっている
- その額も生計を維持しうる程度のもの
―である等報酬に生活保障的な要素が強いと認められる場合には、「労働者性」を補強する。
(3)その他
その他の判例での判断基準
- 採用、委託等の際の選考過程が正規従業員の採用の場合とほとんど同様であること
- 報酬について給与所得としての源泉徴収を行っていること
- 労働保険の適用対象としていること
- 服務規律を適用していること
- 退職金制度、福利厚生を適用していること
―等「使用者」がその者を自らの労働者と認識していると推認される点を、「労働者性」を肯定する判断の補強事由とする判例がある。
雇用契約・労働契約とみなされない業務委託契約のチェックポイント
以上の点から、業務委託契約書を作成する際に、雇用契約・労働契約とみなされないようにするには、以下の点に注意します。
偽装請負(労働基準法違反)とならないチェックリスト
「使用従属性」に関する判断基準のチェックリスト
- 1.受託者が委託者の「指揮監督下の労働」を提供していない
- 1-1.受託者に「仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由」がある
- 1-2-1.委託者による「業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令」がない
- 1-3-2.予定外の業務がない
- 1-2.委託者による業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令がない
- 1-3.拘束性がない
- 1-4.代替性がある(受託者が再委託できる)
- 1-1.受託者に「仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由」がある
- 2.報酬に労務対償性がある
- 2-1.報酬が「労働の結果による」計算となっている
- 2-2.欠勤した場合であっても「応分の報酬が控除」されない
- 2-3.残業をした場合であっても「通常の報酬とは別の手当が支給」されない
「労働者性」の判断を補強する要素のチェックリスト
- 3.事業者性の有無
- 3-1.受託者が機械・器具の所有している
- 3-2.高額な報酬である
- 3-3.その他
- 3-3-1.受託者が損害賠償責任を負う
- 3-3-2.受託者による独自の商号使用が認められている
- 4.専属性の程度
- 4-1.他社の業務に従事することが制度上制約されいない
- 4-2.他社の業務に従事する時間的余裕がある
- 4-3.報酬に固定給部分がない
- 4-4.「業務の配分等により事実上固定給」となっていない
- 4-5.報酬の額が「生計を維持しうる程度のもの」ものでない
- 5.その他
- 5-1.「採用、委託等の際の選考過程が正規従業員の採用の場合とほとんど同様」ではない
- 5-2.報酬について、「給与所得」としては源泉徴収をおこなっていない
- 5-3.労働保険の適用対象としていない
- 5-4.服務規律を適用していない
- 5-5.退職金制度、福利厚生を適用していない
こうした要素が反映された業務委託契約書を作成するとともに、取引きの実態としても、雇用契約・労働契約ではない状態にします。
こうすることで、業務委託契約が、雇用契約・労働契約とみなされなくなります。
なお、業務委託契約と雇用契約・労働契約の違いにつきましては、以下のページも併せてご覧ください。