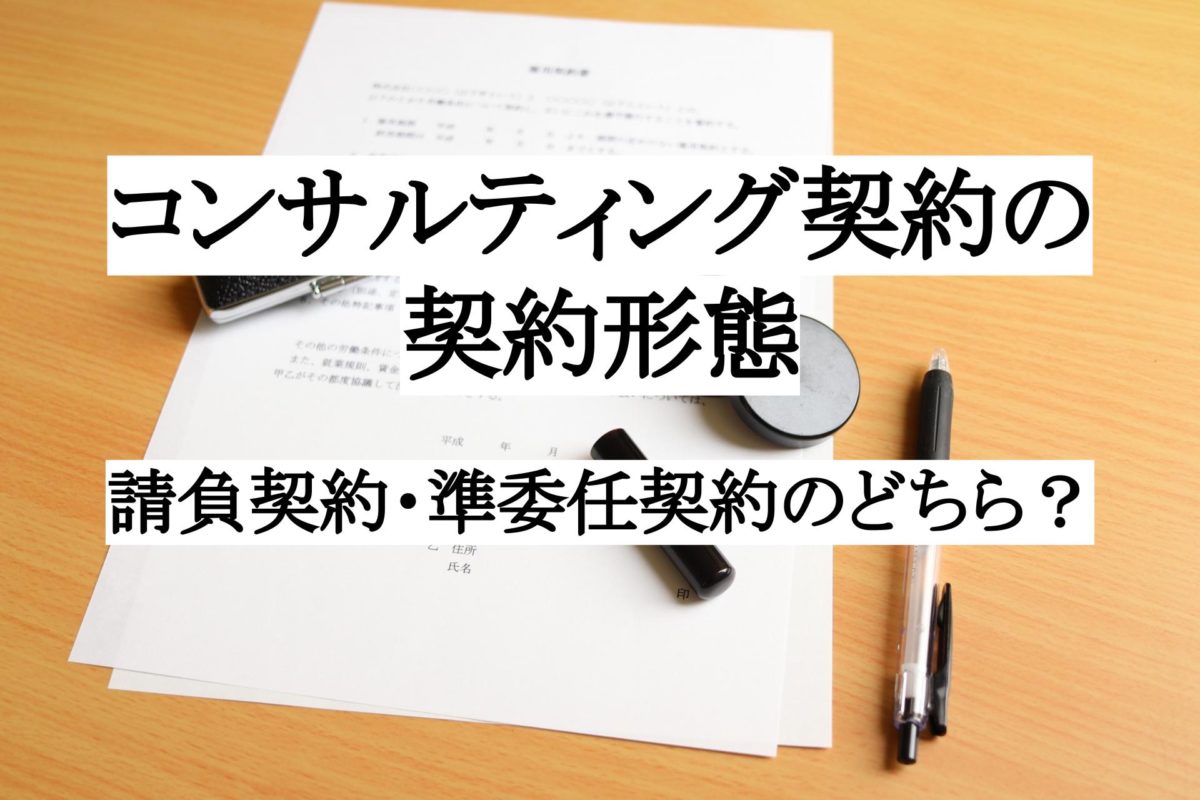建設工事請負契約は、建設業者である請負人(受託者)が、建設工事の施工を請負い、注文者(委託者)が、その対価として、報酬・料金・委託料を支払う契約のことです。
建設工事の定義については、建設業法で厳密に規定されています。
このため、意外と多くの工事が、建設業法上の建設工事に該当します。
このページでは、こうした建設工事請負契約の定義や建設業法による規制等について、解説します。
なお、請負契約の基本的な解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
建設工事請負契約とは?
【意味・定義】建設工事とは?
建設工事請負契約は、特に民法や建設業法では定義がありませんが、一般的には、注文者(委託者)と請負人(受託者)との間で締結される、建設工事の施工に関する請負契約です。
ここでいう「建設工事」は、建設業法に明確に定義づけられていて、29種類あります。
建設業法第2条(定義)
1 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
(以下省略)
引用元:建設業法 | e-Gov法令検索
【意味・定義】建設工事とは?
建設工事とは、土木建築に関する工事のうち、建設業法別表第一の上欄に掲げるものをいう。
このように、およそ「工事」と名前がつくものは、建設業法では建設工事に該当します。
これらの詳細につきましては、国土交通省が定める「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」をご覧ください。
【意味・定義】建設工事請負契約とは?
請負契約は、民法では、以下のように規定されています。
民法第632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
従って、建設工事請負契約の定義は、次のとおりです。
【意味・定義】建設工事請負契約とは?
建設工事請負契約とは、請負人(受託者)が何らかの建設工事を完成させること約束し、注文者(委託者)が、その建設工事の施工の対価として、報酬を支払うことを約束する契約をいう。
なお、建設業法第24条には、以下の規定があります。
建設業法第24条(請負契約とみなす場合)
委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
引用元:建設業法 | e-Gov法令検索
よって、「報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約」は、名義を問わず、建設業法上は請負契約とみなされ、建設業法の規制対象となります。
この他、請負契約につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
建設業法が規定する建設工事請負契約の必須記載事項は?
建設業法第19条で書面作成義務が課されている
建設工事の請負契約を締結する場合、次のとおり、書面の交付が義務づけられています。
建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)
1 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
(1)工事内容
(2)請負代金の額
(3)工事着手の時期及び工事完成の時期
(4)工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
(5)請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
(6)当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
(7)天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
(8)価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
(9)工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
(10)注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
(11)注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
(12)工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
(13)工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
(14)各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(15)契約に関する紛争の解決方法
(16)その他国土交通省令で定める事項
2(以下省略)
引用元:建設業法 | e-Gov法令検索
このように、建設業法では、書面の作成義務に加えて、作成するべき書面の詳細な事項まで規定されています。
建設業法第19条の書面=建設工事請負契約書とする
しかも、単に契約内容を記載した書面を交付すればいいだけではなく、「署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」となっています。
このため、通常は、この建設業法第19条の「書面」として建設工事請負契約書を作成し、同第1項各号に規定された事項をすべてを契約書に記載します。
ちなみに、この規定では、「建設工事の請負契約の当事者は」となっていますので、注文者(委託者)・請負人(受託者)の双方に義務が課されています。
このため、建設工事請負契約書を作成しないと、注文者(委託者)・請負人(受託者)の双方が建設業法違反となります。
建設業法以外でも契約書の作成が義務づけられる可能性もある
なお、建設業法以外の法律でも、契約書なしの建設工事に関する契約は、違法となる可能性が高いです。
具体的には、契約書が必要な建設工事に関する契約は、以下のとおりです(カッコ内は根拠法令)。
契約書が必要な建設工事に関する契約
- 契約形態が請負契約の建設工事に関する契約(建設業法)
- 一般消費者が委託者となる場合において、訪問販売・電話勧誘販売による建設工事に関する契約(特定商取引法)
- 契約形態が請負契約でない(=準委任契約である)建設工事に関する契約であって、委託者と受託者の資本金に大きな差がある場合におけるもの(下請法)
- 受託者がフリーランス・個人事業者(一人親方を含む)や一人法人の場合における建設工事に関する契約(フリーランス保護法。ただし、2024年秋頃までに施行予定)
この他、契約書なしの建設工事に関する契約の違法性につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 建設工事請負契約の当事者は、建設業法第19条により、建設工事請負契約書の作成義務がある。
- 建設業法以外の法律によって、契約書なしの建設工事に関する契約は違法となる可能性もある。
建設工事請負契約の約款=雛形について
建設工事請負契約には、様々な雛形があります。
代表的なものとしては、国土交通省が定めている民間建設工事標準請負契約約款と、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会が定めたものがあります。
参照:建設産業・不動産業:建設工事標準請負契約約款について – 国土交通省
参照:工事請負契約書類 - 民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会
これらは、いずれも大規模な工事や、中規模(個人住宅など)な工事を想定しているものです。
このため、実際の工事の実態や契約内容に合わせて、適宜修正しながら使う必要があります。
ポイント
- 民間建設工事標準請負契約約款・民間(旧四会)民間連合協定工事請負契約約款は、ともに大規模な工事を想定している約款。
建設工事請負契約書の作成義務の誤解
【誤解1】「ウチは建設工事はやってない」
よくありがちですが、建設業法では書面=建設工事請負契約書の作成義務があることを建設業者のお客さまに話すと、次のような言葉が返ってきます。
「いや、ウチでは建設工事はやっていないんですよ」
これは、建設業の許可を取得していない会社のお客さまから、お聞きすることが多いです。
こうしたお客さまからお話を伺うと、「建設工事」のことを、大規模な建物の建築工事や土木工事のことをイメージしていることが多いです。
しかし、すでに触れたように、建設業法では、29種類の建設工事が定義づけられています。
建設工事のイメージ
- 【間違ったイメージ】建設工事はゼネコンが施工しているような大規模な建築工事や土木工事
- 【正しいイメージ】建設工事は建設業法第2条第1項・別表第一に規定する29種類の建設工事
建設業法で規定されている29種類に該当する工事は、どんなに小規模であっても、建設業法上は建設工事として扱われます。
【誤解2】「ウチは建設業の許可は取っていない」
建設業の許可がない=小規模な工事=契約書の作成義務はない?
同じく、建設業者のお客さまに建設工事請負契約書の作成義務について話すと、次のような言葉も返ってきます。
「ウチは建設業の許可が必要な工事はやってないんですよ」
これはどういうことかというと、建設工事の中には、建設業の許可が不要なもの(=軽微な工事)もあります。
具体的には、以下のものです。
建設業の許可が不要な軽微な工事
- 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
※「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
こうしたお客さまは、建設工事請負契約書の作成義務があるのは、建設業の許可を受けている建設業者だけだと誤解されています。
建設業法第19条第1項の主語=建設工事の請負契約の当事者
これもありがちな誤解で、建設業法第19条第1項の主語は、次のとおりです。
建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)
1 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
(1)(以下省略)
引用元:建設業法 | e-Gov法令検索
この点について、建設業の許可を受けて建設業を営む者は建設業法では、「建設業者」とされています(建設業法第2条第3項)。
建設業法第19条第1項の主語が、「建設業者」となっておらず、「建設工事の請負契約の当事者」となっているということは、建設業の許可の取得の有無に関係なく、建設工事請負契約書の作成義務がある、ということです。
つまり、建設業の許可を取得していなくても、建設工事請負契約書の作成義務はあります。
建設工事請負契約書の作成義務のイメージ
- 【間違ったイメージ】建設工事請負契約書の作成義務があるのは建設業の許可を受けた建設業者だけ
- 【正しいイメージ】建設工事請負契約書の作成義務があるのは「建設工事の請負契約の当事者」
ポイント
- 一般的な「工事」は、ほとんどが建設業法の「建設工事」に該当する。このため、工事の契約は、建設業法第19条にもとづき、建設工事請負契約書の作成義務がある。
- 許可を受けた建設業者でなくても、建設業法第19条にもとづき、建設工事請負契約書の作成義務がある。
建設工事請負契約書には印紙税が発生し収入印紙が必要?
建設工事請負契約書は2号文書または7号文書
建設工事請負契約書は、金額の記載がある場合は2号文書となり、印紙税が発生します。
また、金額の記載がない建設工事請負契約書で、契約期間が3ヶ月を越えるもの、または契約期間が3ヶ月以内であっても更新の条項があるものは、7号文書となり、印紙税が発生します。
いわゆる取引基本契約書、つまり建設工事請負基本契約書や建設工事請負取引基本契約書などは7号文書に該当する可能性があります。
ちなみに、この取引基本契約書を利用した取引きの場合、個別契約書や注文請書は2号文書となりますが、注文書は原則として非課税文書となります。
建設工事請負契約書における収入印紙・印紙税の扱い
- 金額の記載がある場合:2号文書
- 金額の記載がない場合で、契約期間が3ヶ月を越えるもの:7号文書
- 金額の記載がない場合で、契約期間が3か月以内であっても更新の条項があるもの:7号文書
印紙税の金額は2号文書=工事代金次第、7号文書=4,000円
2号文書の印紙税の金額は、工事代金の金額に応じて、以下の金額となります。
| 2号文書の印紙税の金額(不動産譲渡契約・建設工事請負契約書) | ||
|---|---|---|
| 記載された契約金額 | 印紙税額(1通又は1冊につき) | |
| 不動産譲渡契約書 | 建設工事請負契約 | |
| 1万円未満 | 非課税 | |
| 10万円以下 | 100万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下 | 100万円を超え200万円以下 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 200万円を超え300万円以下 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 5千円 | |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 1万円 | |
| 5千万円を超え1億円以下 | 3万円 | |
| 1億円を超え5億円以下 | 5万円 | |
| 5億円を超え10億円以下 | 16万円 | |
| 10億円を超え50億円以下 | 32万円 | |
| 50億円を超えるもの | 48万円 | |
また、7号文書の印紙税の金額は4,000円となります。
【意味・定義】優越的地位の濫用とは?
優越的地位の濫用とは、「自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が,取引の相手方に対し,その地位を利用して,正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える行為」をいう。
建設工事請負契約の印紙(印紙税・収入印紙)に関する関連ページ
印紙税の節税は電子契約サービスがおすすめ
印紙税の節税には、電子契約サービスの利用がおすすめです。
というのも、電子契約サービスは、他の方法に比べて、デメリットがほとんど無いからです。
印紙税を節税する方法は、さまざまあります。
具体的には、以下のものが考えられます。
印紙税を節税する方法
- コピーを作成する:原本を1部のみ作成し、一方の当事者のみが保有し、他方の当事者はコピーを保有する。
- 契約形態を変更する:節税のために準委任契約のような非課税の契約にする。
- 7号文書を2号文書・1号文書に変更する:取引基本契約に初回の注文書・注文請書や個別契約を綴じ込むことで7号文書から2号文書・1号文書に変える。
しかし、これらの方法には、以下のデメリットがあります。
印紙税の節税のデメリット
- コピーを作成する:契約書のコピーは、原本に比べて証拠能力が低い。
- 契約形態を変更する:節税のために契約形態を変えるのは本末転倒であり、節税の効果以上のデメリットが発生するリスクがある。
- 7号文書を2号文書・1号文書に変更する:7号文書よりも印紙税の金額が減ることはあるものの、結局2号文書・1号文書として課税される。
これに対し、電子契約サービスは、有料ではあるものの、その料金を上回る節税効果があり、上記のようなデメリットがありません。
電子契約サービスのメリット
- 電子契約サービスを利用した場合、双方に証拠として電子署名がなされた契約書のデータが残るため、コピーの契約書よりも証拠能力が高い。
- 電子契約サービスは印紙税が発生しないため、印紙税を考慮した契約形態にする必要がない。
- 電子契約サービスは印紙税が発生しないため、7号文書に2号文書や1号文書を同轍する必要はなく、そもそも契約書を製本する必要すらない。
このように、印紙税の節税には、電子契約サービスの利用が、最もおすすめです。
![]()
建設工事請負契約の契約条項のポイント
すでに触れたとおり、建設工事請負契約では、契約当事者には、建設業法第19条に規定する事項について、すべて契約書に規定する義務があります。
また、建設業法に規定する事項以外にも、次のような重要な契約条項があります。
建設工事請負契約の重要な契約条項
- 工事内容
- 契約形態
- 工事着手の時期および工事完成の時期
- 前金払いまたは出来高払いの支払時期・支払方法
- 設計変更・工事着手の延期・工事の中止の場合の取扱い
- 不可抗力
- 物価の変動・変更による請負代金(報酬・料金・委託料)・工事内容の変更
- 第三者の損害賠償金の負担
- 資材の提供
- 機械等の貸与
- 検査の時期・方法
- 引渡しの時期
- 所有権の移転
- 請負代金(報酬・料金・委託料)の金額または計算方法
- 請負代金(報酬・料金・委託料)の支払の時期
- 金銭の支払方法
- 契約不適合責任
- 損害保険
- 遅延利息・違約金・その他の損害金
- 知的財産権
- 再委託・下請負
- 秘密保持義務
- 契約解除・施工の中止
- 紛争解決方法(合意管轄・仲裁)
こうした建設工事請負契約の契約条項のポイントにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
補足:建設工事・業務委託・請負の関係は?
建設工事に関連する契約では、「建設工事」「業務委託」「請負」という用語が区別なく使われていて、混乱する場合があります。
これらの用語の意味は、それぞれ次のとおりです。
建設業の契約実務における建設工事・業務委託・請負の使い方
- 建設工事:法的に明確な定義はない。一般的には、建設工事請負契約を意味することが多いが、準委任契約であることもある。
- 業務委託:法的に明確な定義はない。一般的には、「建設業務」の準委任契約を意味することが多いが、請負契約であることもある。
- 請負:文字どおり、建設工事請負契約を意味する。
建設工事と業務委託の関係につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
建設業の業務委託と請負の違いにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
建設工事請負契約に関するよくある質問
- 建設工事請負契約とは何ですか?
- 建設工事請負契約とは、請負人(受託者)が何らかの建設工事を完成させること約束し、注文者(委託者)が、その建設工事の施工の対価として、報酬を支払うことを約束する契約のことです。
- 建設工事請負契約書の記載事項は何ですか?
- 建設業法第19条では、建設工事請負契約書について、以下の項目の記載を義務づけています。
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
- 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
- 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
- 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
- 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
- その他国土交通省令で定める事項