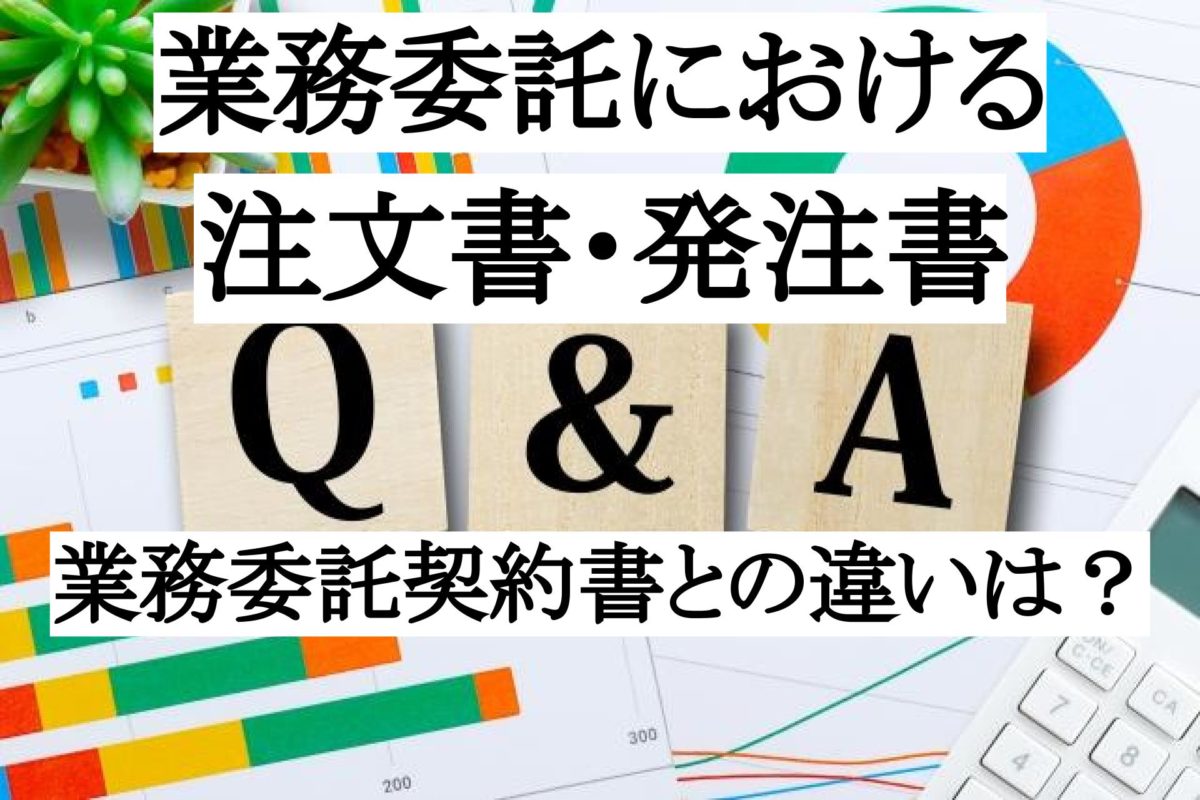請負契約とは、民法第632条に規定された、「仕事の完成」を目的とした契約です。
「請負契約と業務委託契約の違いがよくわからない…」と思ったことはないでしょうか。
それもそのはずで、請負契約は民法に規定された契約ですが、実は、業務委託契約は、民法にも他の法律にも規定されていません。
このように、業務委託契約の定義がはっきりと決まっていないからこそ、請負契約との違いもはっきりとしないのです。
実際の企業間取引の現場でも、「業務委託契約」というタイトルの契約であっても、実際は請負契約であることも多いです。
このページでは、こうした請負契約や請負型の業務委託契約の基本や注意点について、開業20年・400社以上の取引実績がある管理人が、わかりやすく解説していきます。
このページでわかること
- 請負契約の意味・定義・特徴・性質・基本
- 請負契約の具体例・代表例
- 請負契約と委任契約・準委任契約との違いの概要
- 請負契約型の業務委託契約のポイント
- 請負契約の当事者の権利義務と責任
- 請負契約の重要な契約条項の概要
- 請負契約の印紙税・収入印紙
請負契約(読み方:うけおいけいやく)とは
【特徴】請負契約は仕事の完成を目的とした契約
請負契約は、民法では、以下のように規定されています。
民法第632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
【意味・定義】請負契約とは?
請負契約とは、請負人(受託者)が仕事の完成を約束し、注文者(委託者)が、その仕事の対価として、報酬を支払うことを約束する契約をいう。
請負契約における仕事とは?
ここでいう「仕事」は、非常に広い意味で解釈されており、具体的には次のとおりです。
【意味・定義】仕事(請負契約)とは?
請負契約における仕事とは、請負人が労務をすることによって何らかの結果を生じさせることをいう。
つまり、仕事は、必ずしも有体物が発生することに限らず、プログラムのような無体物・知的財産であっても構いません。
また、「結果」である以上は、有体物や無体物ではない、一定の行為によってもたらされる結果もまた、「仕事」に該当します。
このため、成果物・納品物のない請負契約も存在します。
請負契約の性質・概要
請負契約の契約上の性質は、以下のとおりです。
| 請負契約の性質 | |
|---|---|
| 典型契約・非典型契約 | 請負契約は、民法第632条に規定する典型契約です。 |
| 双務契約・片務契約 | 請負契約は、注文者・請負人の双方が債務を負担すうる双務契約です。 |
| 有償契約・無償契約 | 請負契約は、注文者・請負人の双方から相手方に対する経済的な対価の交付がある有償契約です。 |
| 諾成契約・要物契約 | 請負契約は、当事者の合意のみで成立する諾成契約です。 |
| 要式契約・不要式契約 | 請負契約は、契約の成立に特定の方式を必要としない不要式契約です。ただし、成立には必要でないものの、一部の法律(下請法第3条等)書面の交付義務がある場合があります。 |
請負契約の代表例・具体例
請負契約の代表例や具体例には、以下のものがあります。
請負契約の代表例・具体例一覧リスト
- 建設工事請負契約
- 製造請負契約
- 運送請負契約
- システム等開発業務委託契約(特にウォーターフォール開発のもの)
- ウェブサイト制作請負契約
- グラフィックデザイン業務委託契約
このように、企業間取引における請負契約は、一定の成果物の納入が伴うスポットの契約が多いです。
なお、これらは、あくまでも代表的な例であり、実際のビジネスの現場では、様々な請負契約が締結されています。
ポイント
- 請負契約は、仕事の完成を目的とした契約。
- 請負契約は、典型契約、双務契約、有償契約、諾成契約、不要式契約。
- 企業間取引における請負契約は、一定の成果物の納入が伴うスポットの契約が多い。
請負契約と(準)委任契約の違い
請負契約=結果の責任、(準)委任契約=過程の責任
請負契約に似たような契約に、(準)委任契約があります。
【意味・定義】準委任契約とは?
準委任契約とは、委任者が、受任者に対し、法律行為でない事務をすることを委託し、受任者がこれ受託する契約をいう。
請負契約と(準)委任契約の主な違いは、請負契約が仕事の完成=結果に対する責任が発生する契約であるのに対し、(準)委任契約が行為そのもの=過程に対する責任が発生する契約である点です。
請負契約と(準)委任契約の主な違い
- 請負契約は仕事の完成=結果に対する責任が発生する。
- (準)委任契約は行為そのもの=過程に対する責任が発生する。
請負契約と(準)委任契約の14の違い一覧表
この他、請負契約と(準)委任契約とは、以下の14の点で違いがあります。
| 請負契約と(準)委任契約の違い | ||
|---|---|---|
| 請負契約 | (準)委任契約 | |
| 業務内容 | 仕事の完成 | 法律行為・法律行為以外の事務などの一定の作業・行為の実施 |
| 報酬請求の根拠 | 仕事の完成 | 履行割合型=法律行為・法律行為以外の事務の実施、成果完成型=成果の完成 |
| 受託者の業務の責任 | 仕事の結果に対する責任 (完成義務・契約不適合責任) | 仕事の過程に対する責任 (善管注意義務) |
| 報告義務 | なし | あり |
| 業務の実施による成果物 | 原則として発生する(発生しない場合もある) | 原則として発生しない(発生する場合もある) |
| 業務の実施に要する費用負担 | 受託者の負担 | 委託者の負担 |
| 受託者による再委託 | できる | できない |
| 再委託先の責任 | 受託者が負う | 原則として受託者が直接負う (一部例外として再委託先が直接負う) |
| 委託者の契約解除権 | 仕事が完成するまでは、いつでも損害を賠償して契約解除ができる | いつでも契約解除ができる。ただし、次のいずれかの場合は、損害賠償責任が発生する
|
| 受託者の契約解除権 | 委託者が破産手続開始の決定を受けたときは、契約解除ができる | いつでも契約解除ができる。ただし、委託者の不利な時期に契約解除をしたときは損害賠償責任が発生する |
| 印紙(印紙税・収入印紙) | 必要(1号文書、2号文書、7号文書に該当する可能性あり) | 原則として不要(ただし、1号文書、7号文書に該当する可能性あり) |
| 下請法違反のリスク | 高い | 高い |
| 労働者派遣法違反=偽装請負のリスク | 低い(ただし常駐型は高い) | 高い(常駐型は特に高い) |
| 労働法違反のリスク | 低い | 高い |
これらの点の詳しい解説につきましては、以下のページをご覧ください。
補足:請負契約と業務委託契約の違いは?
請負契約と業務委託契約は、同じであることもあれば、まったく違うこともあります。
というのも、実は業務委託契約は、法律上の定義がない契約です。その実態は、ほとんどが請負契約か準委任契約です。
業務委託契約は、一般的には、次の意味で使われています。
【意味・定義】業務委託契約とは?
業務委託契約とは、企業間取引の一種で、ある事業者が、相手方の事業者に対して、自社の業務の一部または全部を委託し、相手方がこれを受託する契約をいう。
このように、「業務委託契約」には法律的に正確な定義がないため、請負契約と業務委託契約の違いは、ある場合もあれば、ない場合もあります。
例えば、請負契約と請負契約である業務委託契約とは、当然ながら違いはありません。
また、請負契約と準委任契約である業務委託契約とは、すでに述べた違いがあります。
なお、業務委託契約の解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 請負契約=結果の責任、(準)委任契約=過程の責任
- 請負契約と(準)委任契約とでは、13もの違いがある。これらの違いを意識して、業務委託契約書を作成する。
- 請負契約と業務委託契約の違いは、ある場合もあれば、ない場合もある。
請負契約である業務委託契約のポイント・注意点
業務委託契約における請負契約の5つのポイントとは?
業務委託契約が請負契約に該当する場合には、特に次の5つのポイントを押さえておく必要があります。
請負契約の5つのポイント
- 【ポイント1】請負契約はあくまで「仕事の完成」が目的
- 【ポイント2】物品・知的財産の「納入」がある契約が多い
- 【ポイント3】サービスの提供を目的とした契約も請負契約となる
- 【ポイント4】請負契約は仕事の過程は問題とはならない
- 【ポイント5】請負契約は結果が出なければ責任が発生する
以下、それぞれ、詳しく解説します。
【ポイント1】請負契約はあくまで「仕事の完成」が目的
業務委託契約としての請負契約は、受託者(=請負人)が仕事の完成という義務を果たし、委託者(=注文者)がその報酬を支払う契約です。
請負契約の最大の特徴は、受注者(請負人)が「仕事の完成」という「結果」に対する責任を負う、という点です。つまり、請負契約の場合は、受注者(請負人)の結果責任が問われます。
これは、言いかえれば、「仕事の過程」については、特に問題にはならない、ということです。
【ポイント2】物品・知的財産の「納入」がある契約が多い
典型的な請負契約の例としては、建設業者がおこなう建築や土木などの建設工事の請負契約、いわゆる「建設工事請負契約」があります。
この他には、製造業者による製品の製造請負契約、プログラムの開発会社(ベンダー)によるソフトウェアの開発請負契約(一部(準)委任契約が含まれる場合もあります)などがあります。
納入がある請負契約の種類・具体例
- 建設工事請負契約
- 製造請負契約
- ソフトウェア開発契約
- システム開発契約
これらの請負契約は、形のある物体(建物・製品)や知的財産(プログラム)の「納入」があります。このため、「仕事の完成」が非常にイメージしやすい契約といえます。
ただし、実際の契約実務では、「納入」の後に「検査」の行程があり、この検査に合格することが「仕事の完成」とされることが多いです。
【ポイント3】成果物なし=サービスの提供を目的とした請負契約もある
また、請負契約は、物体や知的財産の納入がある契約だけではありません。目的物なし・成果物なしの、サービス(法律的には役務といいます)の提供の完成を目的とした請負契約もあります。
例えば、運送業者による運送請負契約もまた、請負契約の一種です。
運送請負契約の場合は、「荷主の荷物を引渡す」請負契約であるため、比較的「仕事の完成」がわかりやすいといえます。
ただ、一般的には、サービス提供型の請負契約は、何をもって「仕事の完成」とするのか、明らかでないあ場合もあります。このため、業務委託契約書での対策が重要となります。
【ポイント4】請負契約は仕事の過程は問題とはならない
請負契約では、どのような業務内容の契約であれ、受託者が問われるのは「仕事の完成」です。逆にいえば、「仕事の完成」がしっかり問題なくできていれば、「仕事の過程」は問題とはなりません。
例えば、建設工事請負契約で、建設業者の職人がお酒を飲んで酔っ払って施工していたとしても、出来た建物に欠陥がなければ、請負契約としては問題とはなりません。
また、同じように、運送請負契約で、運送業者のドライバーが交通違反で処分を受けたり、交通事故を起こしたとしても、荷物に損傷がなければ、請負契約としては問題となりません。
【ポイント5】請負契約は結果に問題があれば責任が発生する
逆に言えば、どんなに一生懸命いい仕事をして、業務内容が素晴らしいレベルのものだったとしても、結果として「仕事の完成」に至らなかった場合は、受託者(請負人)には、責任が発生します。
例えば、システム開発請負契約で、勤務態度が真面目なエンジニアの方が、毎朝早くスーツとワイシャツをビシッと着て出勤して、夜遅くま頑張ってコーディングをして、なんとか納期のギリギリにシステムを納入してくれたとしましょう。
このシステムがバグだらけで、まともに機能しない場合、どんなにエンジニアの方が頑張ったとしても、請負契約としては契約違反となり、受託者である開発会社に責任が発生します。
ポイント
- 請負契約は「仕事の完成」を目的とした契約。あくまで結果が問題であって、過程は問題とはならない。
- 物品(製品・目的物・成果物)の「納入」がない、サービス提供型の請負契約もある。
請負契約の請負人の義務・責任・権利
請負契約の請負人には、以下の5つの義務・責任があります。
請負契約における請負人の5つの義務・責任
- 【義務・責任1】仕事に着手する義務
- 【義務・責任2】期限(納期)までに仕事を完成させる義務
- 【義務・責任3】再委託先・下請負人の行為にもとづく責任
- 【義務・責任4】仕事の完成前の災害による損害の負担
- 【義務・責任5】契約不適合責任
他方で、請負契約の請負人には、以下の2つの権利があります。
請負契約における受託者(請負人)の2つの権利
- 【権利1】報酬請求権
- 【権利2】注文者の破産手続きが開始されたときの契約解除権
これらの請負人の義務・責任・権利の解説につきましては、詳しくは、以下のページをご参照ください。
請負契約の注文者の責任・義務
請負契約の注文者には、以下の2つの義務・責任があります。
請負契約における受託者(請負人)の2つの責任・義務
- 【義務・責任1】報酬の支払い義務
- 【義務・責任2】注文・指図にもとづく第三者に対する責任
他方で、請負契約の注文者には、以下の2つの権利があります。
請負契約における受託者(請負人)の2つの権利
- 【権利1】「仕事の完成」を請求できる権利
- 【権利2】契約解除権・中途解約権
これらの注文者の義務・責任・権利の解説につきましては、詳しくは、以下のページをご参照ください。
請負契約型の業務委託契約の重要な14の条項とポイント
請負契約型の業務委託契約書を作成する場合、次の14の条項が重要となります。
請負契約型の業務委託契約で重要な14の条項 | |
|---|---|
| 1.業務内容 | 業務内容の条項は、注文者が請負人に対し発注する、仕事=業務の内容について規定する条項です。請負契約においては、最も重要な条項のひとつです。 |
| 2.受発注の手続き | 受発注の手続きは、反復継続する請負契約、いわゆる請負取引基本契約において規定する、個々の個別契約の受発注に関する手続きを規定する条項です。 |
| 3.納入期限・納入期日または提供期日・提供期間 | 納入期限・納入期日の条項では、なんらかの納入物を納入する請負契約において、その納入の期限または期日を規定する条項です。 提供期日・提供期限の条項では、なんらかの役務=サービスを提供する請負契約において、その役務の提供の期日または期限を規定する条項です。 |
| 4.納入場所・業務実施の場所 | 納入場所の条項では、なんらかの納入物を納入する請負契約において、その納入の場所を規定する条項です。 提供場所の条項では、なんらかの役務=サービスを提供する請負契約において、その役務の提供の場所を規定する条項です。 |
| 5.検査(検査項目・検査方法・検査基準) | 検査の条項は、検査を実施する際の検査項目、各検査項目の検査の方法、検査結果の合否の判定基準(検査基準)、を規定する条項です。 |
| 6.検査期限・検査手続 | 検査期限の条項は、委託者による検査を実施する期間または期限と、検査の合否に関する手続きを規定します。 |
| 7.契約不適合責任 | 契約不適合責任(旧民法における瑕疵担保責任)の条項は、請負型の業務委託契約の場合における、契約不適合の定義、契約不適合責任、契約不適合責任の期間等を規定します。 |
| 8.報酬・料金・委託料 | 報酬・料金・委託料の金額・計算方法の条項は、具体的な数字や計算方法により、報酬・料金・委託料を規定する条項です。 |
| 9.原材料の有償支給 | 原材料の有償支給の条項は、何らかの製品の製造請負契約において、注文者から原材料を有償支給される場合における、原材料の料金、納入、検査、契約不適合責任等について規定する条項です。 |
| 10.所有権の移転 | 所有権の移転の条項は、物品・製品・有体物の成果物の納入がある業務委託契約の場合において、これらの所有権の移転の時期について規定する条項です。 |
| 11.危険負担の移転 | 危険負担の移転の条項は、物品・製品・有体物である成果物が発生する業務委託契約の場合において、これらになんらかの損害が発生した場合の負担について規定する条項です。 |
| 12.成果物の著作権の取扱い(譲渡または使用許諾) | 成果物の著作権の取扱いの条項は、著作権が発生する請負契約における、著作権の譲渡または使用許諾について規定する条項です。 |
| 13.再委託・下請負 | 再委託・下請負の条項は、受託者による業務の再委託・下請負ができるかどうかを規定する条項です。 |
| 14.契約解除・中途解約 | 契約解除・中途解約の条項は、無催告解除・催告解除に該当する契約解除事由を規定する条項です。 |
ポイント
請負契約型の業務委託契約では、少なくとも13の重要な条項について検討し、業務委託契約書を作成する。
請負契約である業務委託契約書には収入印紙が必要?金額は?
請負契約書は、収入印紙が必要な契約です。
金額は、契約内容や報酬・料金・委託料によって、変わってきます。
請負契約書の印紙税額
- 継続的取引きの基本となる契約書(いわゆる取引基本契約書)の場合:4,000円(いわゆる7号文書)
- 請負契約書(ただし、建設工事請負契約書を除く):(契約金額が1万円から課税対象)200円~(いわゆる2号文書)
- 建設工事請負契約書:(契約金額が1万円から課税対象)200円~(いわゆる2号文書。ただし、軽減措置により、一般の請負契約書とは別計算)
なお、契約内容として、著作権などの知的財産権の譲渡がある場合は、2号文書・7号文書だけでなく、別途1号文書にも該当します。
この場合は、特に2号文書だけに該当する場合と計算方法が違ってきますから、注意が必要です。
請負契約書における印紙税・収入印紙につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
請負契約に関するよくある質問
- 請負契約とは何ですか?
- 請負契約とは、請負人(受託者)が仕事の完成を約束し、注文者(委託者)が、その仕事の対価として、報酬を支払うことを約束する契約のことです。
- 請負契約の代表例は?
- 請負契約の代表例には、以下のとおりです。
- 建設工事請負契約
- 製造請負契約
- 運送請負契約
- システム等開発業務委託契約(特にウォーターフォール開発のもの)
- ウェブサイト制作請負契約
- グラフィックデザイン業務委託契約
- 請負契約の義務・責任には、どのようなものがありますか。
- 請負契約の注文者には、報酬の支払い義務、注文・指図にもとづく第三者に対する責任があります。また、請負契約の請負人には、仕事に着手する義務、期限(納期)までに仕事を完成させる義務、再委託先・下請負人の行為にもとづく責任、仕事の完成前の災害による損害の負担、契約不適合責任があります。
- 請負契約書の印紙税はどちらが負担するのでしょうか?
- 印紙税法では、印紙税は、課税文書の作成者が納税義務者となっています(印紙税法第3条)。他方で、民法上は、契約の締結に要する費用は、当事者の双方が折半して負担することとされています(民法第558条、第559条)。このため、一般的な企業間取引の請負契約では、印紙税は、契約当事者が双方折半して負担することが多いです。
請負契約の関連ページ
請負契約の関連ページ
- 請負契約とは?委任や業務委託契約との関係もわかりやすく解説
- 【改正民法対応版】業務委託契約における請負契約と(準)委任契約の13の違い
- 請負契約の契約解除権・法定解除権とは?
- 建設工事請負契約における業務内容(設計図面・仕様書・設計図書)の決め方・書き方とは?
- 製造請負契約における業務内容(仕様書・設計図・図面・金型)の決め方・書き方とは?
- 建設工事請負契約とは?意味・定義や建設業法の規制について解説
- 製造請負契約とは?意味・定義について解説
- 請負契約書にはいくらの収入印紙を貼るの?印紙税はいくら?
- 請負契約型の業務委託契約で重要な14の条項
- 建設工事請負契約書の作り方と重要な24の契約条項のポイントについて解説
- 製造請負契約書の作り方と重要な20の契約条項のポイントについて解説
- 【改正民法対応】請負契約における注文者の義務・責任と権利とは?
- 【改正民法対応】請負契約における請負人の義務・責任と権利とは?