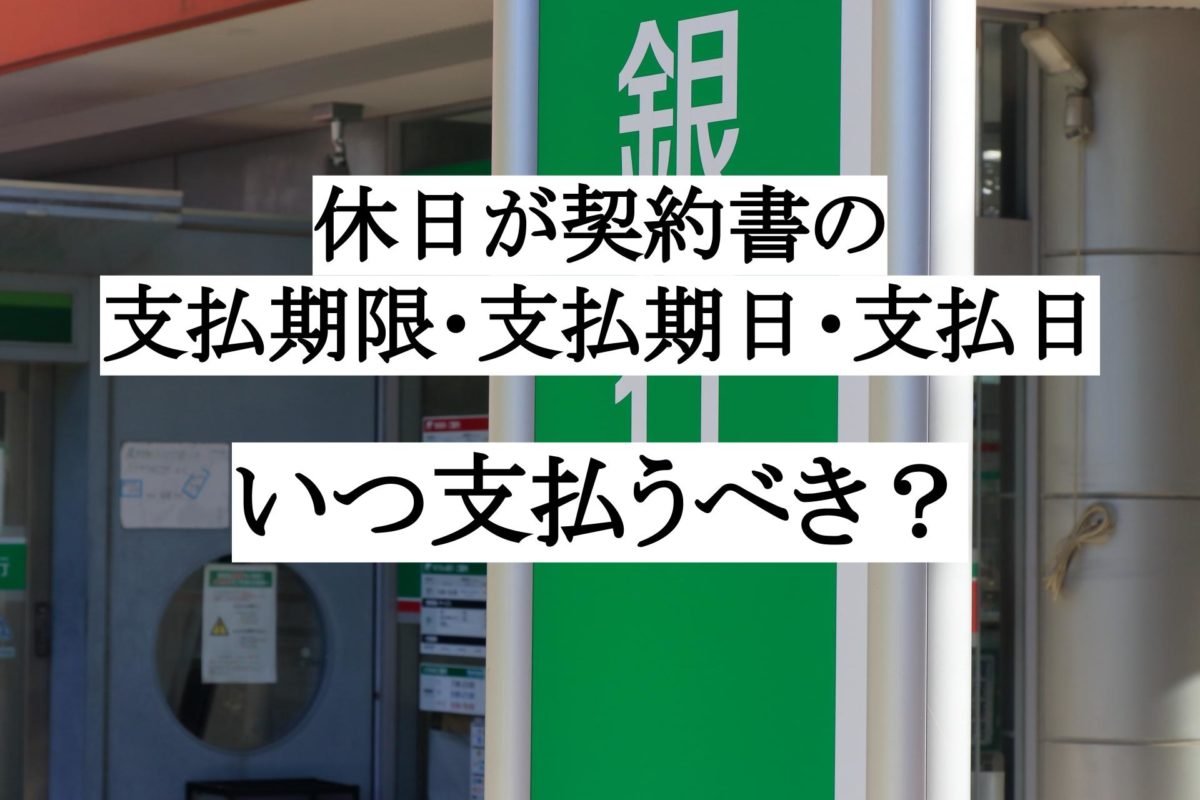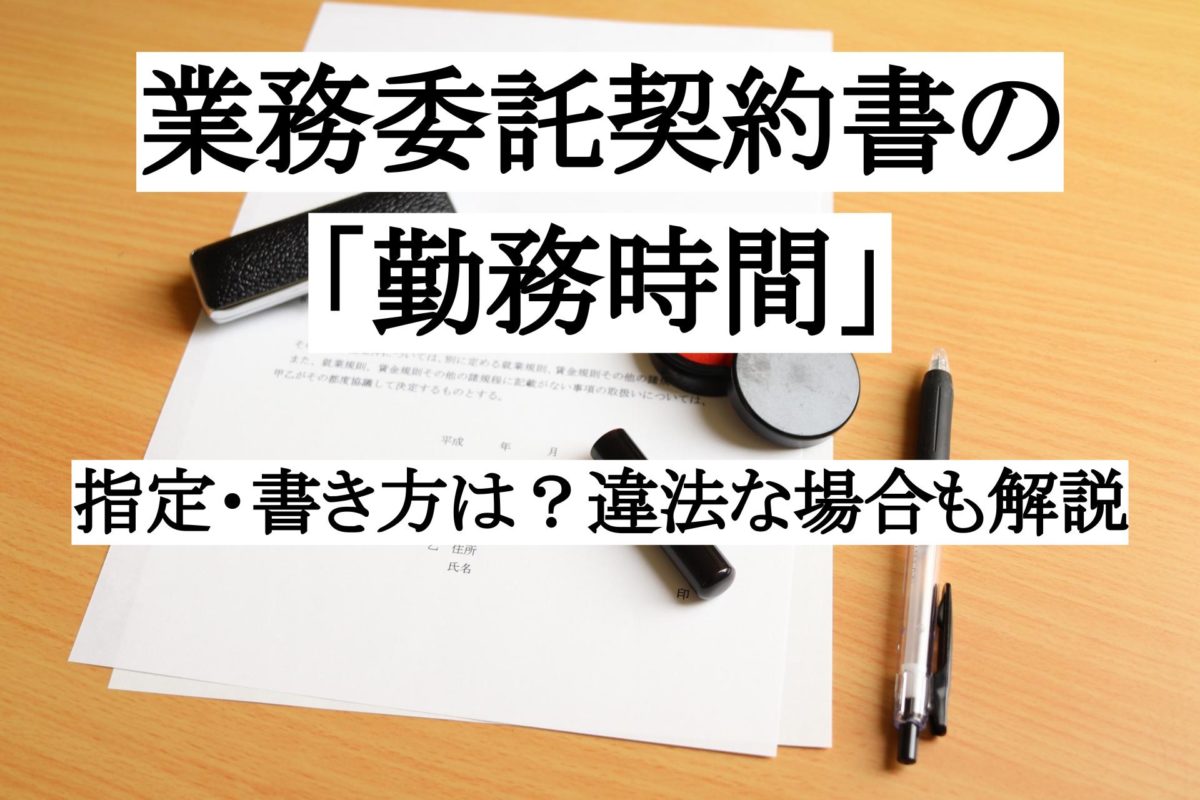契約形態の条項では、その業務委託契約が、民法上のどの契約(主に請負契約か準委任契約)に該当するのかを規定します。
この契約形態の条項は、民法上の定義がない業務委託契約においては、契約の全体に関わる非常に重要な規定です。
このページでは、契約形態の条項の規定のしかたや書き方と、業務委託契約に与える影響について解説します。
契約形態の条項で民法のどの契約なのかを規定する
【意味・定義】契約形態とは?
契約実務における契約形態とは、一般に、その契約や契約書に記載された内容が該当する、法律により定義づけられた契約のことをいいます。
【意味・定義】契約形態とは?
契約形態とは、一般に、その契約や契約書に記載された内容が該当する、法律により定義づけられた契約のことをいう。
契約内容や契約書の記載によっては、その契約が、民法を始めとした各種法律で定義づけられたどの契約が不明である場合があります。
このため、契約形態を明らかにするという点で、契約形態を明記する契約条項は、非常に重要となります。
【意味・定義】契約形態条項とは?
契約形態条項とは、その契約が(主に)民法上のどの契約に該当するのかを規定する条項をいう。
契約形態の条項の記載例・例文
契約形態の条項では、その契約が、民法上のどの契約に該当するのかを規定します。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】契約形態に関する条項(アジャイル型開発の場合)
第○条(契約形態)
1 本契約の契約形態は、発注者を委任者、受注者を受任者とした、民法第656条に規定する準委任契約とする。
2 発注者およぶ受注者は、本契約を民法第632条に規定する請負契約と解釈してはならない。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
この契約形態の記載例は、アジャイル型開発のシステム・アプリ・ソフトウェア開発の契約書のものです。
第1項では、準委任契約であることを明記しています。
通常は、第1項だけで問題ないのですが、第2項で請負契約ではないことを強く否定しています。
これは、アジャイル型開発の契約の場合は、開発対象となるシステム・アプリ・ソフトウェアの完成を巡ってトラブルとなることが多いため、受注者に完成の義務がないことを明確にする目的があります。
契約形態の条項ではその契約が何の契約なのかを規定する
業務委託契約は、そもそも法律上の定義がない契約です。
「契約」にはいろんな種類がありますが、その多くは、民法で明確に規定されています(典型契約・有名契約。後掲)。
また、民法以外の法律によって規定されている契約もあります(例:労働者派遣法に規定されている労働者派遣契約など)。
ところが、「業務委託契約」は、民法でも、その他の契約でも、定義が規定されていません。
つまり、業務委託契約は、「法的には存在しない契約」である、ということです。
この他、業務委託契約の定義と基本的な解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
業務委託契約の契約形態は主に2種類
業務委託契約は請負契約か準委任契約
そこで、業務委託契約では、契約形態の条項で、その業務委託契約が民法上は何の契約に該当することを意図しているのかを規定します。
一般的な業務委託契約は、主に民法上の請負契約か準委任契約の2種類のいずれかとなります。
【意味・定義】請負契約とは?
請負契約とは、請負人(受託者)が仕事の完成を約束し、注文者(委託者)が、その仕事の対価として、報酬を支払うことを約束する契約をいう。
【意味・定義】準委任契約とは?
準委任契約とは、委任者が、受任者に対し、法律行為でない事務をすることを委託し、受任者がこれ受託する契約をいう。
このため、実際に受託者が提供する業務内容から、請負契約か準委任契約のどちらに該当するのかを検討して、契約条項として決定します。
請負契約と(準)委任契約の違いにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
請負契約・準委任契約以外の契約形態の種類は?
なお、民法には、13種類の契約が規定されています。
この民法に規定されている典型的な契約のことを、典型契約または有名契約といいます。
【意味・定義】典型契約・有名契約とは?
典型契約・有名契約とは、売買契約、請負契約、委任契約などの、民法に規定されている13種類の契約をいう。
13種類の典型契約・有名契約の一覧
- 贈与契約(民法第549条)
- 売買契約(民法第555条)
- 交換契約(民法第586条)
- 消費貸借契約(民法第587条)
- 使用貸借契約(民法第593条)
- 賃貸借契約(民法第601条)
- 雇用契約(民法第623条)
- 請負契約(民法第632条)
- 委任契約(民法第643条)
- 寄託契約(民法第657条)
- 組合契約(民法第667条)
- 終身定期金契約(民法第689条)
- 和解契約(民法第695条)
これらのうち、業務委託契約は、請負契約と準委任契約の他にも、寄託契約、組合契約、雇用契約(労働契約)、売買契約、譲渡契約に該当することもあります。
このため、業務委託契約の契約形態は、合計で7種類となります。
この7種類の業務委託契約の契約形態につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 業務委託契約は、法的定義・民法上の定義がない契約。
- 多くの業務委託契約は、民法上の請負契約か準委任契約。
- 業務委託契約書では、必ず契約形態を規定する。
業務委託契約において契約形態を明確に決めないことのリスクは?
意外に契約形態は明記されていない
一般的な業務委託契約書には、契約形態が明記されていない場合もあります。
というよりも、業務委託契約書で契約形態が明記されていることは、意外にありません。
実は、こうした契約形態が不明であることは、非常に大きなリスクがあります。
契約形態が不明な場合のリスク
- 【リスク1】業務の結果が失敗した場合にその責任を巡ってトラブルとなる
- 【リスク2】不要な印紙税を負担させられる
以下、詳しく解説していきます。
【リスク1】業務の結果が失敗した場合にその責任を巡ってトラブルとなる
結果についての責任に大きな違いがある
最も大きなリスクは、業務の実施そのもののがトラブルになる可能性がある、という点です。
請負契約と準委任契約は、「何かの業務を実施する」という、外形的には非常によく似た契約です。
しかし、実は、その業務の実施の性質は大きくことなります。
特に、業務を実施した結果についての責任の有無が、決定的に違います。
請負契約と準委任契約の大きな違い
- 請負契約:受託者が【仕事の結果】に責任を負う契約。仕事の過程の責任は問われない。仕事が完成しなくても出来高払いではあるが報酬・料金・委託料の支払いがある。
- 準委任契約:受託者が【仕事の過程】に責任を負う契約。仕事の結果の責任は問われない。仕事が完成しなくても業務の実施があれば報酬・料金・委託料の支払いがある。
業務の結果が失敗した場合に主張が対立する
このため、契約形態を決めていないと、業務を実施した結果が失敗した場合に、委託者・受託者の双方が、自分にとって都合のいい契約形態を主張します。
これは、特にシステム等開発業務委託契約では、よくあるトラブルです。
システム等開発業務委託契約では、システム等の開発が頓挫したり、完成度が著しく低い場合、裁判まで発展するケースもあります。
こうした裁判では、ソフトウェア・プログラム・システム・アプリの完成度と契約形態を巡って、ユーザとベンダが、次のとおり主張します。
契約形態に関するトラブル
- ユーザの主張:契約形態は請負契約。よって、ソフトウェア・プログラム・システム・アプリが完成しないと報酬・料金・委託料は支払義務はない(せいぜい認められても出来高払い)。
- ベンダの主張:契約形態は準委任契約。よって、ソフトウェア・プログラム・システム・アプリが完成しなかったとしても報酬・料金・委託料の請求権がある。
こうしたトラブルがないように、業務委託契約、特にシステム等開発業務委託契約では、契約形態を契約書に明記して作成するべきです。
【リスク2】不要な印紙税を負担させられる
また、それほど大きなリスクというわけではありませんが、契約形態を決めておかないと、払う必要のない印紙税を負担させられることになります。
請負契約と準委任契約の違いのひとつとして、契約書での印紙税の負担の有無があります。
| 請負契約 | 準委任契約 | |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 必要(1号文書、2号文書、7号文書に該当する可能性あり) | 原則として不要(ただし、1号文書、7号文書に該当する可能性あり) |
原則として、準委任契約書は不課税文書であるため、準委任契約書を作成した場合、印紙税を負担する必要はありません。
このため、準委任型の業務委託契約書の場合は、わざわざ契約形態を明記することにより、不必要な印紙税を負担するリスクもなくなります。
逆に、業務委託契約書に準委任契約であることが規定されていなければ、税務調査の際、税務署・国税庁の担当官から、請負契約と解釈される可能性があります。
こうなると、不必要な印紙税に加えて、過怠税を負担しなければならなくなります。
なお、準委任契約の印紙税については、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 業務の実施の結果が失敗であった場合、契約形態を決めていないと、双方が自分にとって都合のいい契約形態を主張し、トラブルとなる。
- 契約形態を契約書に明記していないと、払わなくてもいい印紙税を負担させられる可能性がある。
業務委託契約の契約形態条項は目的条項と同じ条項にすることも
契約形態の条項は、目的条項と同じ条項(多くは第1条)にすることもあります。
契約形態が第1条に規定されているほうが、契約全体を早く理解するためには便利ではあります。
ただ、だからといって、契約形態の記載が必ず第1条でなければならない、というわけではありません。
第1条よりも後でもかまいませんし、契約の構成によっては、個別契約で規定する場合もあります(システム等開発業務委託契約の場合など)。
このほか、目的条項につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
業務委託契約が請負契約か準委任契約かは当事者が決める
当事務所によく寄せられるご質問ですが、すでに締結している業務委託契約について、「請負契約でしょうか?それとも準委任契約でしょうか?」というお問合わせをいただくことがあります。
業務委託契約が請負契約に該当するのか、準委任契約に該当するのかは、当事者が決めるべきものです。(たとえ専門家であっても)第三者が決めることではありません。
もちろん、専門家としては、客観的に見て、請負契約か準委任契約かの見解を述べることはできますが。
このため、これから締結する業務委託契約であれば、相手方と協議のうえ、請負契約が準委任契約かを決めるべきです。
また、すでに締結した業務委託契約であっても、後から追加で合意することはできますので、こちらも相手方と協議のうえ、請負契約が準委任契約かを決めるべきです。
ポイント
- 請負契約か準委任契約かは、当事者が決める。たとえ専門家であっても、第三者が決めることではない。
契約形態に関するよくある質問
- 契約形態とは何ですか?
- 契約形態とは、一般に、その契約や契約書に記載された内容が該当する、法律により定義づけられた契約のことをいいます。企業間の契約では、主に請負契約か準委任契約のいずれかを規定する契約条項となります。
- 契約形態の一覧は?また、どのような種類がありますか?
- 民法上の契約形態には、以下の種類があります。
- 贈与契約(民法第549条)
- 売買契約(民法第555条)
- 交換契約(民法第586条)
- 消費貸借契約(民法第587条)
- 使用貸借契約(民法第593条)
- 賃貸借契約(民法第601条)
- 雇用契約(民法第623条)
- 請負契約(民法第632条)
- 委任契約(民法第643条)
- 寄託契約(民法第657条)
- 組合契約(民法第667条)
- 終身定期金契約(民法第689条)
- 和解契約(民法第695条)
このうち、業務委託契約の契約形態で特に問題になるのは、請負契約の(準)委任契約いずれに該当するのか、とういう点です。
- 個人事業者との契約において注意するべき契約形態は何ですか?
- 個人事業者と契約する場合は、適法な請負契約や準委任契約としなければ、雇用契約・労働契約とみなされるリスクがあります。これを回避するには、「昭和60年労働基準法研究会報告」の基準に準拠した契約書を作成する必要があります。
- 企業間契約で注意するべき契約形態は何ですか?
- 企業間契約では、特に請負契約や準委任契約などの業務委託契約の場合は、適法な契約内容としないと、偽装請負とみなされ、労働者派遣法違反となるリスクがあります。これを回避するには、37号告示に準拠した契約書を作成する必要があります。