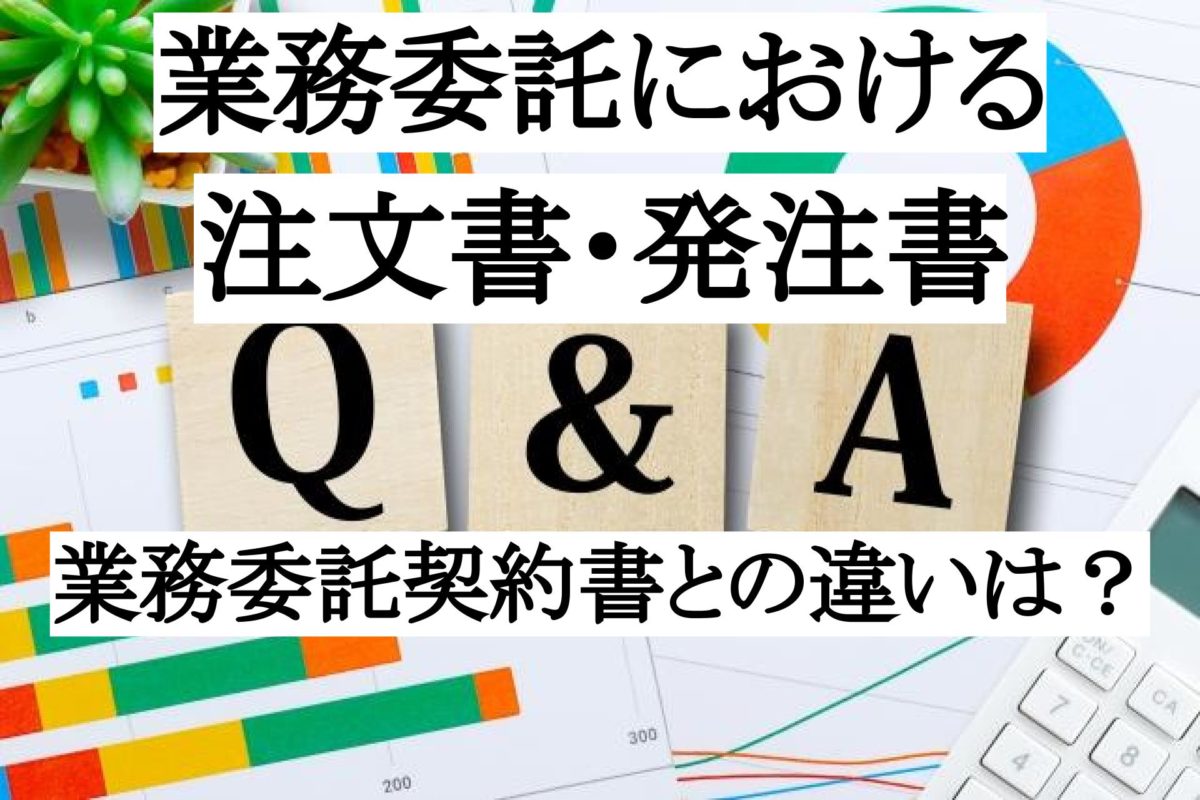このページでは、契約書がない場合の業務委託の8つの注意点・リスク・デメリット注意点を紹介しています。
業務委託契約は、原則として、口約束でも成立します。このような、当事者の合意だけで成立する契約を「諾成契約」といいます。
このような諾成契約である業務委託契約と結ぶ際、法律上の義務がない限り、契約書を作成する必要はありません。
ただ、業務委託契約は企業間の取引ですので、金額も多額となることも多く、契約内容も複雑です。
にもかかわらず、業務委託契約書を作成せずに、口約束で済ませると、さまざまなリスク・デメリットがあります。
このページでは、そうしたリスク・デメリットの中でも、典型的な8つのパターンを紹介しています。
なお、下請法が適用される業務委託契約や建設工事の業務委託契約書の場合は、業務委託契約書を作成しないこと自体が違法行為となりますので、ご注意ください。
また、業務委託契約書の基本的なポイントにつきましては、以下のページをご覧ください。
契約書がない業務委託の注意点・リスク・デメリット一覧
まず、契約書がない業務委託のリスク・デメリットには、大きく分けてつぎの8つのパターンがあります。
業務委託契約書を作成しない注意点・リスク・デメリット
- 【注意点1】業務委託契約の内容を巡ってトラブルとなる
- 【注意点2】下請法違反となる
- 【注意点3】業務委託契約が雇用契約・労働契約とみなされる
- 【注意点4】業務委託契約が偽装請負とみなされる
- 【注意点5】建設工事請負契約の場合は建設業法違反となる
- 【注意点6】著作権を巡ってトラブルとなる
- 【注意点7】業務委託契約が資金決済法違反となる
- 【注意点8】税法違反・税務調査に対応できない
以下、それぞれ詳しく解説していきます。
【注意点1】業務委託契約の内容を巡ってトラブルとなる
業務委託契約書がない=証拠がない
業務委託契約書を作成しないことによって、委託者・受託者の両者にとってのデメリットとなるのが、契約内容を巡って水掛け論・トラブルとなる、ということです。
業務委託契約書に限ったことではありませんが、契約書は、契約の存在自体を証明する、最も有力な物的証拠=物証となります。逆に、契約書を作成しておかないと、客観的な契約内容を証明する記録が、ほとんど残りません。
ですから、いざ契約内容を巡ってトラブルとなった場合、契約内容そのものがどうであったかを巡って、当事者の見解が対立します。
利害が対立してから業務委託契約の内容を決めるのでは遅い
業務委託契約を結ぶ前、つまりトラブルになっていない段階でも、契約内容を決めるのは、非常に難しいことです。
ましてや、トラブルになってしまったら、当事者間で利害が完全に対立してしまいます。
こうした場合に業務委託契約書がないと、それぞれが都合のいいように契約内容を主張してきます。
こうなると、もはや水掛け論となり、収集がつかなくなります。
電子メール・SNS・チャットでは業務委託契約の内容を詰め切れない
現在では、電子メール、SNS、チャットツールなど、記録媒体が増えているため、かつてよりは、契約内容を推測しやすくなっています。ただ、こうした記録媒体と紙の契約書の決定的な違いは、当事者間を拘束する法的な権利義務の詳細な内容を詰めるかどうか、という点です。
通常、電子メール、SNS、チャットツールなどは、連絡手段として使いますが、契約書の調印のように、法的な権利義務を発生させる目的では使いません。
このため、連絡の表現も、たとえそれが一種の合意を取り付けるものであっても、あいまいなものが多く、契約書ほど詳細に詰められていません。
電子メール、SNS、チャットツールなどの連絡では、改めて紙の契約書を作成するのと比べて、どうしても契約内容があいまいになりがちです。
ポイント
- 業務委託契約書がないということは、業務委託契約関する法的な物証がない、ということ。
- 利害が対立してからでは、委託者・受託者の双方が自分にとって都合のいい主張をするため、契約内容を決められない。
- 電子メール・SNS・チャットでは、業務委託契約書と違って、契約内容を詰め切れない。
【注意点2】下請法違反となる
業務委託契約書を作成しないことによって、委託者にとってのリスク・デメリットになるのが、下請法の違反です。
【意味・定義】下請法とは?
下請法とは、正式には「下請代金支払遅延等防止法」といい、親事業者に対し義務・禁止行為を課すことにより、下請代金の支払遅延等を防止するなど、下請事業者を保護することを目的とした法律をいう。
下請法第3条にもとづく書面(三条書面)を交付する義務がある
下請法が適用される業務委託契約の場合、親事業者(=委託者)は、下請業者(受託者)に対し、下請法第3条にもとづき、契約内容が記載された書面を交付する義務があります。
下請法第3条(書面の交付等)
1 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。
2 親事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該親事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
契約実務では、この書面のことを、「三条書面」といいます。
【意味・定義】三条書面(下請法)とは?
三条書面(下請法)とは、下請代金支払遅延等防止法(下請法)第3条に規定された、親事業者が下請事業者対し交付しなければならない書面をいう。
三条書面につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
下請法第5条にもとづく書類(五条書類)を保存する義務がある
また、下請法が適用される業務委託契約の場合、親事業者(=委託者)は、下請法第5条にもとづき、契約内容が記載された書面を保存する義務があります。
下請法第5条(書類等の作成及び保存)
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則で定めるところにより、下請事業者の給付、給付の受領(役務提供委託をした場合にあつては、下請事業者がした役務を提供する行為の実施)、下請代金の支払その他の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、これを保存しなければならない。
契約実務では、この書類のことを「五条書類(または五条書面)」といいます。
【意味・定義】五条書類・五条書面とは?
五条書類(書面)とは、下請法第5条にもとづき、親事業者が、作成し、保存しなければならない書類。
五条書類・五条書面につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
下請法第3条・第5条違反は最大50万円の罰金刑
親事業者(=委託者)が下請業者(=受託者)に対し、三条書面を交付しない場合は、50万円以下の罰金が科されます。
親事業者(=委託者)が、五条書類(五条書面)を保存しない場合は、同様に、50万円以下の罰金が科されます。
下請法第10条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、50万円以下の罰金に処する。
(1)(省略)
(2)第5条の規定による書類若しくは電磁的記録を作成せず、若しくは保存せず、又は虚偽の書類若しくは電磁的記録を作成したとき。
ポイントは、単に親事業者である法人に罰金が科されるのではなく、「その違反行為をした親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者」に罰金が科される、ということです。
会社で50万円を払えばいい、というものではないのです。しかも、50万円とはいえ、いわゆる「前科」がつきます。
三条書面・五条書類(五条書面)を兼ねた業務委託契約書を作成する
このように、下請法が適用される業務委託契約では、親事業者(=委託者)は、三条書面を作成して、下請業者(=受託者)に交付し、かつ、社内で五条書類(五条書面)を保存しておかなければなりません。そこで重要となるのが、業務委託契約書です。
三条書面と五条書類(五条書面)の内容が記載された業務委託契約書を作成して取交し、1部を親事業者(=委託者)が保存し、1部を下請業者(=受託者)に交付します。
こうすることで、三条書面の交付と、五条書類(五条書面)の保存の両方をすることができます。わざわざ、別に書類を作る必要はありません。
このように、下請法が適用される業務委託契約では、親事業者(=委託者)にとって、業務委託契約書の作成は事実上の義務といえます。
下請法につきましては、以下のページもご覧ください。
ポイント
- 下請法が適用される業務委託契約では、委託者(=親事業者)は、受託者(=下請事業者)に対し、下請法第3条にもとづく書面(三条書面)を交付する義務がある。
- 下請法が適用される業務委託契約では、委託者(=親事業者)は、下請法第5条にもとづく書類(五条書類)を保存する義務がある。
- 下請法第3条・第5条違反は、最大50万円の罰金刑。
- 下請法が適用される業務委託契約では、委託者(=親事業者)は、三条書面・五条書類(五条書面)を兼ねた業務委託契約書を作成する。
【注意点3】業務委託契約が雇用契約・労働契約とみなされる
業務委託契約書を作成しないことによって、委託者にとってのリスク・デメリットとなるのが、各種労働法の違反です。
「業務委託契約」という名目の雇用契約・労働契約
個人事業者やフリーランスが受託者となる業務委託契約の場合、取引の実態によっては、業務委託契約ではなく、雇用契約・労働契約とみなされる可能性があります。特に、常駐型の準委任の業務委託契約の場合、作業や労力の提供をしてもらうことになるため、雇用契約・労働契約と区別がつきません。
このため、契約実務では、『労働基準法研究会報告』(労働基準法の「労働者」の判断基準について)(昭和60年12月19日)に準拠して、適法な業務委託契約書を作成しなければなりません。
また、単に形式的に業務委託契約書を作成するのではなく、実態としても、雇用契約・労働契約ではなく、業務委託契約としての取引であることが重要です。
この点につきましては、以下のページもご覧ください。
偽装「業務委託契約」のペナルティ
偽装業務委託契約・偽装請負の4つのペナルティ
実態が雇用契約・労働契約であるにもかかわらず、請負契約等の業務委託契約に偽装した場合、主に次の4つのペナルティが課されれます。
偽装業務委託契約・偽装請負の4つのペナルティ
- 【ペナルティ1】労働基準法違反(特に残業代の支払い)
- 【ペナルティ2】源泉所得税の徴収
- 【ペナルティ3】社会保険料の負担
- 【ペナルティ4】最低賃金の支払い
以下、それぞれ詳しく解説していきます。
【ペナルティ1】労働基準法違反(特に残業代の支払い)
本来は雇用契約・労働契約であるにかかわらず、労働者を個人事業者・フリーランスとして扱い、偽装「業務委託契約」を結んだ場合、各種の労働法に違反します。代表的な法律としては、労働基準法に違反することになります。
労働基準法は、雇用契約・労働契約の内容として、最低限の労働基準を定めた法律です。
偽装「業務委託契約」が雇用契約・労働契約とみなされた場合に、労働基準法に定める労働基準を下回った業務委託契約の内容だったときは、あらゆる点で労働基準法違反となります。
代表的なものとしては、偽装「業務委託契約」の報酬・委託料が、雇用契約・労働契約としての給料や残業代を下回っていた場合です。
この倍は、「委託者」(=本来は使用者)は、「受託者」(=本来は労働者)に対して、足りない分の給料や残業代を支払わなければなりません。
【ペナルティ2】源泉所得税の徴収
次に、税務調査に入られた際、個人事業者・フリーランスとの業務委託契約の報酬・料金・委託料で源泉徴収をしていない場合、源泉所得税を徴収されるリスクがあります。
一般的に、個人事業者・フリーランスとの業務委託契約では、報酬・料金・委託料が源泉徴収の対象となることが多いため、源泉所得税を払っている場合は、特に税務署としても厳しい対応はしません。
ところが、報酬・料金・委託料が源泉徴収とならない業務委託契約の場合、税務署としては、「実はこの業務委託契約は雇用契約・労働契約に該当するのでは?」と考えます。
当然、雇用契約・労働契約と判断されると、給与所得の源泉所得税を支払わなければならなくなります。しかも、追徴課税や延滞税まで発生します。
【ペナルティ3】社会保険料の負担
そして、忘れてはならないのは、社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料・労災保険料)です。偽装「業務委託契約」で社会保険の負担を免れようとする経営者は、非常に多いです。
当然ながら、適法な業務委託契約としなければ、雇用契約・労働契約とみなされ、社会保険料を負担しなければならなくなります。
ちなみに、社会保険料は、最長で過去2年分を遡って徴収されますので、かなり高額な負担となります。
【ペナルティ4】最低賃金の支払い
かなりレアなケースだとは思いますが、偽装「業務委託契約」の報酬・委託料が時給換算で最低賃金を下回る場合に、偽装「業務委託契約」が雇用契約・労働契約とみなされたときは、少なくとも最低賃金分の報酬・委託料は支払わなければなりません。
過去の判例では、業務委託契約の報酬・委託料が低いほうが、より雇用契約・労働契約とみなされやす傾向があります。
このため、「委託者」(=本来は使用者)が、雇用契約・労働契約を業務委託契約に切り替えた場合、高額な報酬・委託料を支払わない限り、業務委託契約とはみなされずに、結局は雇用契約・労働契約とみなさる可能性が高いです。
ポイント
実態が雇用契約・労働契約である業務委託契約には、以下のようなペナルティがある。
- 受託者(=実態は労働者)からの残業代の請求
- 税務署からの源泉所得税+追徴課税の徴収
- 日本年金機構(悪質な場合は国税庁)からの社会保険料の徴収
- 受託者(=実態は労働者)からの最低賃金の支払
【注意点4】業務委託契約が偽装請負とみなされる
業務委託契約書を作成しないことによって、(意外に思われるかもしれませんが)委託者と受託者の両者にとってリスク・デメリットとなるのが、いわゆる「偽装請負」による、労働者派遣法違反です。
労働者派遣法そのものにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
常駐型の業務委託契約は労働者派遣契約(=偽装請負)とみなされやすい
企業間の業務委託契約では、取引の実態によっては、業務委託契約ではなく、労働者派遣契約とみなされる可能性があります。
特に、常駐型の準委任の業務委託契約(いわゆるシステムエンジニアリングサービス契約・SES契約など)の場合、作業や労力の提供をしてもらうことになるため、労働者派遣契約と区別がつきません。
このため、契約実務では、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(いわゆる「37号告示」)に準拠して、業務委託契約書を作成する必要があります。
また、単に形式的に業務委託契約書を作成するのではなく、実態としても、労働者派遣契約ではなく、業務委託契約としての取引であることが重要です。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
偽装請負はあらゆる労働者派遣法に違反
労働者派遣法では、労働者派遣をする際、派遣元事業者と派遣先事業者の双方に、さまざまな義務を貸しています。
このため、業務委託契約が偽装請負とみなされた場合、これらの労働者派遣法にもとづくさまざまな義務を果たしていないことになります。
より具体的には、「受託者(=本来の派遣元事業者)」は、無許可で労働者派遣事業をしていることになります。これは、当然、労働者派遣法違反となります。
「委託者」(=本来の派遣先事業者)も労働者派遣法違反
よく誤解されがちですが、偽装請負とみなされた場合、「受託者(=本来の派遣元事業者)」だけが労働者派遣法違反となるわけではなく、「委託者(本来の派遣先事業者)」も労働者派遣法違反となります。
労働者派遣法は、派遣先事業者にも、一定の義務を課しています。このため、業務委託契約が偽装請負とみなされた場合は、「委託者」もまた、労働者派遣法となります。
労働者派遣法は、あくまで派遣労働者を保護するための法律ですので、「委託者」は、規制対象として、厳しく規制されているのです。
なお、偽装請負につきましては、以下のページもご参照ください。
ポイント
- 常駐型の業務委託契約、特にシステムエンジニアリングサービス契約・SES契約は、労働者派遣契約(=偽装請負)とみなされやすい
- 偽装請負は、受託者だけでなく、委託者の、あらゆる労働者派遣法に違反する。
【注意点5】建設工事請負契約の場合は建設業法違反となる
建設業務委託契約書を作成しないことによって、委託者と受託者の両者にとってリスク・デメリットとなるのが、建設業法違反です。
建設業法第19条で契約書の作成義務がある
建設工事が業務内容(ただし、請負契約に限る)となる建設工事請負契約では、建設業法第19条第1項により、契約書の作成が義務づけられています。
建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)
1 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
(1)(以下省略)
引用元:建設業法 | e-Gov法令検索
ここで注意しなければならないのは、主語が「建設工事の請負契約の当事者は」となっている点です。
この点から、建設工事請負契約の委託者(注文者)と受託者(請負人)の双方に、建設工事請負契約書の作成が義務づけられています。
このほか、契約書がない建設工事請負契約のリスクにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
500万円未満の工事でも建設工事請負契約書を作る義務がある
よく誤解されがちですが、施工金額が500万円未満の建設工事では、建設工事請負契約書を作成しなくてもいい、というわけではありません。建設業法第19条により作成しなければならない契約書は、施工金額は関係ありません。
「施工金額が500万円」というのは、あくまで建設業の許可が必要な工事のひとつの基準に過ぎません。
このため、どんなに施工金額が少ない建設工事であっても、委託者(注文者)と受託者(請負人)には、建設工事請負契約書を作成する義務があります。
この他、建設工事請負契約書の作成義務と施工代金の金額の関係性につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 建設工事の業務委託契約では、契約書の作成は、建設業法第19条に規定された必須の義務。
- 建設工事請負契約書は、工事の金額に関係なく、作成しなければならない。
【注意点6】著作権を巡ってトラブルとなる
業務委託契約書を作成しないことによって、(主に)委託者にとってリスク・デメリットになるのが、著作権のトラブルです。
著作権そのものにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
著作権は移転しなければ著作者のもの
著作権が発生するタイプの業務委託契約では、業務委託契約書を作成して著作権の処理を規定しないと、著作権を巡ってトラブルになることがあります。
著作権は、著作物を創作した著作者の権利です。ですから、業務委託契約で著作権の処理を決めていないと、その著作権は著作者のもののままです。
もちろん、理論上は、口約束でも著作権の譲渡は可能ですので、著作権の譲渡に業務委託契約書が必要というわけではありません。ですが、証拠としての業務委託契約書が残っていない場合は、後々になって著作者と「言った、言っていない」で揉めるリスクがあります。
これは、その著作物が原因で大きな収益が発生した場合に、その収益の「取り分」を巡って、特に問題になりがちです。
「著作権はお金を払った委託者のもの」とは限らない
この点について、特に委託者の側の立場から、「お金を払った以上は、わざわざ業務委託契約書を作るまでもなく、著作権は当然委託者のものでしょう?」というお話を聞くことがあります。しかし、必ずしも、そうとは限りません。
受託者(=著作者)の立場に立てば、「お金は著作物の作成の費用として貰っただけで、著作権の譲渡をするとは合意していない。あくまで、著作権は、一定の条件で使用許諾をしているだけだ」という主張も成り立ちます。
このような利害の対立が考えられるからこそ、著作権が発生する業務委託契約では、著作権の処理について、明確に業務委託契約書に規定する必要があります。
著作権法は著作権者を強力に保護する法律
意外と軽視しがちな視点ですが、著作権という権利は、わざわざ「著作権法」という、ひとつの法律によって保護されている権利です。著作権法は、著作権とその保有者である著作権者を保護するための法律です。
実は、この著作権法によって、著作権が発生する業務委託契約における受託者は、圧倒的に強力に保護されています。このため、業務委託契約書で著作権の処理や取扱いについて特約を結ばない限り、著作権法によって、受託者は、非常に強く保護されることになります。
ですから、委託者の立場として、著作権が発生する業務委託契約を結ぶのであれば、業務委託契約書の作成は必須です。
この点につきましては、以下のページもご参照ください。
業務委託契約書がないと著作者人格権を行使されるリスクがある
また、著作者には、著作権とは別に、著作者人格権が発生します。
著作者人格権は、公表権、氏名表示権、同一性保持権の3種類の権利に分類されます。
【意味・定義】著作者人格権とは?
著作者人格権とは、公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つの権利の総称をいう。
この著作者人格権は、譲渡することができない権利です。
著作権法第59条(著作者人格権の一身専属性)
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
引用元:著作権法 | e-Gov法令検索
このため、契約実務では、著作者人格権を行使されないように、「著作者人格権の不行使」の特約を規定した業務委託契約書を作成します。
このような業務委託契約書がない場合、受託者から、著作者人格権を行使されてしまうリスクがあります。
著作者人格権を行使されるリスク
- 公表権:成果物の公表が制限される。
- 氏名表示権:成果物についてクレジット表記を要求される(著名・ブランドがある受託者であれば問題が少ない)。
- 同一性保持権:成果物を改変する権利(翻案権)が制限される。
ポイント
- 著作権は、移転しなければ著作者のもの。
- 必ずしも、「著作権はお金を払った委託者のもの」となるとは限らない。
- 業務委託契約書がないと著作者人格権を行使されるリスクがある。
- 著作権が発生する業務委託契約では、著作権の処理が規定された業務委託契約書を取り交わさないと、委託者(委任者)は圧倒的に不利な立場になる。
【注意点7】業務委託契約が資金決済法違反となる
業務委託契約書を作成しないことによって、受託者にとってリスク・デメリットになるのが、資金決済法の違反です。
「決済代行」は適法に対処しないと資金決済法違反となる
業務委託契約のなかには、いわゆる「決済代行」サービスが業務内容となっている場合があります。
このような決済代行サービスは、適法な業務委託契約とないと、資金決済法違反となります(ただし、代金引換、収納代行、エスクローサービスの場合は、規制対象外です)。
資金決済法では、「為替取引」を業として営むことを「資金移動業」として定義づけています。
資金決済法第2条(定義)
1 (省略)
2 この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。
3 (以下省略)
資金移動業は、登録制であり(資金決済法第37条)、無登録での営業は、銀行業法第4条違反となります。
銀行業法第4条違反は、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科」(銀行業法第61条第1号)という重い罰則が科されます。
【意味・定義】為替取引とは
為替取引の定義は、資金決済法にも、銀行法にも規定がありませんが、最高裁の判例があります。
この最高裁の判例によると、「為替取引を行うこと」は、以下のとおりです。
銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」とは、顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、又はこれを引き受けて遂行することをいう。
引用元: 最高裁判決平成13年3月12日
このように、為替取引は、資金決済法・銀行業法に明確な定義がなく、判例では、非常に広範囲な資金の移動として定義づけられています。
なお、当然ながら、為替取引は、FXや外貨両替のことではありません。
「個人間送金」の受託が発生する業務委託契約は「為替取引」に該当する
なお、いわゆる「割り勘アプリ」のような個人間送金が発生するサービスは、為替取引に該当するものとされています(資金決済法第2条の2)。
よって、一般消費者からの委託を受けて支払代行をおこなう業務委託契約の場合は、注意を要します。
代金引換・収納代行・エスクローサービスは資金決済法の規制対象外
なお、運送業者による「代金引換」(いわゆる代引)や、コンビニによる公共料金の収納代行のような単純な収納代行をともなう業務委託契約は、現行法では規制対象外です。
また、エスクローサービスも、同様に規制対象外です。
参照:『金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案 説明資料』p.10
【意味・定義】エスクローサービスとは?
エスクローサービスとは、取引の当事者の間に第三者であるプラットフォーマーやサービス提供事業者の仲介者が入って一方の当事者から金銭を預かり、商品の受取りやサービスの実施を確認できてから、他方の当事者にその代金が支払われる仕組みのことをいう。
業務委託契約書に金銭の流れと委託業務の内容を明記する
いわゆる決済代行サービスが伴う業務委託契約では、取引の実態によっては、上記の「為替取引」に該当します。この場合、資金移動業の登録をしなければなりません。
資金移動業の登録は、非常に条件が厳しく、一般的な企業では、登録が難しいものです。
ですので、決済代行サービスが伴う業務委託契約では、為替取引や資金決済法違反に該当しないように、慎重に契約内容を検討する必要があります。
また、規制対象外となる代金引換、収納代行、エスクローサービスに該当するよう、金銭の流れや委託業務の内容について決める必要があります。
ポイント
- 決済代行など、他人のお金を取扱う業務委託契約では、資金決済法に適合した適法な業務委託契約としなければ、資金決済法違反となる。
- 個人間送金等は「為替取引」となり、資金決済法の規制対象となる。
- 単純な収納代行は、資金決済法の規制対象外。
【注意点8】業務委託契約書がないと税法違反・税務調査に対応できない
業務委託契約書を作成しないことによって、委託者・受託者の両者にとってリスク・デメリットになるのが、税法違反・税務調査への対応です。
税務調査ではあらゆるお金の流れをチェックされる
業務委託契約書を作成していないと、税務調査に対応できなくなります。
税務調査では、税務署・国税庁の職員から、経理・税務について、さまざまな調査や質問がおこなわれます。それこそ、ありとあらゆるお金の流れについて、徹底的に調べられます。
この際、適正な経理・税務をおこなっているかどうか、裏付けとなる資料の提示を求められる場合があります。
契約書は税務署・国税庁を納得させる証憑書類
こうした場合、業務委託契約書は、いわゆる「証憑書類」として、企業間取引の重要な裏付資料となります。
逆に、業務委託契約書がない、言いかえれば、口約束だけで取引をしていると、税務署・国税庁の職員の質問に対して、納得されるような回答が、難しくなります。
もちろん、業務委託契約書がないからといって、取引の実態を説明することができない、というわけではありません。
請求書、領収書、業務委託契約によって完成した成果物などを提示することにより、間接的に、取引の実態を説明することはできます。
ただ、最初から業務委託契約書を作っておけば、より簡単に説明することができます。
いい加減な業務委託契約書はかえって怪しまれる
もっとも、単に形式だけ業務委託契約書を整えておけばいい、というわけではありません。
特に、雛形の業務委託契約書を使う場合は、取引の実態に合っていないこともあります。
この場合、税務署・国税庁の職員への説明と、雛形の業務委託契約書の内容が食い違うことがよくあります。
こうなると、税務署・国税庁の職員に、かえって怪しまれることになります。
これは、雛形の業務委託契約書だけでなく、いい加減な業務委託契約書であっても同じです。
税務調査の際に、税務署・国税庁の職員が取引の実態について納得してもらうには、実態が反映された業務委託契約書が必要です。
報酬・委託料が「給与」として源泉徴収される
また、税務調査の際にはよくありがちな問題ですが、個人事業者・フリーランスとの業務委託契約が、雇用契約・労働契約とみなされることがあります。
なぜ契約形態が税務調査の際に問題となるのかといえば、「その契約にもとづく報酬・委託料が源泉徴収の対象となるかどうか」というポイントがあるからです。
なぜ税務調査で契約形態がチェックされるのか?
個人事業者・フリーランスとの業務委託契約が雇用契約・労働契約とみなされると、給与所得として源泉徴収の対象となるから。
個人事業者・フリーランスとの業務委託契約では、一部の例外を除いて、報酬・委託料は源泉徴収の対象となりません。
ところが、この業務委託契約が雇用契約・労働契約とみなされると、報酬・委託料は「給与」とみなされ、源泉徴収の対象となります。
このように、業務委託契約が雇用契約・労働契約とみなされると、追徴課税をされた源泉所得税を払わなければならなくなります。
この点からも、業務委託契約が雇用契約・労働契約とみなされないために、適切な業務委託契約書を作成しておく必要があります。
ポイント
- 税務調査では、あらゆるお金の流れをチェックされる。
- 契約書は、税務署・国税庁を納得させる証憑書類となる。
- いい加減な業務委託契約書を作成していいた場合、かえって税務署の担当者から怪しまれる。
- 個人事業者・フリーランスとの業務委託契約では、源泉所得税を追徴課税されるリスクがある。
契約書がない場合の業務委託のリスク・デメリット・注意点に関するよくある質問
- 契約書がない場合の業務委託のリスク・デメリット・注意点にはどのようなものがありますか?
- 契約書がない業務委託契約では、1.業務委託契約の内容を巡ってトラブルとなる、2.下請法違反となる、3.業務委託契約が雇用契約・労働契約とみなされる、4.業務委託契約が偽装請負とみなされる、5.建設工事請負契約の場合は建設業法違反となる、6.著作権を巡ってトラブルとなる、7.業務委託契約が資金決済法違反となる、8.税法違反・税務調査に対応できない―等のリスクやデメリットがあります。
- 業務委託契約書がないと、下請法違反となりますか?
- 下請法が適用される場合、親事業者が下請事業者に対し、業務委託契約書などの適法な書面(いわゆる三条書面)を交付しないと、下請法第3条に違反します。
- 業務委託契約書がないと、業務委託契約ではなく、雇用契約・労働契約とみなされますか?
- 適法な業務委託契約の内容が記載された契約書がない場合は、業務委託契約ではなく雇用契約・労働契約とみなされるリスクがあります。
- 業務委託契約書がないと、偽装請負・労働者派遣法違反となりますか?
- 適法な業務委託契約の内容が記載された契約書がない場合は、業務委託契約ではなく労働者派遣契約とみなされ、偽装請負・労働者派遣法違反となるリスクがあります。
- 建設工事業務委託契約がない場合、建設業法違反となりますか?
- 建設工事業務委託契約や建設工事請負契約では、契約書がない場合、発注の金額に関係なく、建設業法第19条違反となります。
- 著作権等の知的財産権が発生する契約で契約書がない場合、どのようなトラブルがありますか?
- 著作権等の知的財産権が発生する業務委託契約で契約書がない場合、知的財産権が受託者から委託者に譲渡されるのかどうかが不明となり、権利の所在を巡ってトラブルになることがあります。
- 業務委託契約書がない場合、税務調査ではどのような問題となりますか?
- 業務委託契約書がない場合、契約内容について税務署・国税庁の職員に対し客観的に説明ができず、調査が長引いたり、個人事業者・フリーランスとの業務委託契約が雇用契約・労働契約とみなされたりするリスクがあります。