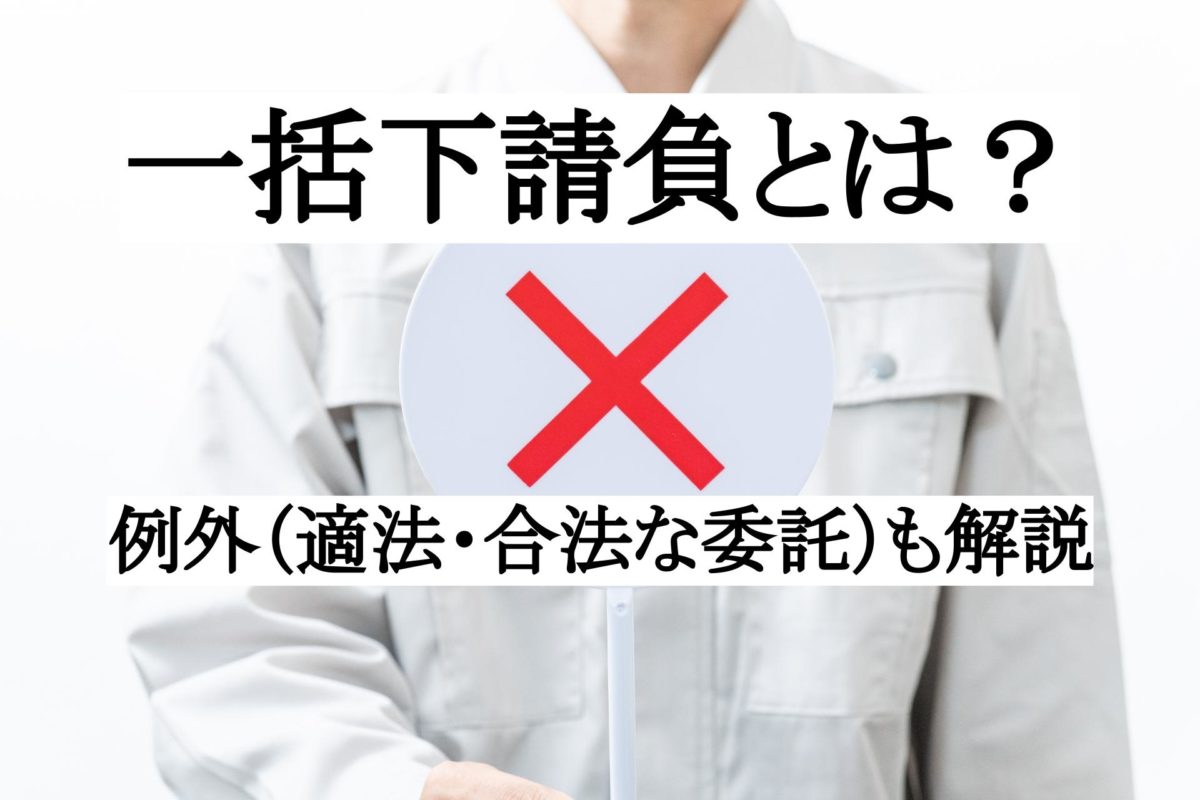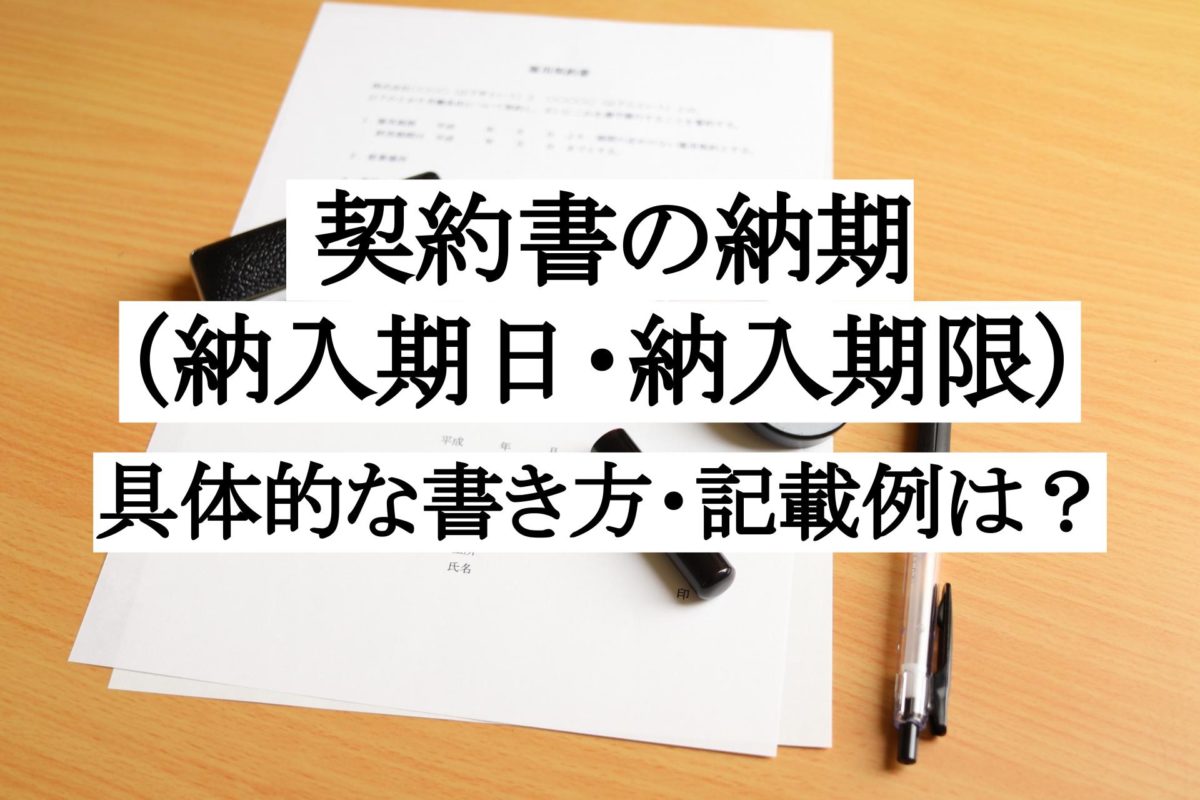業務委託契約書において、目的物の引渡しの時期や役務(サービス)の提供の時期(以下、「納期」とします。)は、特に委託者側にとって、極めて重要な条項です。
納期は、委託者・受託者双方に食い違いが出ないように、年月日で明記します。
ただし、年月日で明記できないような契約内容の場合は、納期を明確に決めるスケジュールと手続きを明記します。
こうすることで、実際に納入するまでには、納期が明確に決まるようにします。
このページでは、こうした納期の規定について、解説します。
納期=納入・納品の期日・期限
納期とは、納入期限・納入期日・納品期限・納品期日の略称のことで、一般に、債務の弁済・履行として何らか物品・成果物の納品・納入の期限・期日のことを意味します。
【意味・定義】納期とは?
納期とは、一般に、何らか物品・成果物の納品・納入の期限・期日をいう。
なお、「一般に」と記載したとおり、納期は、ビジネス用語としては使われていますが、正式な法律用語ではありません。
「納期」自体に、法的な定義があるわけではありません。
民法でも、「納期」という言葉は使われていません。
納入期限・納品期限と納入期日・納品期日の違い
期限と期日は別物
なお、法律上、納入期限・納品期限と納入期日・納入期日は別のものです。
ですから、業務委託契約では、納入期限・納品期限なのか納入期日・納品期日なのかがわかるように明記する必要があります。
納入期限・納品期限と納入期日・納品期日は、文字どおり、「期限」なのか「期日」なのかの違いがあります。
納入期限・納品期限と納入期日・納品期日の違い
- 納入期限・納品期限は「期限」であり、指定された「日まで」に納入するという意味。
- 納入期日・納品期日は「期日」であり、指定されたピンポイントの「日」に納入するという意味。
業務委託契約の場合、納入期日・納品期限ではなく、納入期限・納品期限を設定されると、注文者(委託者)にとって問題となることがあります。
製造請負契約では納品期限と納品期日ではまったく意味が違う
これは、特に製造請負契約の場合に問題なります。
製造請負契約では、注文者(委託者)の側で、物品・製品の保管や受け入れ体制が整っていなければ、いくら早く納入・納品されても困ることがあります。
このため、大量の物品・製品や、特殊な管理が必要な物品・製品の製造請負契約の場合は、納入期限・納品期限ではなく、納入期日・納品期日を設定することがあります。
なお、納期に関連する用語の詳細な違いにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
「納期」とは書いてはいけない
このように、納入期日と納入期限では、意味が大きく違ってきます。
このため、契約書の条項として、「納期」という表現は、安直に使ってはいけません。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】納期等に関する条項
第○条(納期)
本件製品の納期は、2022年9月30日とする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
このような記載では、この日付が「納入期限」・「納品期限」なのか「納入期日」「納品期日」なのかが、ハッキリしません。
ですから、「納期」ではなく、期限か期日なのかを明確に記載するべきため、「納入期限」・「納品期限」か「納入期日」「納品期日」で明記するべきです。
ポイント
- 納期とは、納入期限と納入期日の略称に過ぎない。
- 納入期限は「期限」なので、指定された「日まで」に納入するという意味。
- 納入期日は「期日」なので、指定されたピンポイントの「日」に納入するという意味。
- 契約書に「納期」と書くと、納入期限なのか納入期日なのかが判然としない。
準委任型の業務委託契約では業務実施日・業務実施期間を設定する
なお、物品・製品・成果物の納入がなく、特定の業務を実施する(主に準委任型の)業務委託契約の場合は、納期=納入期限・納入期日は規定しません。
その代わり、こうした業務を実施する日や期間(下請法では、「役務が提供される期日又は期間」と表現されています)を規定します。
また、場合によっては、その日や期間のうち、業務の実施がされる時間帯についても規定します。
なお、こうした日程の記載の量が多くなる場合は、契約内容の本文ではなく、別紙にスケジュール表などを記載することで、規定します。
納期等は日付・年月日を明記する
誤解がないように特定の日付・年月日を記載する
納入期限・納入期日・業務実施日・業務実施期間(以下、「納期等」といいます)は、具体的な特定の日付・年月日で納期等を指定します。
納期等は、委託者・受託者双方にとって、極めて重要な条項です。
納期等の解釈にズレが生じた場合、物品や製品のサプライチェーンに重大な影響を与えます。
特に、大量の物品や製品の納入がともなう業務委託契約や、大規模なシステム等に関する業務委託契約の場合、1日でも納期等の解釈にズレが生じると、広範囲な悪影響が出ます。
このため、業務委託契約では、できるだけ日付方式で特定の日付・年月日で納期等を設定し、契約当事者双方に誤解が生じないようにするべきです。
毎月の日にちを指定する納期等も可能
継続的業務委託契約では毎月1回以上の納期等もある
ただ、必ずしもすべての業務委託契約において、納期等が日付で特定できるとは限りません。
特に、継続的な業務委託契約の場合は、定期的な納入や業務の実施があるとなることが多いです。
具体的には、例えば、毎月1回の納期等としています。
このような場合は、「毎月25日」、「毎月末日」、「毎月第4金曜日」のように、日にちだけでも特定できるように規定します。
なお、2月は28日(うるう年で29日)しかありませんので、日にちで指定する場合は、通常は毎月28日か毎月27日(忙しい月末=28日を避けるため)とします。
継続的な業務委託契約は営業日に要注意
なお、このように月1回の納期等を設定する場合、委託者・受託者双方の営業日に注意してください。
納入や業務の実施をしようとしても、委託者・受託者のいずれかが休業日であった場合、納入や業務の実施ができないことなります。
例えば「毎月末日」を納期等とした場合、必ずしも毎月末日が委託者・受託者の営業日とは限りません。
ある月の末日に休業日であった場合に、納入や業務の実施がないときは、休業日であった当事者は、契約違反となります。
営業日について特約を規定する
このため、業務委託契約において、納期等が委託者・受託者のいずれかの休業日だった場合に、納入や業務の実施を前倒しまたは順延できるような特約を規定しておくべきです。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】納期等に関する条項
第○条(納期等)
受託者による納入期日は、毎月末日(当該日が受託者の休業日に該当する場合は、その後の最初の営業日)とする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
この規定は、納入について順延する規定の例です。
こうした納期等の順延の特約を規定しておくことで、納期等に委託者が休業日だったとしても、契約違反とはなりません。
なお、こうした規定をする際は、必ず、「営業日」を定義づけてください。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】営業日の定義に関する条項
第○条(営業日)
本契約において、「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第1条第1項各号列記に規定する日以外の日をいう。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
上記の記載例は、行政機関の「営業日」と同じ日を営業日とする場合の記載例です。
業務委託契約書を作成する理由
法律上は営業日の定義がないことから、契約内容として営業日を日付の計算で使用したい場合は、特約として営業日の定義を規定した契約書が必要となるから。
この他、より詳細な納期(納入期限・納入期日)の書き方・記載方法につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 納期等は、誤解がないように、特定の日付・年月日で規定する。
- 毎月特定の日付を納期等とすることもできる。
- この場合、業務委託契約で契約当事者の休業日の場合における納期等の前倒し・順延について合意しておく。
- 契約書で「営業日」の表記を使う場合は、必ず定義を規定する。
納期等は下請法の三条書面の必須記載事項
下請法が適用される業務委託契約の場合、納期等は、いわゆる「三条書面」の必須記載事項です。
三条書面につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
下請法が適用されるかどうかにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
業務委託契約で納入・業務実施の手続きを規定する
納入・業務実施の「完了・終了」を規定する
納入や業務実施の規定では、単に納入や業務実施について規定するだけでは不十分です。
こうした内容に加えて、何をもって納入・業務実施が完了・終了したのかを明記します。
具体的には、受託者は、実際に物品・製品・成果物の納入や、業務の実施をした場合、納入・実施と引き換えに、必ず受領証書や完了証書を徴収します。
また、委託者は、納入の際、受託者から、納品書を受取ります。
意外と重要な「納入があった日」
受領証書や完了証書は、納入・業務の実施があったことの証拠になります。
また、同様に納入・業務の実施があった日の根拠になります。
こうした納入・業務の実施があった日は、以下の契約条項で重要となります。
業務委託契約に規定がなくても受領証書は発行される
このように、納入・業務の実施があった日は非常に重要です。
なお、業務委託契約に受領証書や完了証書に関する規定がなかったとしても、受託者は、民法第486条により、こうした証書の交付を請求できます。
民法第486条(受領証書の交付請求)
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
このため、委託者は、業務委託契約に規定がないことを理由に、受領証書や完了証書の交付を拒否できません。
納入の受領を拒否されることもある
なお、物品・製品・成果物の納入がある業務委託契約の場合、委託者は、必ずしもこれらを受領するとは限りません。場合によっては、受領を拒否することがあります。
受託者としては、こうした委託者による受領拒否に対応した条項を、業務委託契約に規定する必要があります。
また、下請法が適用される業務委託契約では、こうした受領拒否は、下請法違反となることがあります。
このほか、受領遅滞・受領拒否につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 納入・業務実施の手続き、つまりそれぞれの「完了・終了」を規定する。
- 「納入があった日」は重要であるため、受領証書・完了証書で特定させる。
- 業務委託契約に規定がなくても、受託者は、委託者に対し、民法第486条にもとづき、受領証書の発行を請求できる。
- 委託者が物品・製品・成果物の受領を拒否することがあるため、受託者は、業務委託契約で対応を規定する。
納期等を規定できない場合の納期等の決め方は?
納期等を規定できない場合は手続き・スケジュールを明記する
一般的な業務委託契約では、納期等は非常に重要な契約条項ですので、規定できない、ということはまずありません。
ただ、ごく一部の特殊な事例ですが、やむを得ず納期等を規定できない場合もあります。この場合は、当初の業務委託契約書では納期等を記載しません。
その代わり、あらかじめ納期等を確定させる手続きやスケジュールを明記します。
そのうえで、実際に納期等が確定した場合は、覚書・合意書・確認書・仕様書などの書面を作成して、納期等を明記します。
この際、必ず委託者・受託者双方が署名または記名押印のうえ、相互にこれらの書類を取り交わします。
システム等開発業務委託契約では納期が規定できない場合もある
例えば、システム等開発業務委託契約では、業務内容(仕様等)を確定させることから、業務内容・契約内容となっているものがあります。
このような契約内容では、当初の契約締結の時点では、最終的な成果物であるシステム等の納期等は、規定しようがありません。
このため、仕様等が確定した段階で、スケジュール=納期等を決めます。
この際、すでに触れたとおり、仕様書等、通常は外部設計書(基本設計書)か、または別途の覚書・合意書・確認書などの書面を作成して、納期等を確定させます。
正当な理由がある場合は下請法でも認められている
なお、このような方法は、下請法が適用される業務委託契約においても認められる方法です。
ただし、「その内容が定められないことにつき正当な理由があるもの」についてのみに限定されます。
下請法第3条(書面の交付等)
1 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。
2 (省略)
そして、書面(補充書面)の交付については、「直ちに」しなければなりません。
「その内容が定められないことについて正当な理由がある」とは?
なお、「その内容が定められないことについて正当な理由がある」とは、次のとおりです。
(2) 「その内容が定められないことについて正当な理由がある」とは,取引の性質上,製造委託等をした時点では必要記載事項の内容について決定することができないと客観的に認められる理由がある場合であり,次のような場合はこれに該当する。ただし,このような場合であっても,親事業者は,特定事項がある場合には,特定事項の内容が定められない理由及び特定事項の内容を定めることとなる予定期日を当初書面に記載する必要がある。また,これらの特定事項については,下請事業者と十分な協議をした上で,速やかに定めなくてはならず,定めた後は,「直ちに」,当該特定事項を記載した補充書面を下請事業者に交付しなければならない。
○ ソフトウェア作成委託において,委託した時点では最終ユーザーが求める仕様が確定しておらず,下請事業者に対する正確な委託内容を決定することができない等のため,「下請事業者の給付の内容」,「下請代金の額」,「下請事業者の給付を受領する期日」又は「受領場所」が定まっていない場合
○ 広告制作物の作成委託において,委託した時点では制作物の具体的内容が決定できない等のため,「下請事業者の給付の内容」,「下請代金の額」又は「下請事業者の給付を受領する期日」が定まっていない場合
○ 修理委託において,故障箇所とその程度が委託した時点では明らかでないため,「下請事業者の給付の内容」,「下請代金の額」又は「下請事業者の給付を受領する期日」が定まっていない場合
○ 過去に前例のない試作品等の製造委託であるため,委託した時点では,「下請事業者の給付の内容」又は「下請代金の額」が定まっていない場合
○ 放送番組の作成委託において,タイトル,放送時間,コンセプトについては決まっているが,委託した時点では,放送番組の具体的な内容については決定できず,「下請代金の額」が定まっていない場合引用元: 下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準第3 2(2)
ここで重要な点は、単に納期等を決めなくてもいいというわけではない、ということです。
理由・スケジュールの明記が重要
次の2点を当初の三条書面を明記する必要がある。
- 特定事項の内容(=納期等)を定められない理由。
- 特定事項の内容(=納期等)を定めることとなる予定期日。
ポイント
- 納期等を規定できない場合は、納期等を確定する手続き・スケジュールを明記する。
- システム等開発業務委託契約では、納期が規定できない場合もある。
- 正当な理由がある場合は、下請法でも、納期等を規定しないことは認められている。
- ただし、この場合、委託者は、三条書面に「納期等が定められない理由」と「納期等を定めることとなる予定期日」を明記しなければならない。
【補足】履行期限と納入期限の違いは?
よくある質問ですが、履行期限と納入期限の違いについて尋ねられることがあります。
納入期限は、債務の履行としての納入の期限です。
このため、納入期限は、履行期限の一種であって、両者には、厳密には違いはありません。
この点につきましては、詳しくは、以下のページをご参照ください。
業務委託契約における納期に関するよくある質問
- 納期とは何ですか?
- 納期とは、一般に、何らか物品・成果物の納品・納入の期限・期日のことです。なお、民法では、特に「納期」「納入期限」「納品期限」「納入期日」「納品期日」などの用語の定義はありません。
- 納期はどのように決めますか?
- 納期は、通常は、年月日で指定することにより決めます。また、継続的な契約の場合は、「毎月25日」、「毎月末日」、「毎月第4金曜日」のように規定することもあります。